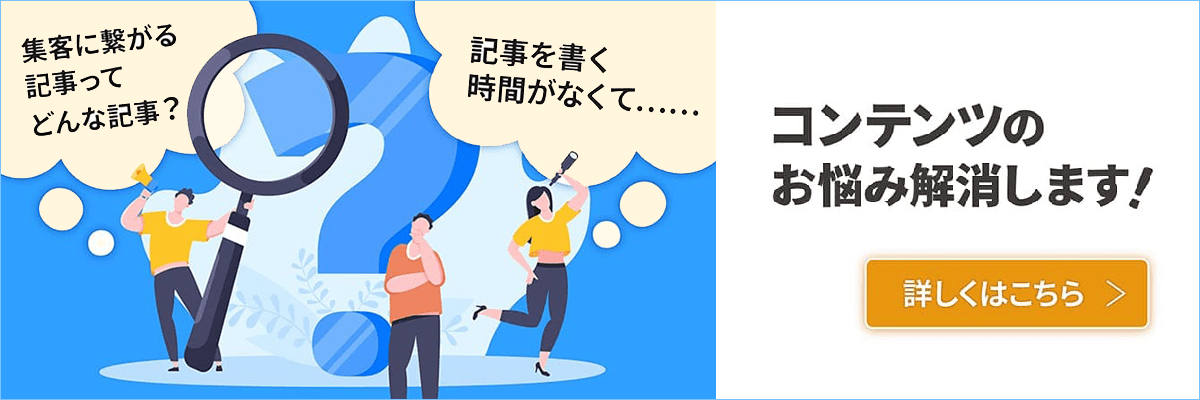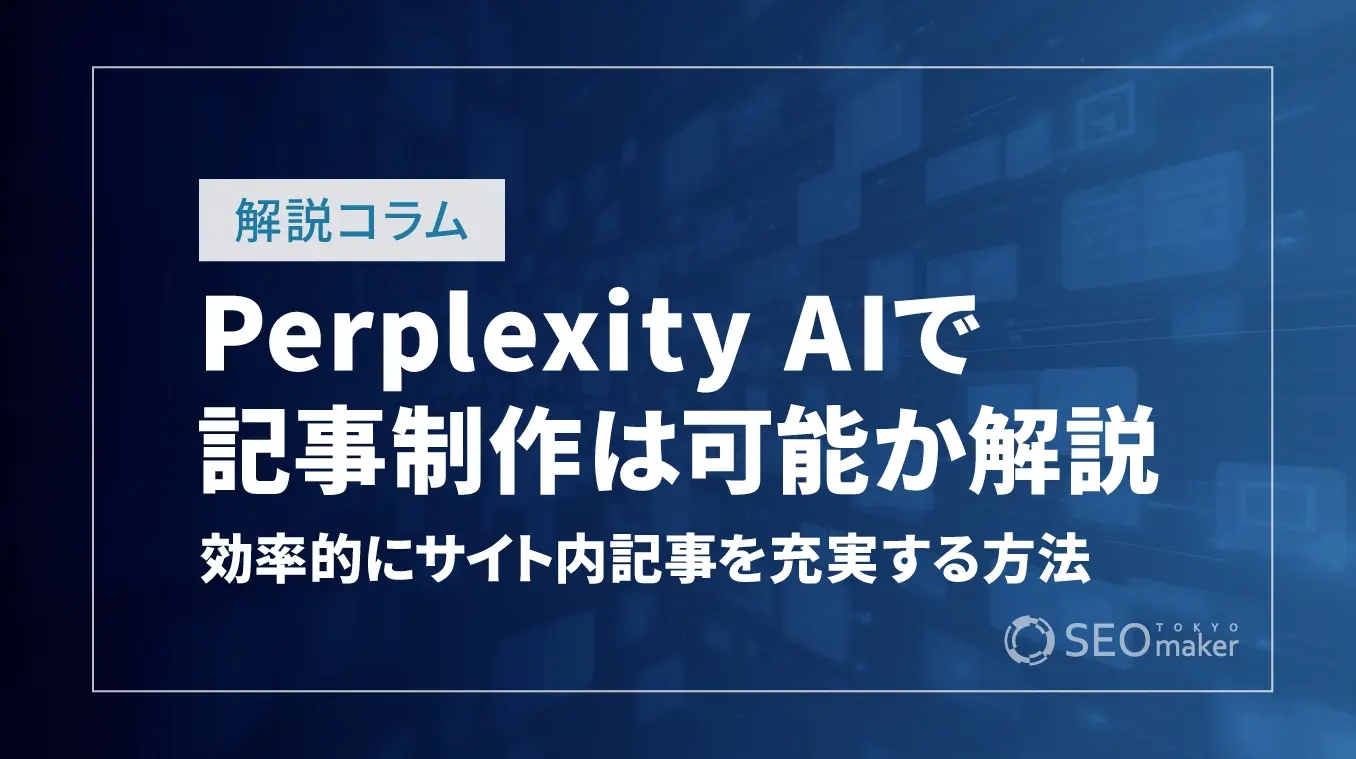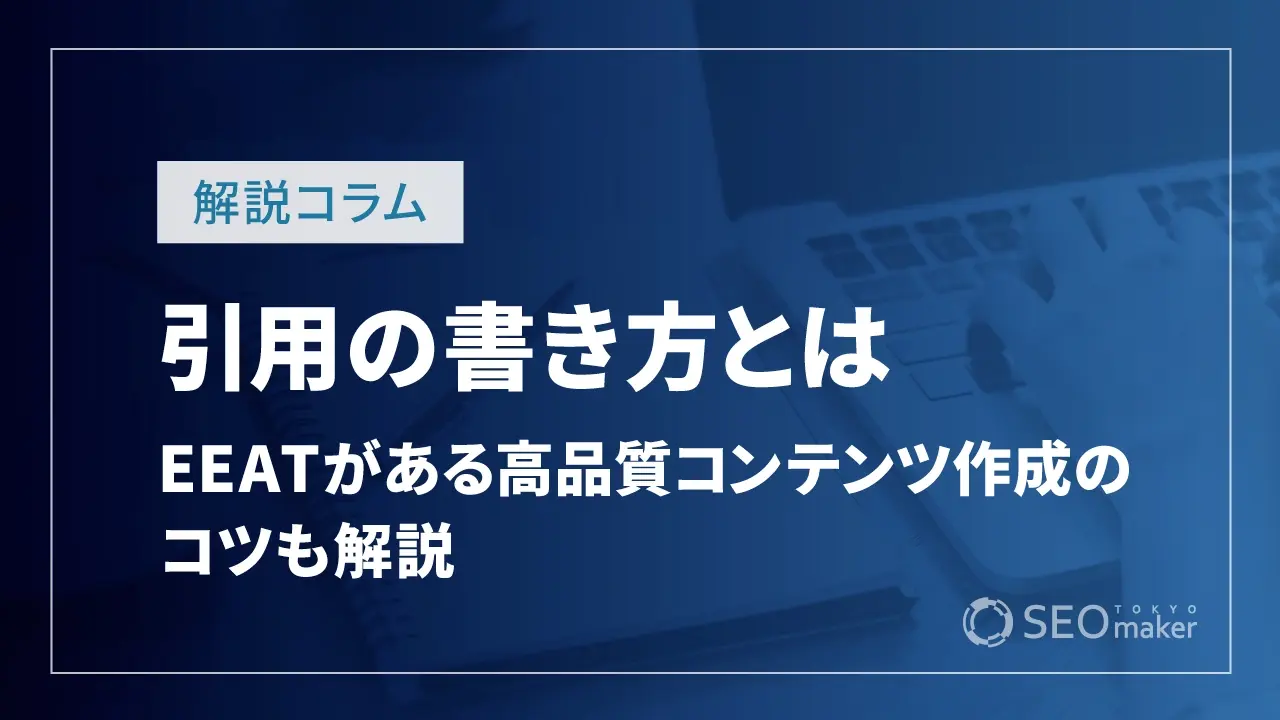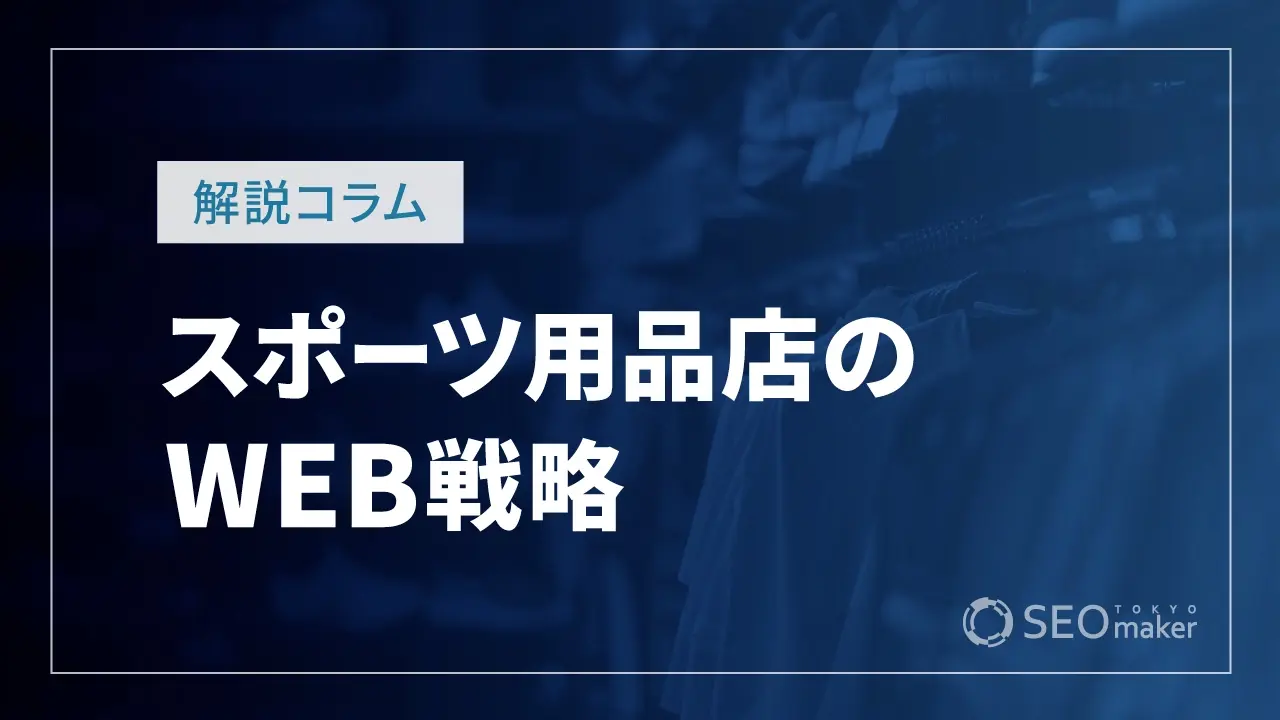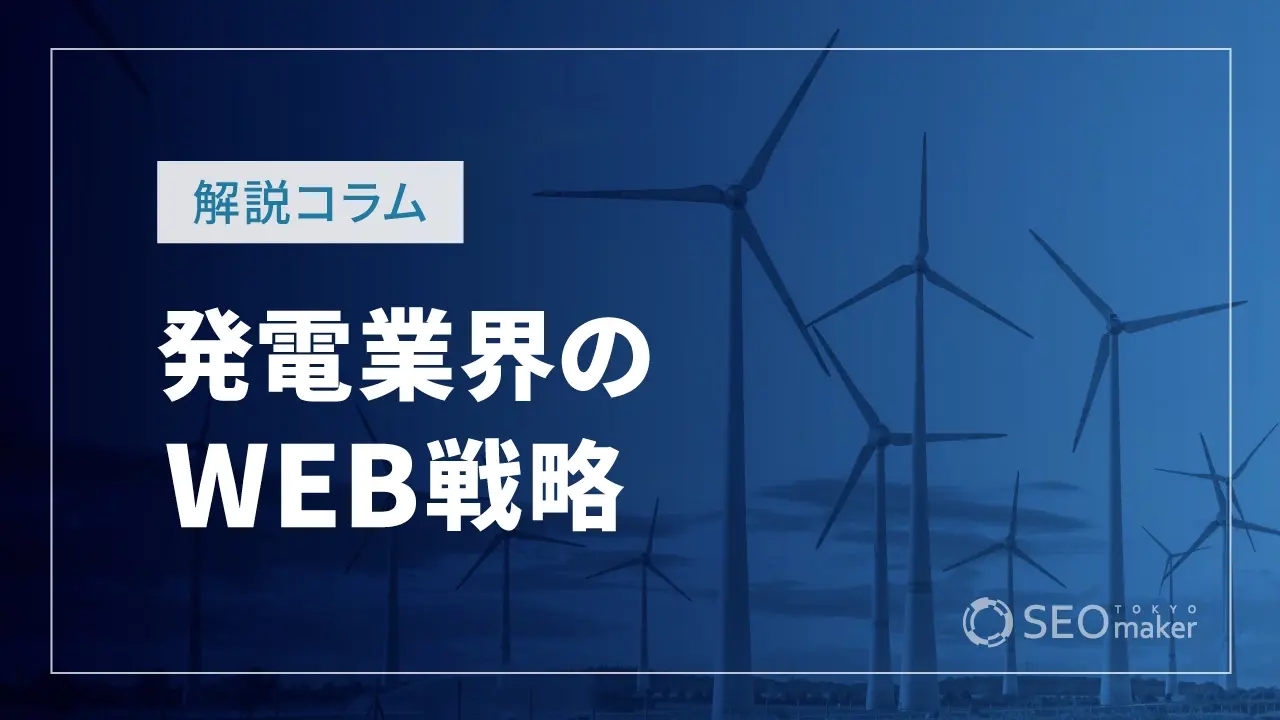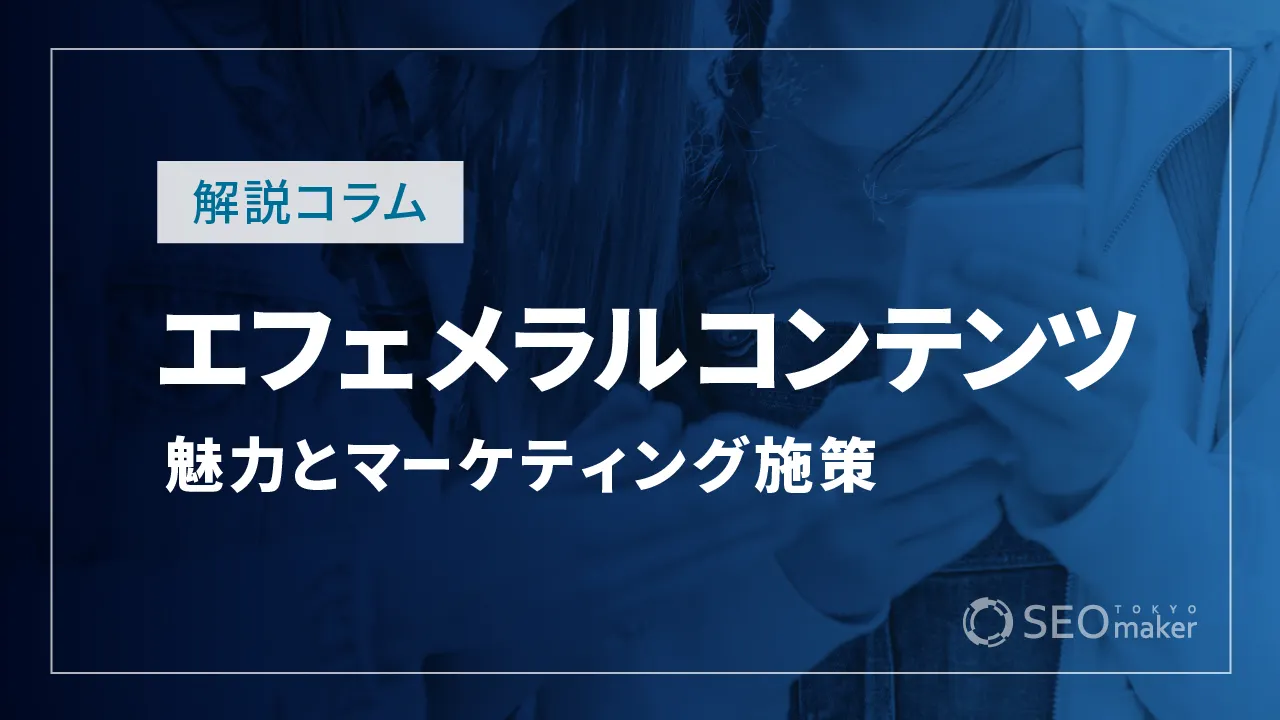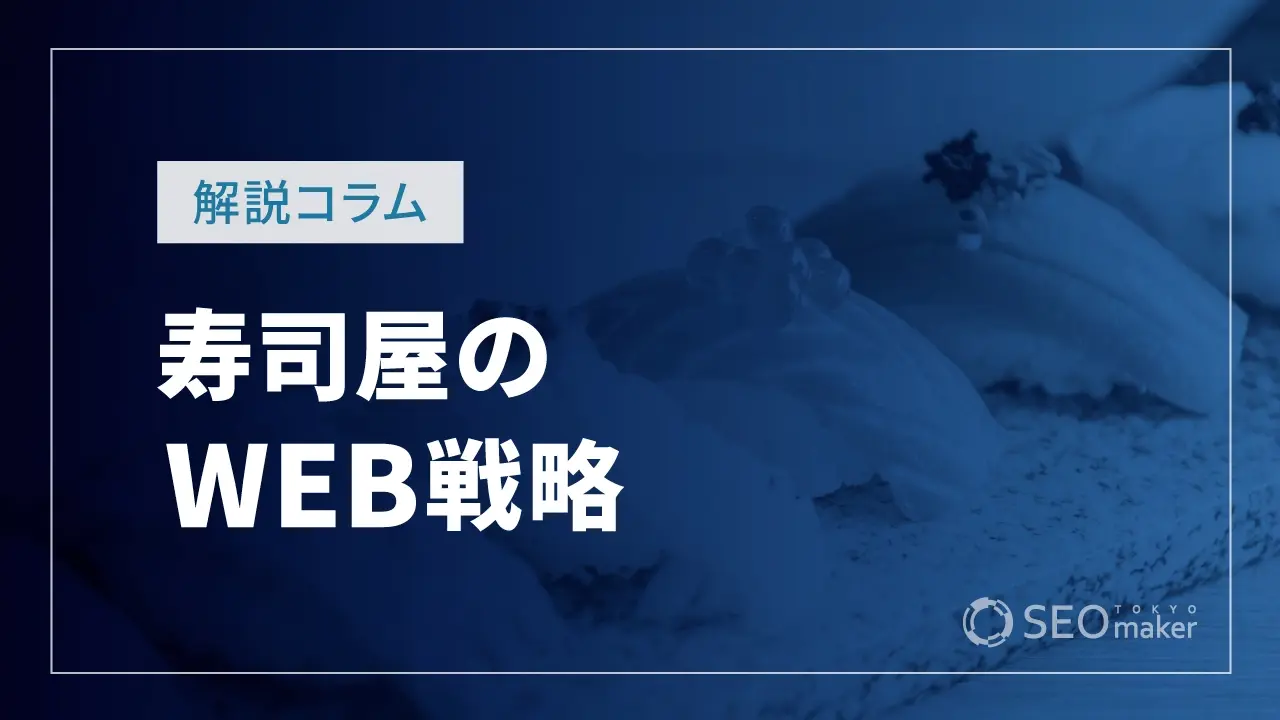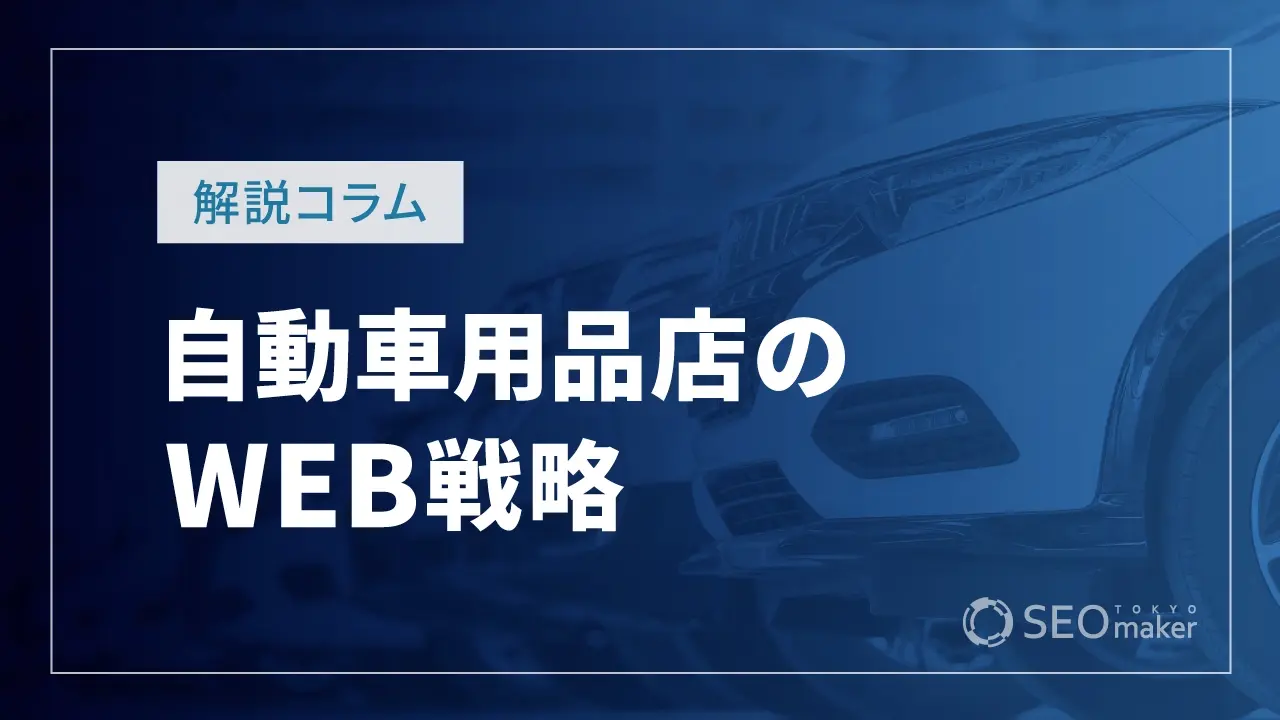転載とは?WEB担当者が知るべきルールやメリットについて解説
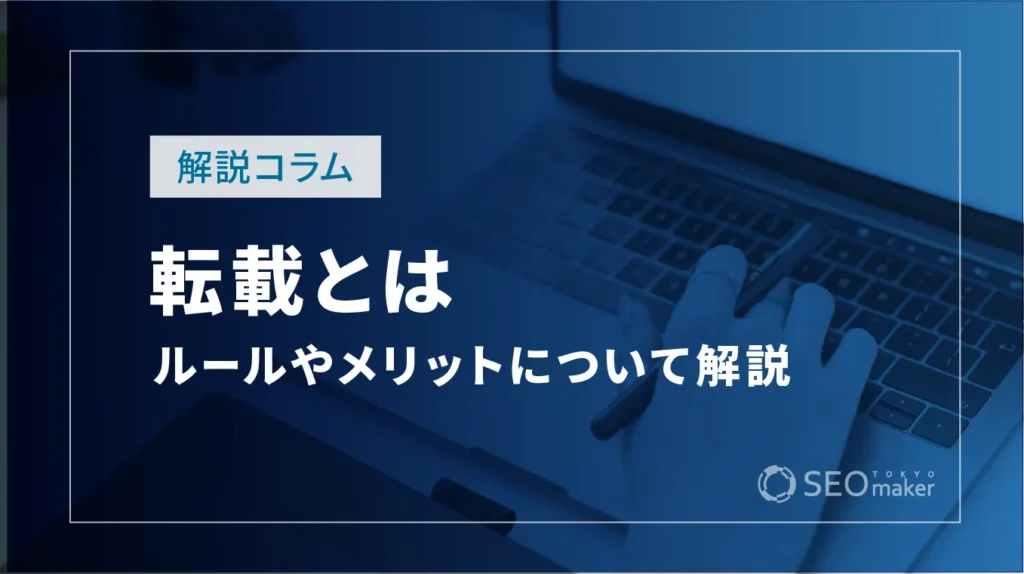 転載は、著作物の使用行為を指します。適切な手続きを踏まないと違反行為の恐れがあるので、慎重な対応が求められます。
転載は、著作物の使用行為を指します。適切な手続きを踏まないと違反行為の恐れがあるので、慎重な対応が求められます。
ルールを正しく理解せずに行うと、思わぬ法的トラブルにつながる可能性があるので、特に信頼できる情報を他のメディアから掲載することで、自社コンテンツの信憑性を高めたいと考えているWEB担当者は、転載の理解を深めるのが重要です。
転載とは
転載は、他者が作成した文章をコピー使用します。著作物を大部分そのまま使用し、ページの中で主要な要素として扱うことです。
注意点として、重要性や文脈なども考慮しながら、適切な判断が大切です。特に、内容が一切変更されずに公開する際は、原文転載と表現されるケースもあります。
引用との違い
転載は、引用の大部分をそのまま掲載します。これに対して、引用はページを補強する目的で、適切な範囲内で取り入れる行為です。
判断する際の重要なポイントは主従関係です。
引用部が役割を果たしているケースは、引用と認められる確率が高いです。引用が主となると、転載と見られる恐れがあります。引用時は、自分の書いた文章の方が全体の中で多くを占めていることが挙げられます。
引用部分が主ではなく、自分の考えや意見が主体となっている場合、それは適切な引用と見られます。
WEB担当者が知るべき転載ルール
ルールの把握によって、トラブルを未然に防ぐことにもつながります。
具体的には、以下の4つが挙げられます。
- 許可が必要
- リンクを明記する
- 明確にする
- 元文章を崩さない
それぞれの項目について解説していきます。
許可が必要
法律によって保護されています。私的利用の例外を除き、勝手に複製は認められていません。自社ページの中で著作物を多く利用すると違法行為のリスクがあります。
例えば、ニュースサイトや個人ブログのコピー行為は、違反になります。
また、Web公開情報や素材には、第三者の権利が関係していることが多いです。
第三者の権利には、以下が含まれます。
- 著作権
- 肖像権
- 商標権
- パブリシティ権
- データ利用権
これらの権利が関係している素材や情報をウェブで利用する際には、原則として権利者の許可が求められます。無許可で使用すれば、プライバシー侵害などの法的トラブルに発展する可能性があるので注意が求められます。
ルールを守れば一部利用は可能ですが、無断は避けるべきです。
リンクを明記する
出典を明確に示すことが求められます。特に、元記事がWEB上で公開する際は、そのURLを併せて記載しましょう。また、正しくリンクを貼ることで、信頼性の高い情報発信ができ、サイトの評価向上にもつながります。
さらに、情報がどこから来たのかを明らかにすると、読者はその情報の信頼性を判断する材料を得ることができます。
信頼できるメディアや専門家の情報を正しく引用し、出典を明示することで、ページの信頼性も高まります。
明確にする
文章が混同しないように、明確化が必要です。読者がどこまでが転載で、どこからが自分の意見なのかを明確に判断できるよう、インデントを活用したりして、視覚的に区別する工夫が求められます。
明記は、著作権を守るだけでなく、読者のためにも重要なルールです。逆に、引用が曖昧な記事は、読者を混乱させ、信頼を損なってしまうリスクがあります。
元文章を崩さない
原作者の意図を損なわないように、元の文章を崩さないように注意が必要です。文章や図表を変えてしまうと、本来の意味が変わってしまうリスクがあるので注意が必要です。原文を使用する際でも、コピペをした後に、内容が正しく保持されているか慎重に確認が必要です。
特に学術論文やニュース記事などは、正確な情報の伝達が求められるので、変更しないで引用が原則です。
どのような状況であっても、表現を変更しないよう心がけましょう。
WEB担当者が把握すべき転載のメリット
メリットを理解することで、転載効果を最大限に活用することにつながります。
ページがメディアに転載されると、より多くの人の目に触れる機会が増えます。特に影響力の高いページだと、ブランドや個人の知名度向上につながります。
具体的なメリットについては、以下にて解説していきます。
自社の周知に繋がる
自社の認知度を高められるというメリットがあります。特にWebメディアなどで取り上げられると、消費者は自社の公式サイトを直接訪問しなくても、必要な情報を得ることができます。
これにより、普段自社の情報に触れる機会がない人々にも、彼らが普段利用しているメディアを通じて間接的に情報を届けることが可能です。しかし、取材を受け、ニュースとして報道されるケースとは異なる点に注意が必要です。
ブランド価値の強化
転載によって、ブランド価値の強化にもつながります。
単独で発信していた場合には届かなかった層にも、自社の立ち位置やメッセージを伝える機会を広げることができます。実際に、転載されて被リンクが増えると、Googleの検索エンジンでの評価が上がる可能性があります。
検索順位が上がれば、より多くのユーザーにブランドを認知してもらいやすくなり、結果的にブランド価値が向上します。また、信頼性の高いメディアや影響力のあるプラットフォームに取り上げられることで、企業の情報発信の価値がさらに高まるケースがあります。
関連記事:ブランディングってどんな意味?正しい進め方を徹底解説!
アクセス数の向上
読者が元の情報を詳しく知りたいと思ったときに、リンクを通じて自社サイトへアクセスする流れが生まれます。
自社サイトへ訪問者を誘導できれば、詳細な情報や、自社の理念、関連する他のページなども読んでもらえる可能性が高まります。結果として、より多くの情報を届け、読者が自社に関心を持つきっかけにつながります。さらに、他の信頼できるメディアからの転載は信頼できる情報を発信していると認識されやすくなります。
一度訪れたユーザーがファンになると、継続的なアクセス増加につながります。
WEB担当者が理解すべき転載される注意点
これから自社ページの制作を検討している方は、注意点を事前に把握しておくことで、トラブルを防ぐことにもつながります。
具体的な注意点については、以下の2つが挙げられます。
- SEOの評価で重複ページになる可能性
- 表示されない可能性
それぞれの注意点について解説していきます。
SEOの評価で重複ページになる可能性
重複ページとは、同じ内容の記事が複数サイトに掲載されている状態を指します。特に、文章が一致するため、検索エンジンによって重複ページと判断される可能性が高くなります。万が一、重複ページと認識されると、検索エンジンからペナルティを受けるケースがあります。
Googleは検索結果質の向上に向けて、不適切な運営をしているサイトを厳しくチェックしており、違反が確認された場合はペナルティの対象となります。その結果、検索順位が下がるなどの悪影響を受けてしまうので、あらかじめ注意が必要です。
関連記事:重複コンテンツとは?SEOにおける評価とコピペ率を確認する方法等を解説
表示されない可能性
自社ページが表示されない可能性があるので注意が必要です。
グーグルは、検索結果として表示される情報の品質をより良いものにするため、類似性が高いページを検索結果に複数表示しないようアルゴリズムを調整しています。この影響で、仮に自社が公開したページとしても、転載先となった他のウェブのほうがグーグルから高く評価されてしまうと、検索順位が低下してしまうリスクがあります。
SEOへの影響を含め、どのようなデメリットが生じるのかまで、慎重に検討することが大切です。
まとめ
 本記事は、転載に関して解説しました。引用は、補足・強化するのに対して、転載は他ページが大部分を占めるケースが多く、著作権の扱いも大きく異なります。他人が制作した著作物を中心とする際には、事前に正式な許可を得ることが必須です。また、文章などを転載には、原文を改変せずに記載するのはもちろん、引用箇所が明確に区別できるように工夫し、出典の明確な記載が必要です。万が一、無断だと、違法行為とみなされるケースがあります。トラブルに発展し、サイトの評価が下がるリスクもあります。自社メディアを運用しても、期待した効果が出ず、お困りの場合には、WEBマーケティングの「東京SEOメーカー」がご相談をお伺いします。お気軽にご連絡ください。
本記事は、転載に関して解説しました。引用は、補足・強化するのに対して、転載は他ページが大部分を占めるケースが多く、著作権の扱いも大きく異なります。他人が制作した著作物を中心とする際には、事前に正式な許可を得ることが必須です。また、文章などを転載には、原文を改変せずに記載するのはもちろん、引用箇所が明確に区別できるように工夫し、出典の明確な記載が必要です。万が一、無断だと、違法行為とみなされるケースがあります。トラブルに発展し、サイトの評価が下がるリスクもあります。自社メディアを運用しても、期待した効果が出ず、お困りの場合には、WEBマーケティングの「東京SEOメーカー」がご相談をお伺いします。お気軽にご連絡ください。