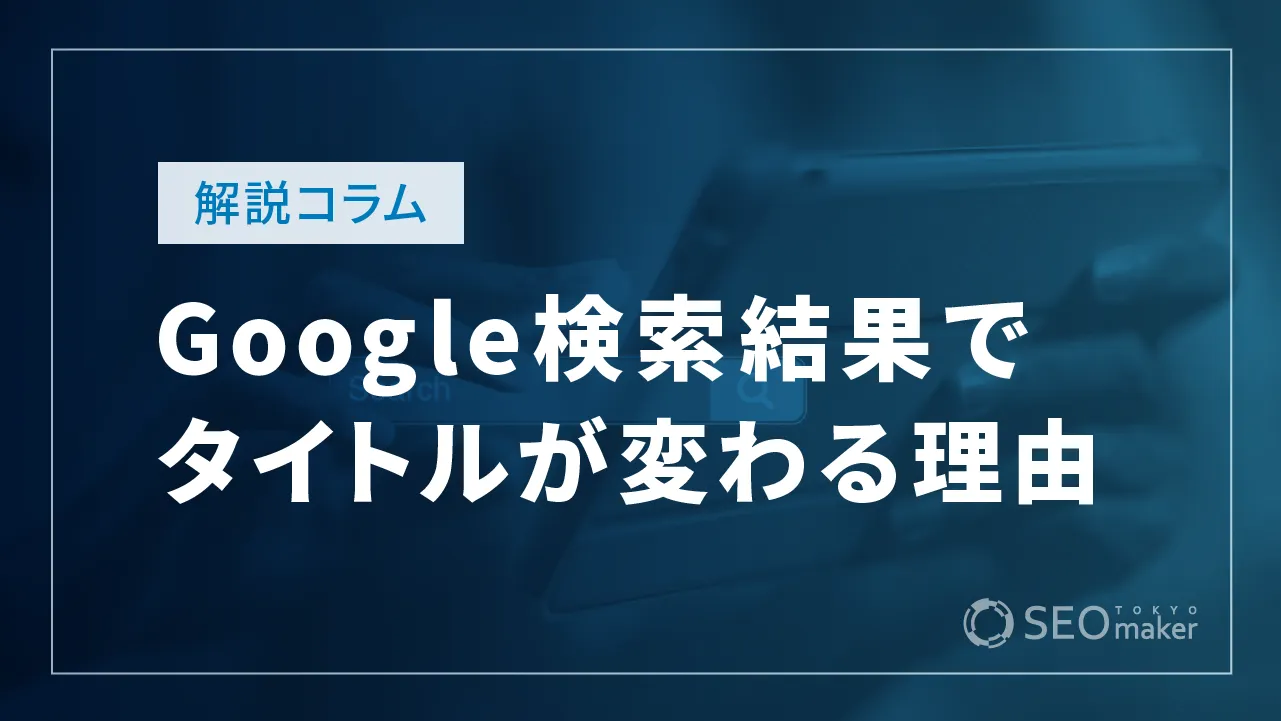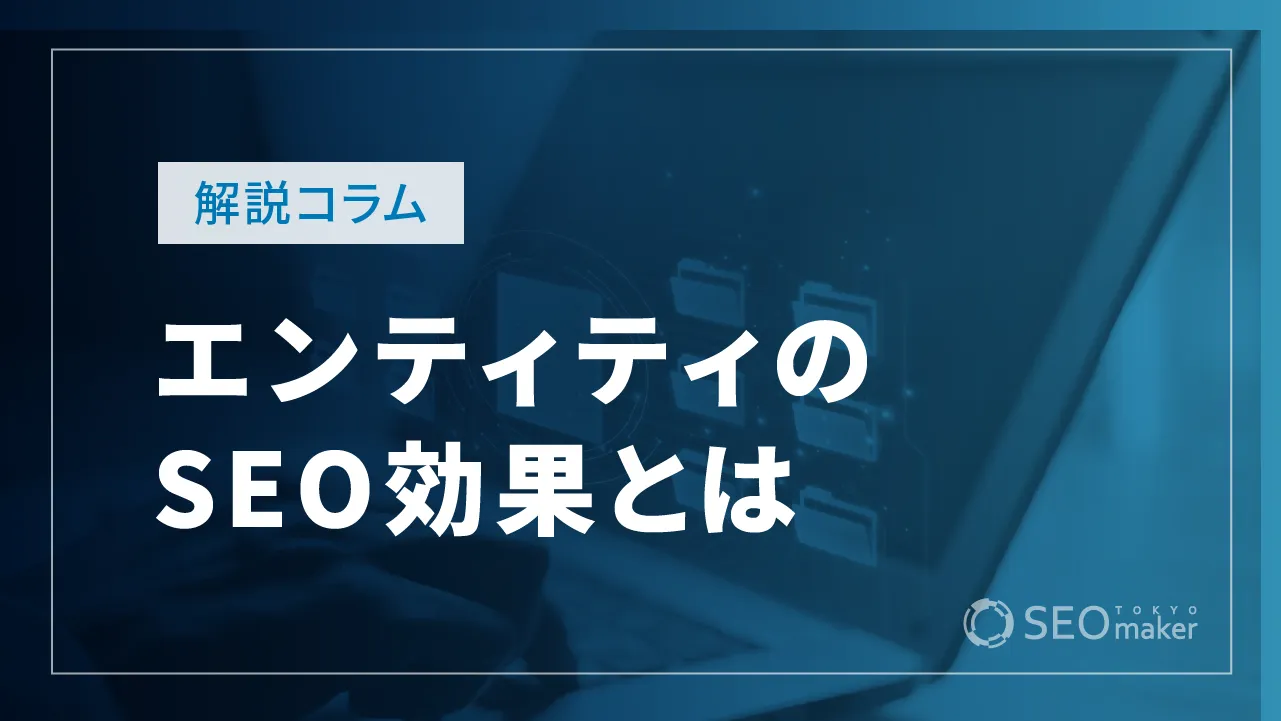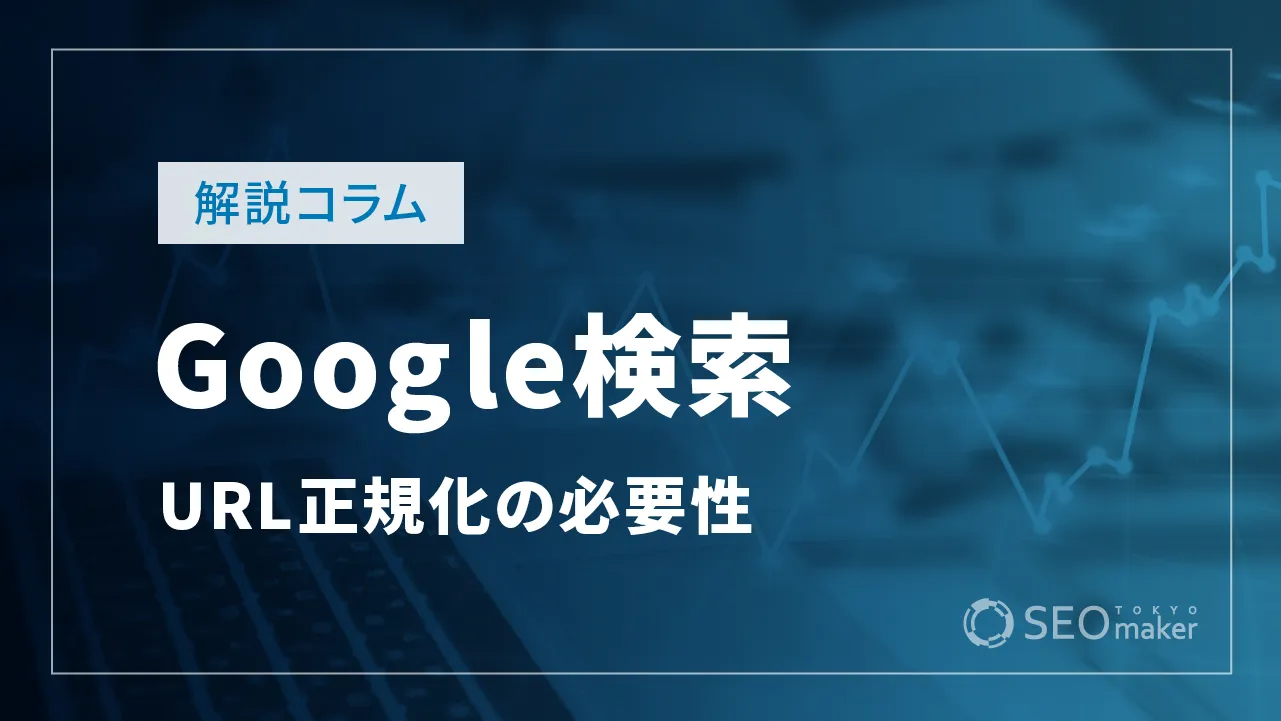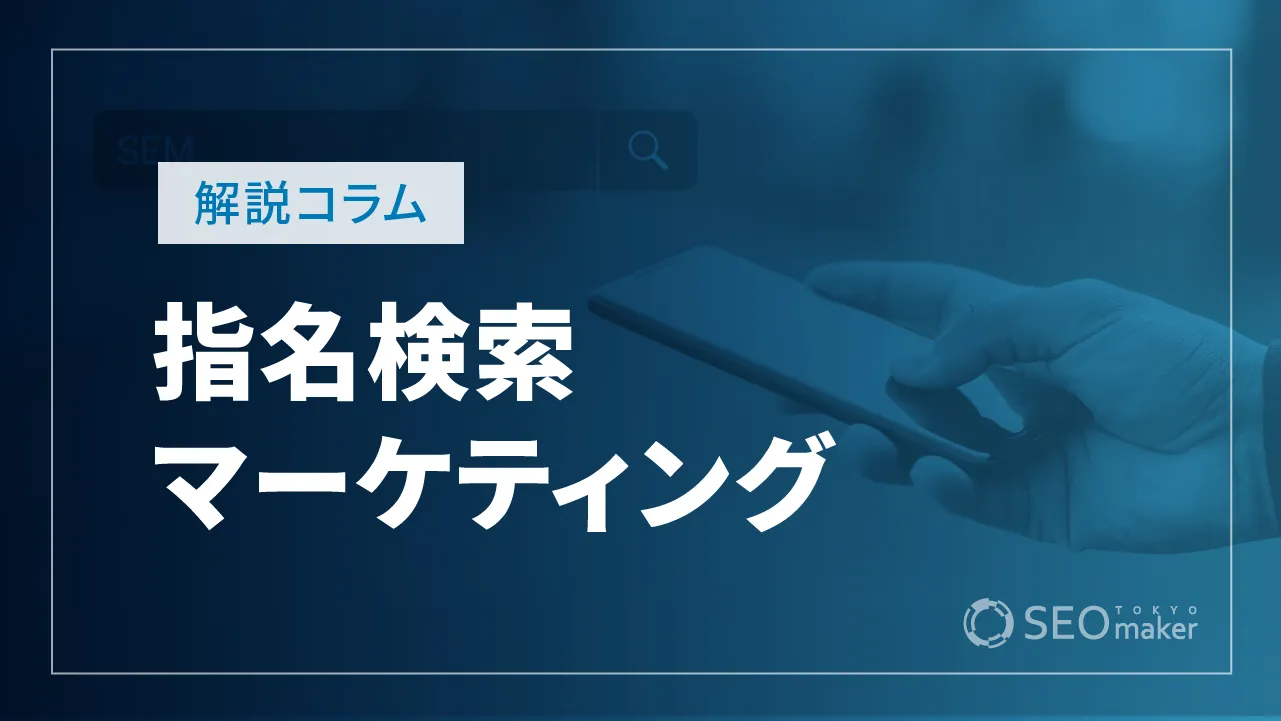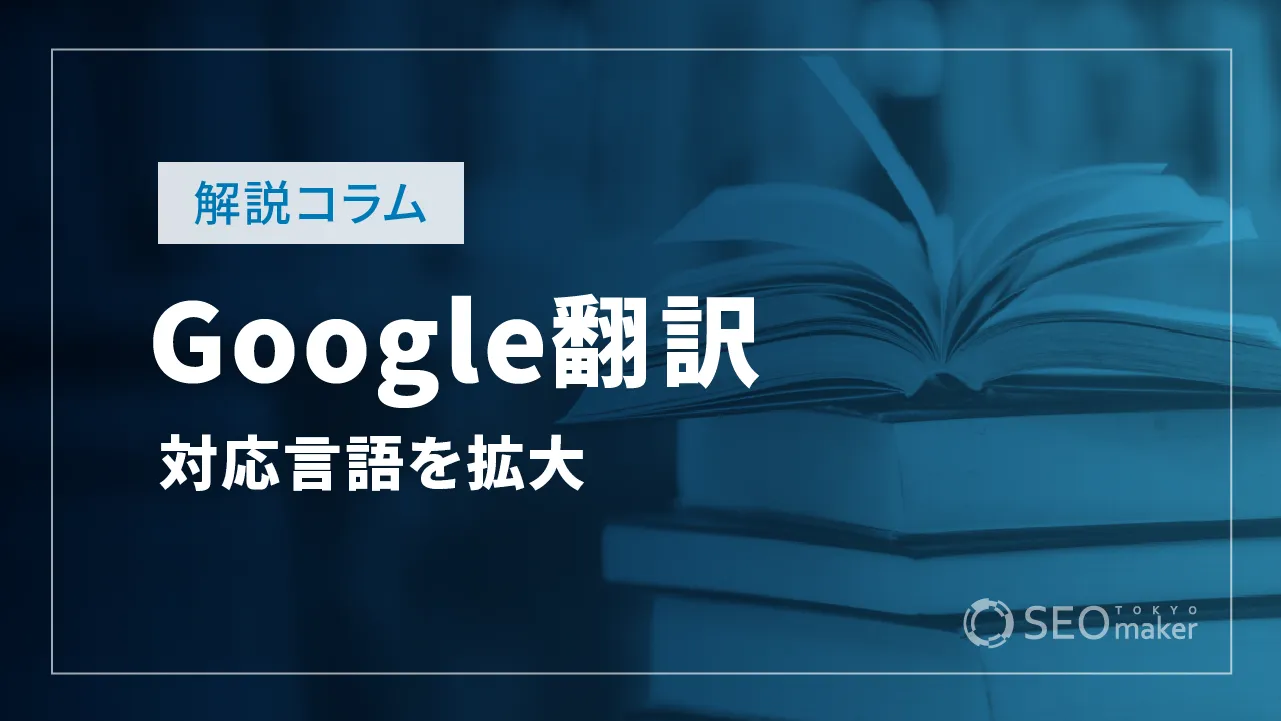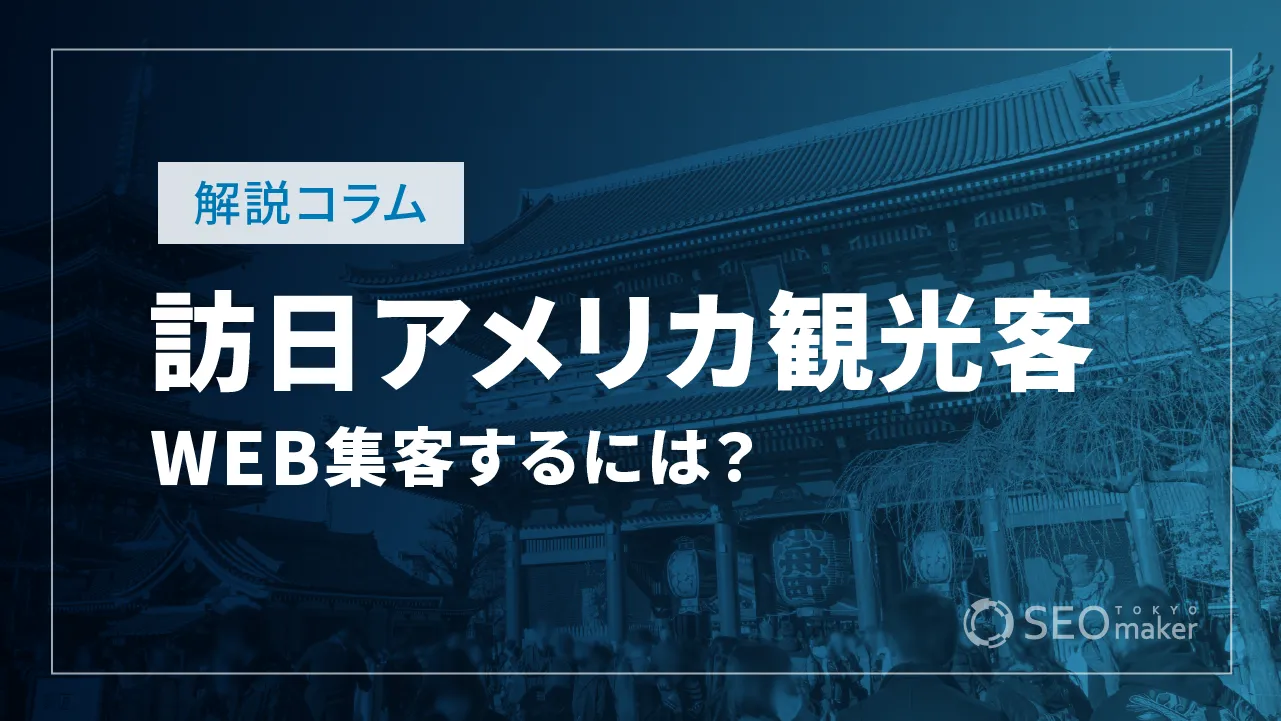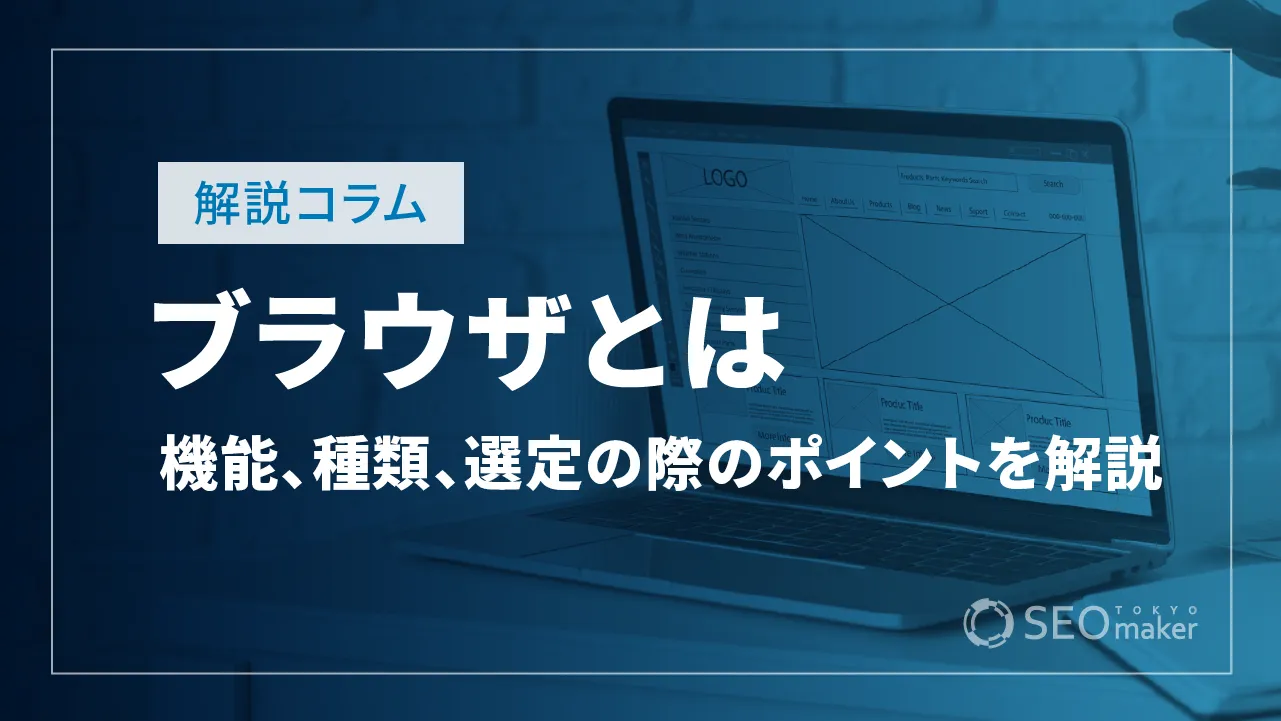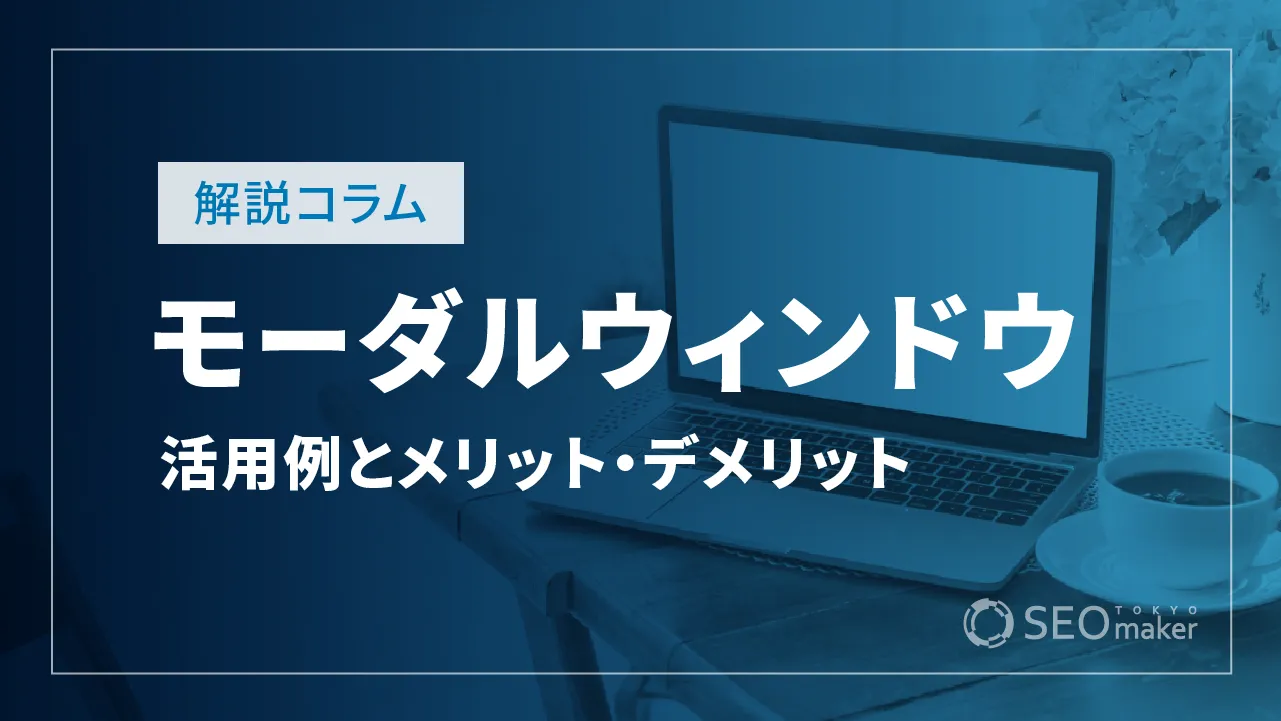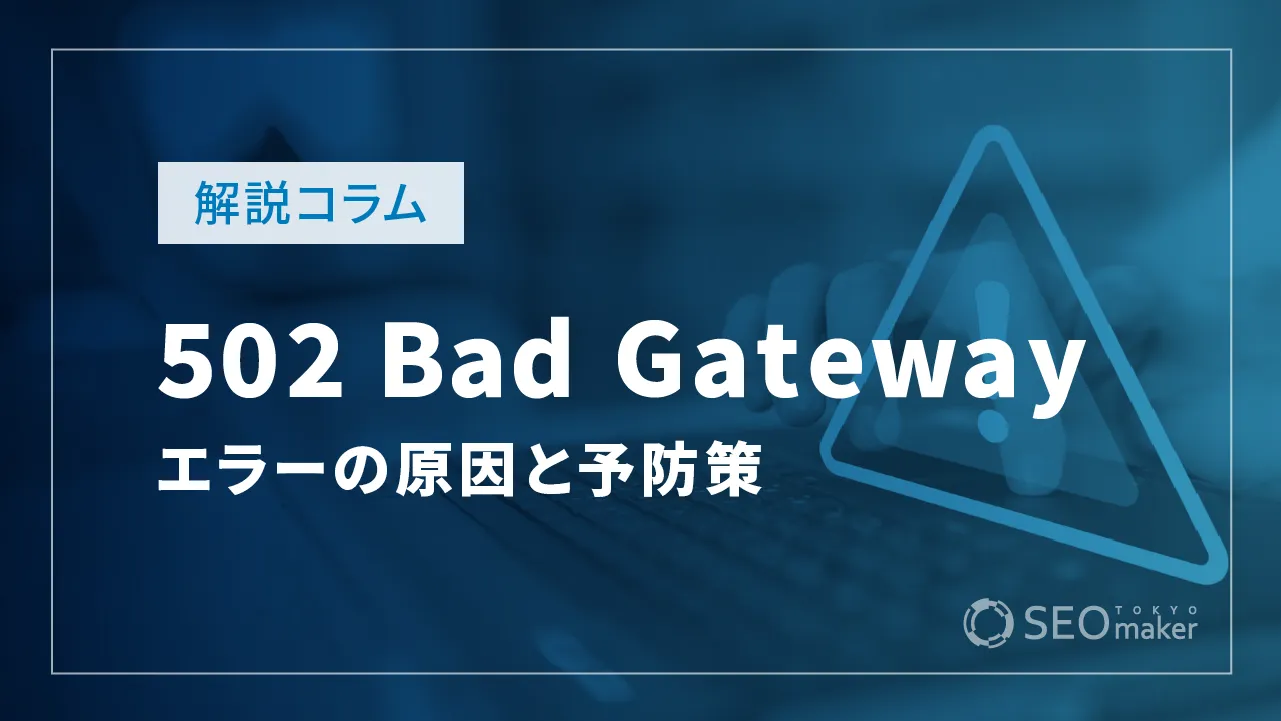記事のリライトとSEOの関係性は?正しいリライト手順を解説
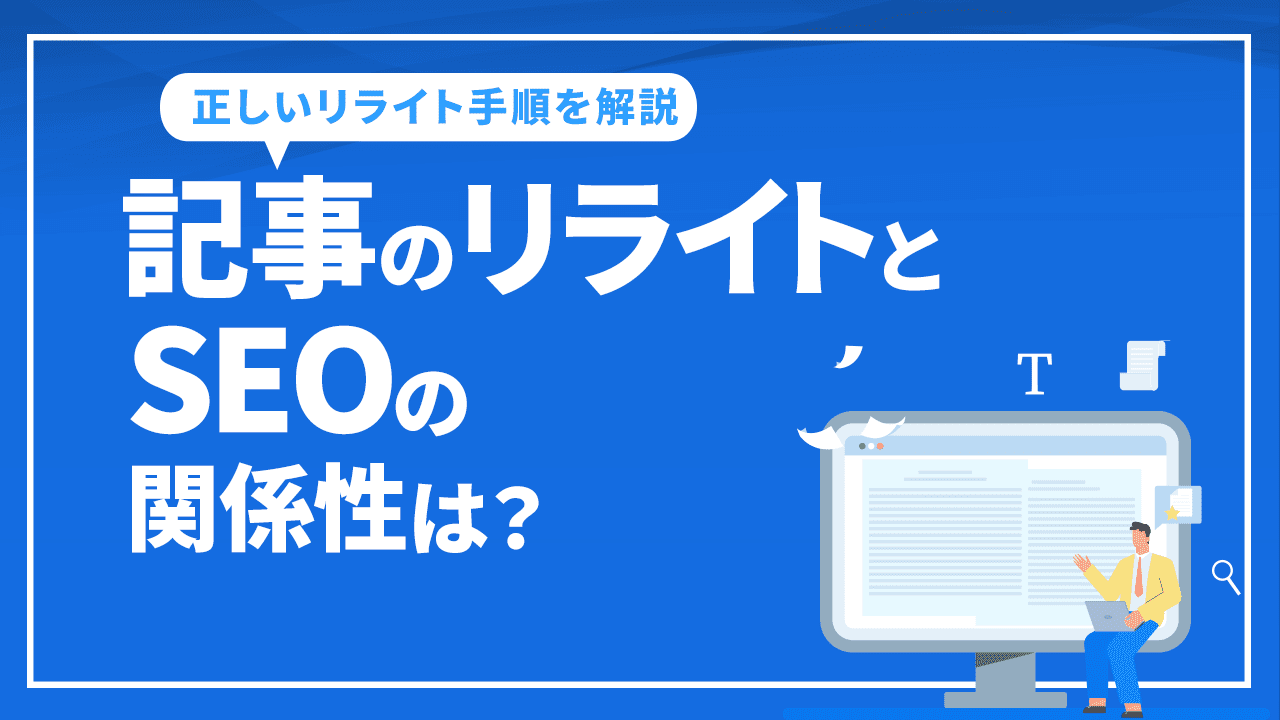
検索エンジンがページを上位表示する仕組みと、リライト時のいくつかの注意点を守ることで、リライトによる自社ページの検索順位の改善が可能です。SEOライティングには、新規記事のアップのほかに、既存記事のリライトがあります。
 そこで本記事ではリライトすべき記事の見つけ方や優先順位の付け方、リライトの流れについて解説します。本記事を最後までお読みいただくことで、SEO対策におけるリライトの重要性や正しいリライトの方法について理解できるようになりますので、是非とも最後までお読みください。
そこで本記事ではリライトすべき記事の見つけ方や優先順位の付け方、リライトの流れについて解説します。本記事を最後までお読みいただくことで、SEO対策におけるリライトの重要性や正しいリライトの方法について理解できるようになりますので、是非とも最後までお読みください。
目次
記事のリライトとは?
記事のリライトは多くの場合、ページのSEO効果を高める目的で実施されます。ページコンテンツの内容を最新のものに改めたり、状況に応じて内容を修正したりすることで、変化するユーザーニーズに対応したコンテンツを作ることができます。
検索エンジンは特定の検索キーワードに対し、優れた回答を行うページを優先的に上位表示させるアルゴリズムを採用しています。これはGoogleが掲げる10の事実「1. ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。」にも明記されており、ユーザーの利便性を第一に考えるコンテンツが検索上位に来ることがGoogleにとってもメリットになることが示唆されています。
つまり記事のリライトはただコンテンツを最新のものに更新するだけでなく、よりユーザーの利便性を考慮した内容に調整していくことがポイントとなります。記事のリライトを機に「このページの企画、構成はユーザーファーストなのか」「もっと分かりやすい文章展開はないのか」といった視点を持つことが大切なのです。
なぜ記事のリライトを行うべきなのか
記事のリライトは多くの場合「ページSEO効果を高めるため」に実施されますが、先述したように「検索順位を改善すること」だけが目的になってはいけません。
なぜならGoogleはユーザーの利便性を第一に考えてアルゴリズムアップロードを繰り返しており、都度変化するアルゴリズムをハックすることが目的になっていては、本来達成すべき「ユーザー獲得」の目的を見失ってしまう恐れがあるからです。
記事のリライトは「ユーザーの利便性を高めるため」に行われる必要があることを覚えておきましょう。
最新の情報に更新するため
記事のリライトはページコンテンツを最新の状態に保つために実施されるべきです。ページコンテンツの内容が最新の状態に更新されることで、「最新の情報を求めるユーザー」は検索行動を終えます。
企業、個人サイトはしばしばサイトの回遊性やCV率向上などを目的としていますが、ある情報へのアクセス性をあえて損なうことで発生する検索コストはGoogleの掲げるユーザーファーストの理念に反します。もしリライトを行うべき記事が「新鮮さ」を第一に提供する記事ならば、ユーザーが検索行動を終えることも1つのゴールとして想定する必要があります。
記事の品質を向上させるため
記事のリライトはページコンテンツを最新の状態に更新するとともに、ユーザーの利便性を向上させる施策である必要があります。
リライトを行うページによっては「コンテンツの更新」以外にもユーザーの利便性を向上させる要素が隠されているかもしれません。例えば「トピックの追加」はある検索キーワードに対するユーザーの理解を助ける可能性があります。
SEO効果を高めるため
記事のリライトでページコンテンツを最新の状態に更新したり、トピックの追加でユーザー理解を助けたりすることで、Googleの検索エンジンは「良質なコンテンツ」と判断する可能性があります。作成したページがユーザーにとって良質なコンテンツであれば、狙ったKWで上位表示される可能性が高くなります。
しかし記事コンテンツを用いたSEO(コンテンツSEO)の難しい点は、ページを作成するサイト運営者が考えるユーザーファーストなコンテンツと、検索エンジンが評価するユーザーファーストなコンテンツが必ずしも一致しない点です。SERPs(検索結果画面)に上位表示されるコンテンツはユーザーの利便性を第一に考えて表示されますが、実際にどのようなコンテンツが上位表示されるかはSERPsを確認するまで分かりません。したがって記事のリライトは「修正と確認の繰り返し」が必要とされます。
記事のリライトによってSEO効果が高まる理由
記事のリライトは以下2つの理由からSEO効果が高まるといえます。
- 狙うKWのユーザーニーズに記事内のトピックをチューニングするため
- Googleがページ品質を評価する「E-A-T」を高められるため
先述したような「新鮮さ」や「ユーザー理解を助けるトピックの追加」といったリライトでもページのSEO効果は高めることができますが、より戦略的にコンテンツSEOを実施したい方は理解しておいた方が良い部分になります。
狙うKWのユーザーニーズに記事内のトピックをチューニングするため
1回の記事のリライトで狙いたいKWの上位表示が実現することは少なく、多くの場合2回、3回とリライトを重ねていくことになります。
既にweb上に記事コンテンツをアップし、後述するGoogle Search Consoleなどで順位追跡を行っている方には経験があると思いますが、はじめに狙ったKWで上位表示を取れる確率はかなり低いといえます。
どちらかといえば、Google Search Consoleなどのツールで「自社ページが上位表示されているKW」を発見し、そのKWでさらに順位を上げるためにリライトを行う場合の方が多くなります。
つまりコンテンツSEOで自社ページを上位表示させる過程は主に以下の3つに分かれるのです。
- 狙ったKWで上位表示されるために最適なコンテンツを揃えた記事を作成
- はじめ想定したKWとは異なるKWで評価されているページを発見
- 既に評価を受けているKWに自社ページのコンテンツを調整する
記事のリライトによって成果を得たい方は、上位表示させたいKWに執着するのではなく、既に評価されているKWにも注目しましょう。
Googleがページ品質を評価する「E-E-A-T」を高められるため
記事のリライトはユーザーの利便性を向上させる目的で行われますが、それは同時にGoogleがページ品質を評価する際の指標として用いている「E-E-A-T」も高めることになります。だからこそ記事のリライトによってSEO効果は高まるのです。
Googleは検索品質評価ガイドラインの中で、ページ品質を評価する要素として「E-E-A-T」(Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性))に度々言及しています。
例えば医療用語や学術関連用語など、一般のユーザーの間で周知となっていない事柄に対し、Googleは「専門家」からの発信を求めています。それはある情報の信頼性が「専門家による発信によって担保される」と考えているからであり、情報の信頼性を支える上で重要な一次情報になるからです。
このE-E-A-Tの考え方は企業や個人の記事にも通用するもので、あるKWに関する情報を網羅的に記載したり、画像や動画を用いた説明で可読性を向上させたりすることが結果的にページSEO効果を高めることに繋がります。
リライトを行う記事の優先順位について
先述したように記事のリライトで成果を出すには、上位表示させたいKWにこだわるよりも、既に評価されているKWにコンテンツの内容を調整(チューニング)する方が簡単です。
既に評価されているということは、少ない施策の実施で検索順位を上げられる可能性が高いため、対策の優先順位が高いといえます。
検索順位が1ページ目もしくは2ページ目にランクインしている記事
後述するGoogle Search ConsoleなどのSEOツールで、特定KWで上位表示を獲得している自社ページを見つけることが可能です。
その際に「検索順位5位〜20位」前後にランクインしている記事があれば、その記事がリライト優先度の最も高い記事となります。
検索順位が1ページ目もしくは2ページ目にランクインしているということは、Googleが「ユーザーニーズにマッチするコンテンツ」と認識している可能性が高いことを意味します。
つまり少ない工数で検索順位の上昇が狙えるため、対策の優先順位が高くなるのです。
「トピック追加、本文の加筆」で順位上昇が見込める記事
トピックの追加や本文の加筆で順位上昇が見込める記事は、検索2ページ目〜3ページ目(11位〜30位)に多い記事です。これらの記事は特定KWのユーザーニーズをある程度満たしているものの、不足している情報などがある場合によく認められます。
検索2ページ目〜3ページ目にランキングしている自社ページを見つけた場合は、検索1ページ目に表示されているコンテンツとの差分がないかチェックしましょう。
差分をチェックする際のポイントは「見出し」と「本文のボリューム」です。不足しているトピックがないか、また検索1ページ目にランクインしている記事に比べて説明が不足していないか、といった視点が必要になります。
CTRの高い記事
リライトによる検索順位の上昇を図る場合、CTRの高い記事のリライトは先述した2つに比べて優先順位が高くありません。
なぜならCTRの高い記事はその指標単体ではリライトによって検索順位が上昇するかどうか見込みが立たない場合も多く、特に検索3ページ目以降にランクインしている記事はGoogleが認識している特定KWのユーザーニーズから外れている可能性が高くなるからです。
しかしこのような「CTRは高いが検索順位が低い記事」は「検索順位が低いにもかかわらずクリック率が高い」という特徴を持っています。
こうした現象はGoogleが特定KWに対して紐付けているユーザーニーズと、実際の検索ユーザーのニーズがズレている場合にも起こる可能性があり、リライトの仕方によっては検索順位の上昇が見込めます。
もし「CTRは高いが検索順位が低い記事」を見つけた場合は「現在評価されているKWに関連したKWで上位表示が狙えないか」を考えることが大切です。コンテンツ内容の修正と継続的なモニタリングによって上位表示を獲得できるチャンスがあります。
リライトを行う記事の見つけ方
記事のリライト基準は会社や個人によって様々ですが、リライトによって検索順位を向上させたい意図があるならば、基本的に確認すべきものは「現状の検索順位」です。
現状の検索順位が上位であればあるほど、少ない工数で成果を期待できます。現状の検索順位は順位追跡ツールやGoogle Search Consoleを使うことで効率的に把握可能です。
順位追跡ツールを活用する
順位追跡ツールとは文字通り「ページの検索順位を追跡するツール」を指します。代表的なツールにはSEOツールラボが提供する「GRC」などがあり、追跡したいページURLを入力することで順位を継続的にモニタリングしてくれます。
また多くの順位追跡ツールには「特定KWの検索順位を一覧表示する機能」が搭載されており、自社ページで検索上位にランクインしている記事を効率的に把握することが可能です。
Google Search Consoleを活用する
Google Search Consoleの「検索パフォーマンス」から、自社ページで検索上位を獲得している記事を見つけることができます。
デフォルトではサイト全体の検索パフォーマンスが表示されているため、特定のページを選択し、その後「クエリ」(検索キーワード)を選択することで、特定のページがどのようなキーワードで評価されているのかを把握することが可能となります。
SEO効果を上げるリライトのポイント
SEOの効果を最大限に上げるためにはどのような点に気を付けるべきなのか、多くのメディア運営者が気になっているはずです。Googleから高い評価を受けるためには以下のポイントを抑える必要があります。
- E-E-A-Tを意識する
- 独自性、網羅性を高める
- 内部リンクを設置する
E-E-A-Tを意識する
E-E-A-TとはGoogleが提唱しているWebサイトの評価基準で、以下の3つの項目の頭文字を取って作られた用語です。これらの項目を満たしたコンテンツはGoogleからの評価が高くなる傾向にあります。
- Experience:経験
- Expertise:専門性
- Authoritativeness:権威性
- Trustworthiness:信頼性
経験とは執筆者・作成者の実体験やトピックについての経験値のことです。経験が伴った記事は、独自性がありユーザーにとっても有益な情報を伝えると評価されます。
専門性は扱っているトピックに関する専門的な情報を提供できているかどうかという指標です。記事の内容を充実させたり、そのジャンルに関する専門的な知見を持っている人に執筆してもらったりすることで評価を上げることができます。
権威性は読者から「このメディアに掲載されている情報は正しい」と信頼されているメディアかどうかという指標です。
外部サイトからの被リンクを得ることや、執筆者の情報を開示することで権威性を高められます。また、長期間メディアを運営しているという実績も権威性に関係します。
最後に信頼性については読者から記事の内容が信じられているかどうかです。権威性と少し似ている指標です。
例えば匿名の個人が発信しているブログの情報と公的機関が発表している情報では信頼度が変わるように、ユーザーから信頼されるメディアになるよう執筆者の情報やメディアの運営者情報を充実させることを意識する必要があります。
E-E-A-Tについて詳しく知りたい方はGoogleが発表している「検索品質評価ガイドライン」をチェックしてください。
独自性、網羅性を高める
Googleからの評価を上げるためには独自性と網羅性を高めることが重要です。
Googleから競合のコンテンツのコピーだと判断されるとペナルティの対象となる可能性があります。競合コンテンツの研究はリライトをするうえで重要な作業ですが、あまりにも似ている内容にならないよう注意する必要があります。
そのうえで、自分のメディアの独自性を出す工夫をすることが大切です。競合コンテンツにはない切り口で情報をまとめたり、常に最新の情報を掲載できるよう更新の頻度を上げたりさまざまな施策を試してみてください。
また、記事の網羅性を高めることも大事なポイントです。競合のコンテンツを調査し、自分のメディアの記事にない内容があればリライトをする際に盛り込むことをおすすめします。
内部リンクを設置する
リライトをする際には関連する記事への内部リンクを設置することをおすすめします。ユーザーがサイト内を回遊しやすくなったり、Googleのクローラーがスムーズにサイトを巡回できるようになったりすることで、評価が上がる可能性があります。
記事を新規作成したときにすでに内部リンクを設置しているケースもあるかもしれませんが、リライトをするときにはメディア内での記事の関連性が変化していることもあります。リライトをするタイミングで改めて内部リンクを見直してください。
記事のリライトの流れ
記事のリライトは多くの場合以下の流れに沿って実施されます。先述した「リライトを行う記事の優先順位について」の内容を参考にしながら、適宜不要な工程は省いて作業を行って下さい。
- リライト記事の選定(チューニングするKWの決定)
- ニーズの調査
- 競合ページの調査
- 方向性を決定し実際にリライト
- タイトル、見出しの作成
- 本文執筆
各作業について説明していきます。
リライト記事の選定(チューニングするKWの決定)
まずは順位追跡ツールやGoogle Search Consoleなどのツールを用いて、リライトすべき記事を見つけましょう。多くの場合リライト対象記事は2つ以上あるため、優先順位をつけて対策していきます。ここで重要なのはリライトする記事を選定した後、チューニングするKWも決めることです。
評価されているKWの中には、例えばミドルキーワードやビックキーワードとよばれる検索ボリュームの大きいキーワードも含まれている場合があります。
その場合は検索1位が狙えるスモールキーワード(検索ボリュームの小さいキーワード)にチューニングするよりも、検索10位以内が狙えるミドルキーワードやビックキーワードにコンテンツ内容をチューニングした方が施策のインパクトが大きくなります。
ニーズの調査
リライト記事とチューニングするKWが決まった後は、チューニングするKWのニーズ調査を行います。まずは実際のSERPsを確認し、どのようなユーザーニーズが存在するのかを端的に把握しましょう。
特に見定めるポイントは、チューニングするKWにおいて「主題となるトピックは何か」という点です。主題とは「ユーザーが最も知りたいこと」と解釈できます。
GoogleはほとんどのKWにおいて、様々なユーザーニーズを反映させたSERPsを作成しますが、どのKWにも核となるトピックが存在します。上位表示を狙うKWでどのようなトピックが核(主題)となるのかを調べましょう。
競合ページの調査
狙うKWで核となるトピックを見つけた後は、競合ページの見出し構造や、ページ内コンテンツの調査を行います。ラッコキーワードなどのSEOツールで、狙うKWの上位表示ページの見出し構造を可視化します。
上位表示されているページとリライト対象ページの差分を「見出しレベル」でチェックします。この時に「上位表示ページにはあるが自社ページにはないトピック」があれば追加を検討しましょう。
また上位表示されているページを実際にスクロールして見ることも重要です。実際にページをスクロールすることで、ページ内に盛り込まれた画像や動画といったテキスト以外のコンテンツを確認することができます。
ユーザーの利便性を向上させるコンテンツや、ユーザー理解を助けるコンテンツが盛り込まれていた場合は、自社ページのリライトにも反映させましょう。
方向性を決定し実際にリライト
記事の選定、ユーザーニーズや競合コンテンツの調査が終わったら、リライトの方向性を決めます。これまでに分析した内容を踏まえ、構成を作り直して本文を全体的に書き直すのか、本文の一部を修正したり加筆したりするのか、タイトルやディスクリプションのみ変更するのかなどを判断してください。
リライトの方向性が決まったら実際にリライトを進めます。
タイトル、見出しの作成
競合ページの調査の結果、追加すべきタイトルや、トピック、見出しが分かってきます。ここで注意したいのは「バイアスをかけないこと」です。あるKWに対して抱いている先入観が本来追加すべきトピックを不要なものとして判断する可能性があります。
検索順位の改善が目的で記事のリライトを行うのなら、自身の考えとユーザーニーズは混同させないように注意しましょう。
本文執筆
タイトル、見出しの修正を行った後は中身の文章を書いていきます。ユーザーの可読性を向上させる方法としてPREP法とよばれる書き方があります。
これは「Point(結論)」「Reason(理由)」「Example(例)」「Point(結論)」の順番で書かれる文章作成術で、結論を先に説明することでユーザー理解を促進する目的があります。
また複雑な仕組みや進行の流れ、対象物の関係性などを説明する場合は「図」といった視覚的なデザインも適宜作成することが重要です。
ライターにはユーザーが読みやすい文章とは何か、理解を促進するためにできる工夫はないか、といった視点で書くことが求められます。
効果の検証
リライトが完了した後は効果を検証することも重要です。Google Search Consoleを使用してリライト後の検索順位やCTRの動向を確認します。
リライトの効果が出るまでの時間は記事によって異なりますが、まずは1ヶ月を目途に効果をチェックすることがおすすめです。リライト前後の1ヶ月のデータを比較してみてください。成果が表れていなかったりリライト前より順位が下がってしまったりした場合は、改めてリライトをする必要があります。
検索ボリュームの大きいキーワードを狙う記事や運営しているメディア内で重要な位置を占める記事などは、優先的にリライトを続けていってください。
リライトに関する注意点
リライトの流れやポイントはここまで紹介したとおりですが、その他にも事前に知っておくべき注意点があります。リライトで成果を上げたり、効率的に作業を進めたりするためには以下の項目を意識することが重要です。
- 検索順位が上位の記事はリライトしない
- リライトにかける時間は余裕をもって確保する
- 新規記事はリライトを前提に作成する
検索順位が上位の記事はリライトしない
すでにGoogleで上位を獲得している記事はリライトしないようにしてください。1位になった記事にリライトの必要性がないことはもちろんですが、2位~9位の記事についても安易にリライトをしないほうが得策です。
2位~9位を獲得している場合、記事の内容以外に問題がある可能性があります。独自性や網羅性の高い文章になっていても、表示速度が遅かったり、被リンクが少なかったり、E-A-Tに関する情報が足りなかったりする場合があるからです。
そのため2位~9位の記事については、リライトをする前にほかの対応策を取って順位を上げることができないか試してください。
リライトにかける時間は余裕をもって確保する
一般的にリライトは新規記事の作成よりも難易度が高く、リライトにかける時間は余裕をもって確保する必要があります。
ユーザーニーズを調査したり、競合コンテンツの研究をしたりして記事を作成する点は新規記事でもリライトでも同じです。ただし、新規記事の場合は検索順位が上がるかどうかは未知数の部分があります。
質の高い記事を公開したとしても、そのキーワードで自分の運営するWEBメディアがどこまで勝負できるのかは公開してみないと分かりません。
一方、リライトの場合は記事を公開してから現在にいたるまでのアクセスデータも踏まえ、確実に順位が上がるであろうという内容に仕上げる必要があります。新しく記事を作成するよりもリライトのほうがむずかしいので、時間に余裕をもってスケジュールを組むようにしてください。
新規記事はリライトを前提に作成する
新規記事を作成する段階から公開後にリライトすることを想定しておいてください。
たとえ経験豊富でスキルの高い人でも、いきなり最初から100点の記事を作ることはむずかしく、どれだけ質の良い記事を出しても公開後にリライトの必要性に気付くケースもあります。
そのため、リライトすることを前提に60点~70点程度の新記事を作成することが効果的です。一度60点~70点の仕上がりの記事を出してGoogleの評価を確認し、そのうえで改善点を洗い出しリライトをしてみてください。
リライトによって検索順位が上がれば追記したり変更を加えたりした部分が評価されたことが分かるので、ほかの記事をリライトする際に同じ視点を活かすことができます。
まとめ
 本記事では、SEO対策におけるリライトの重要性や記事リライトの流れについて解説しました。記事を最新の状態に保つことはSEO対策では重要となります。また、記事のリライトによって検索順位の上昇を図るには、継続的な効果検証が必要です。仮説を立ててリライトを行い、狙ったKWで順位が改善されるかモニタリングしましょう。弊社ではSEOの戦略策定から実行まで幅広くご支援をおこなっています。もしも自社でSEO対策を行うリソースがない場合には、お気軽にお問い合わせください。
本記事では、SEO対策におけるリライトの重要性や記事リライトの流れについて解説しました。記事を最新の状態に保つことはSEO対策では重要となります。また、記事のリライトによって検索順位の上昇を図るには、継続的な効果検証が必要です。仮説を立ててリライトを行い、狙ったKWで順位が改善されるかモニタリングしましょう。弊社ではSEOの戦略策定から実行まで幅広くご支援をおこなっています。もしも自社でSEO対策を行うリソースがない場合には、お気軽にお問い合わせください。