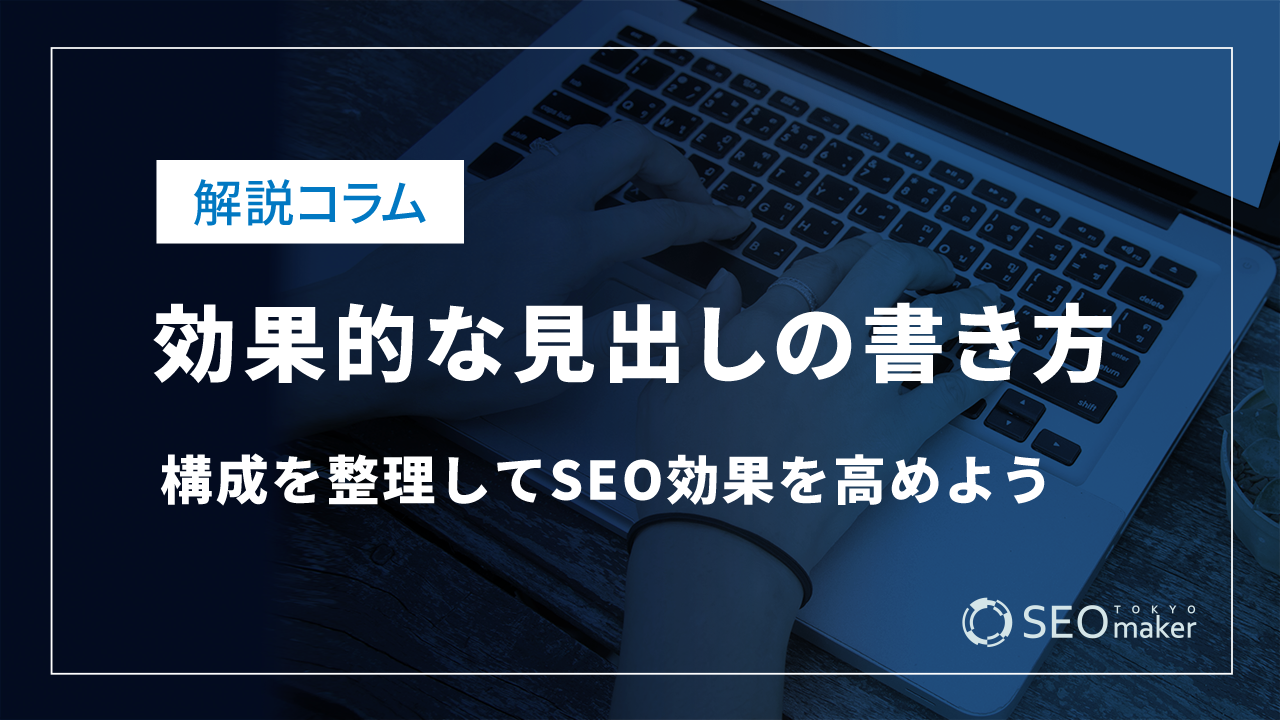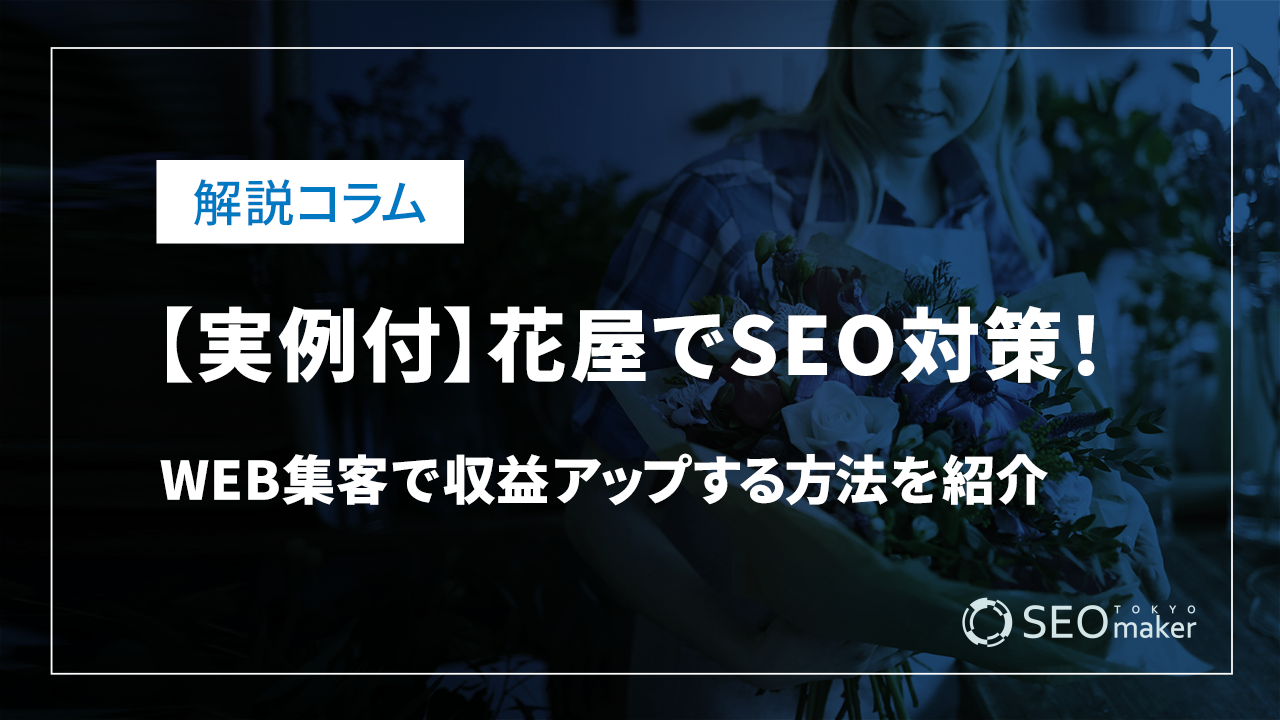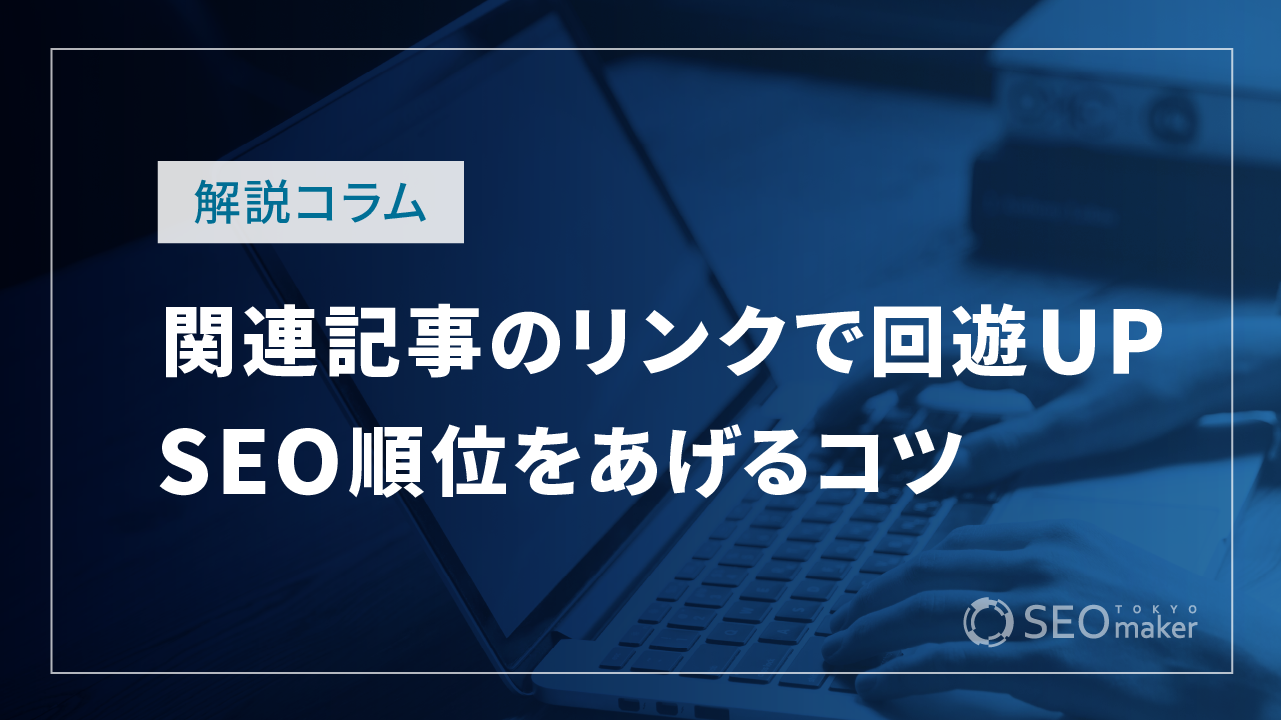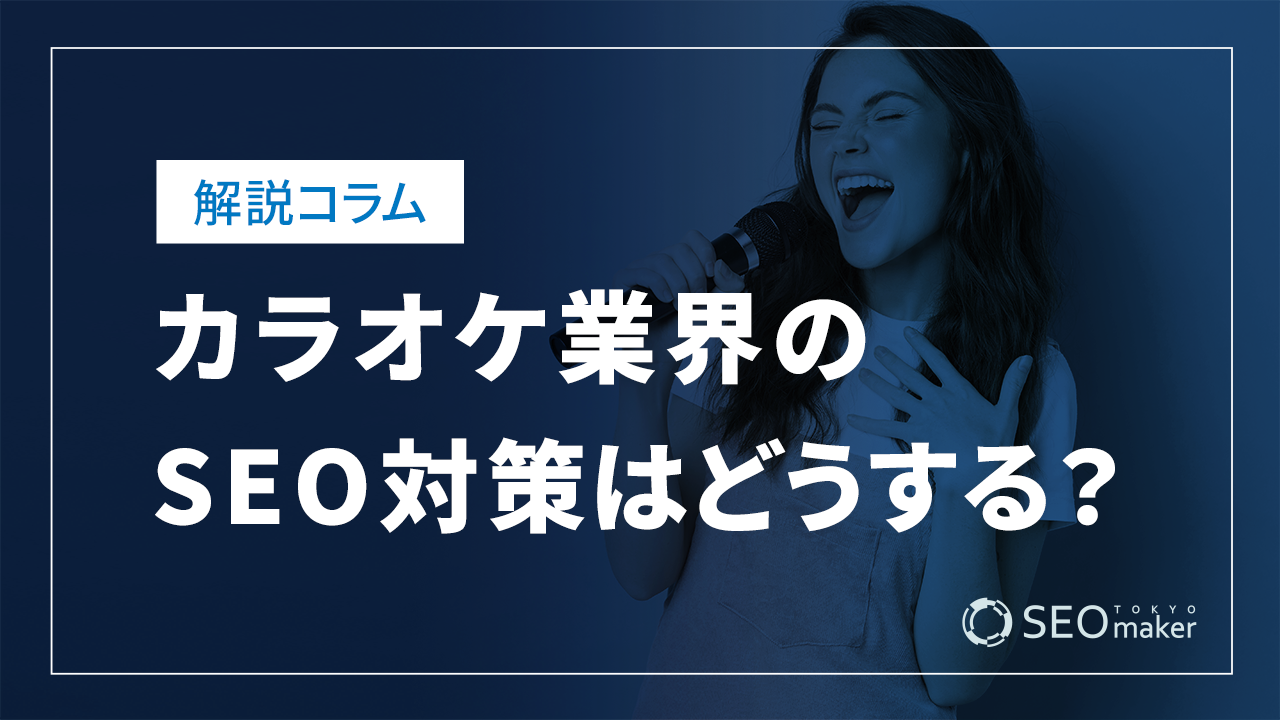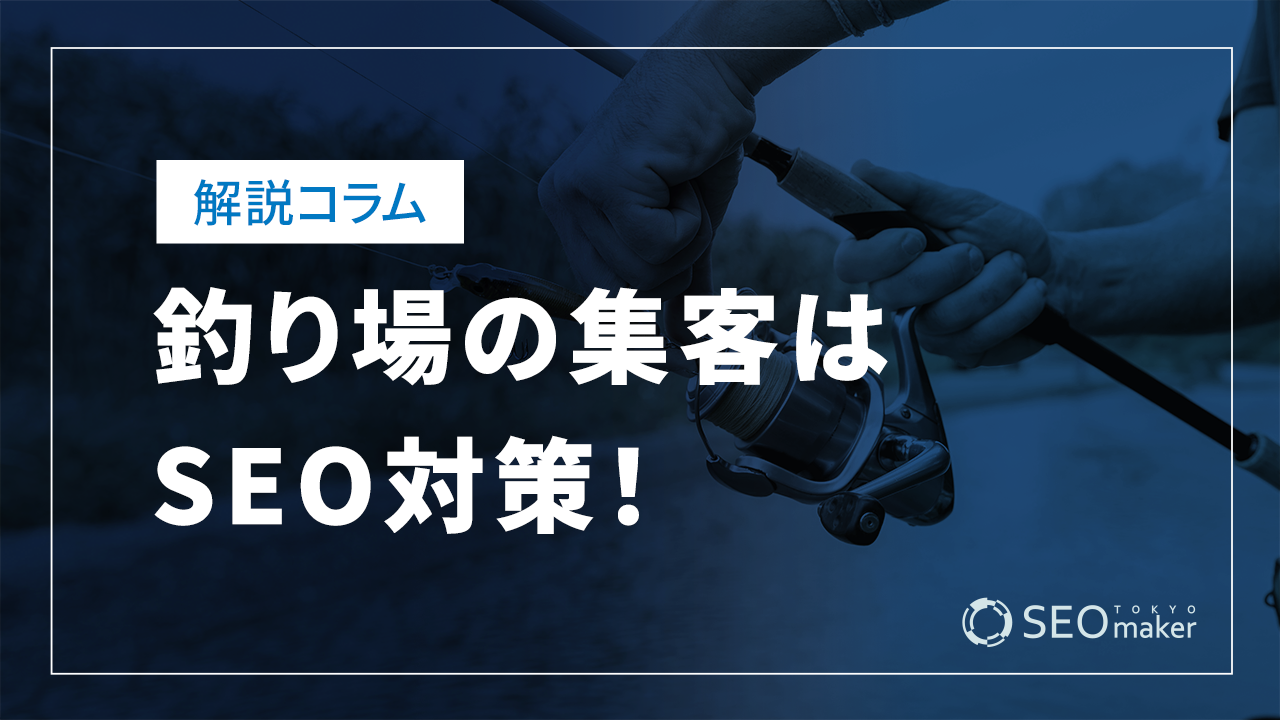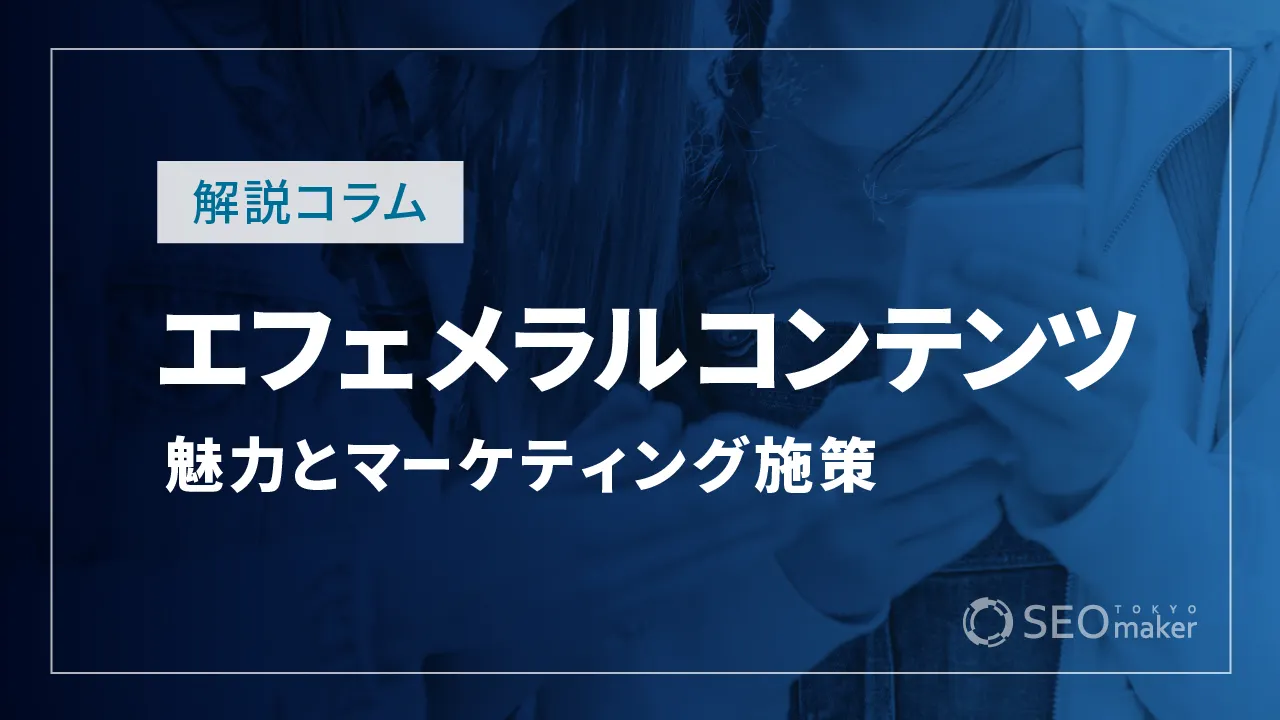オウンドメディアのSEO対策とは?基本・内部のSEO対策を併せて紹介
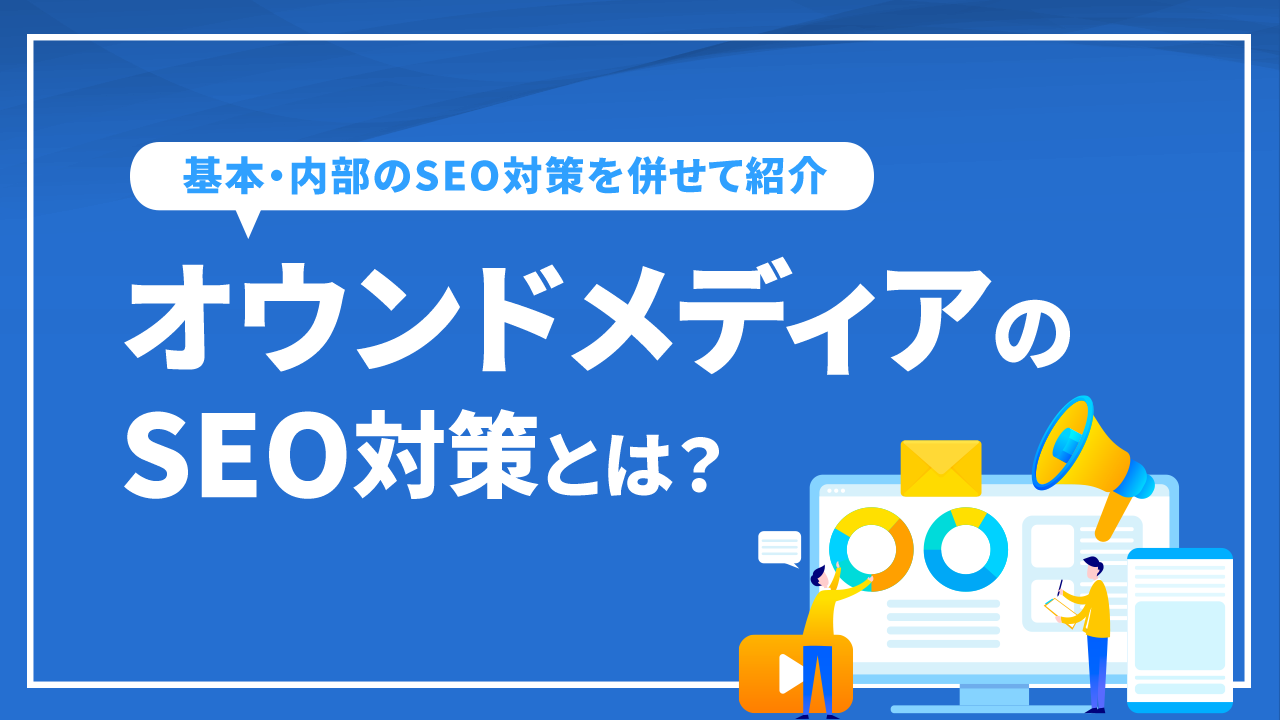 近年オウンドメディアを運用する企業が増えてきました。しかし、オウンドメディア立ち上げ初期は成果が出にくく、発信したいコンテンツをただ掲載するだけでいいというわけではありません。
近年オウンドメディアを運用する企業が増えてきました。しかし、オウンドメディア立ち上げ初期は成果が出にくく、発信したいコンテンツをただ掲載するだけでいいというわけではありません。
検索ボリュームの多いキーワードを入れてコンテンツを作成しても、ユーザーファーストのものでなかったり、伝えたい内容ばかり書いていては、ユーザーが定着しないメディアになりかねません。
 この記事では、オウンドメディアのSEO対策や失敗例などを解説しています。オウンドメディアのSEO対策について知りたい方はぜひご覧ください。
この記事では、オウンドメディアのSEO対策や失敗例などを解説しています。オウンドメディアのSEO対策について知りたい方はぜひご覧ください。
オウンドメディアとは
オウンドメディアとは、企業が所有するメディアのことです。一般的に、企業のWebサイトなどのことを指す場合が大半ですが、会社のパンフレットや広報誌などの紙媒体のものもオウンドメディアに含まれます。
冒頭でお伝えした通り、オウンドメディア立ち上げ初期は成果が出にくいものです。オウンドメディアで成果を出したいのであれば、SEOを意識したオウンドメディア運営を実施するのが近道です。
SEOとは
SEOとは、Search Engine Optimizationのイニシャルをとった言葉で、日本語では検索エンジン最適化といいます。
Googleなどの検索エンジンで、Webサイトが上位表示しやすいように対策することを、SEO対策と言います。SEOの表示のランキングのルールは、Googleのアルゴリズムによって決まっており、SEO対策とは、アルゴリズムから高評価を得るためのものともいえます。
しかし、Googleのアルゴリズムは200以上とも言われ、頻繁に更新されるため、コンテンツの最適化と見直しが必要です。
SEO対策は、継続的に行い、Googleから発表されるアルゴリズムの更新にもアンテナを立て、戦略を立てて実行することが重要です。
オウンドメディアのSEOが注目されている理由
ここでは、オウンドメディアのSEOが注目されている理由を解説します。
会社の製品・サービスの認知度の向上につながるから
オウンドメディアのSEOが注目されている理由は、会社の製品・サービスの認知度の向上につながるからです。
例えば、オウンドメディアにSEO対策して、上位表示ができれば、検索エンジンからの自然流入が見込めるWebサイトになります。
つまり、検索エンジンを使用するユーザーの目に増える機会が増えるので、会社の製品やサービスの認知度が向上します。認知度が向上すれば、会社の製品やサービスに興味を持つユーザーが増え、製品の購入や申し込みをしてくれる人も増えるでしょう。
このように、会社の製品やサービスの認知度の向上に繋がるので、オウンドメディアのSEOが注目されています。
広告費を抑えられるから
オウンドメディアのSEOが注目されている理由は、広告費を抑えられるからです。
例えば、オウンドメディアへ検索エンジンからの流入数を増やすため、Googleにリスティング広告などを出稿すると、当然ですが広告費が発生します。しかし、SEO対策を行い、上位表示されるようになれば、検索エンジンよりユーザーの自然流入も見込め、広告費も必要ありません。
このように、広告費を抑えられるので、オウンドメディアのSEOが注目されています。
会社の資産になるから
オウンドメディアのSEOが注目されている理由は、会社の資産になるからです。
例えば、オウンドメディアにSEO対策して、上位表示されるようなサイトにすると、検索エンジンから自然流入が見込めるWebサイトになります。このWebサイトを継続して管理すれば、集客力のあるオウンドメディアを保有し続けられ、会社の資産になります。
このように、会社の資産になるので、オウンドメディアSEOが注目されています。
オウンドメディアの基本のSEO対策
ここまでは、オウンドメディアのSEO対策が注目される理由などを解説してきましたが、ここでは、オウンドメディアの基本的なSEO対策を解説します。
ユーザー目線の質の高いコンテンツを作成する
SEO対策では、キーワード選定や検索ボリュームなどが重要視されることが多いですが、まずはユーザー目線の質の高いコンテンツを作成することに重きをおきましょう。
さまざまなSEO対策がありますが、ユーザーのニーズを調査し、質の高いコンテンツを作ることがオウンドメディア運営の基本的な活動となります。つまり、ユーザーがそのメディアにアクセスした時に、ユーザーのニーズを満たせるようなコンテンツを作成する必要があります。
また、PV数が多くても、オウンドメディアの目標としている成果を得られなければ意味がありません。まずは、ユーザーニーズをどのように満たすかを考えましょう。
リライトを継続して行い上位表示を狙う
オウンドメディアを立ち上げたばかりの企業がしがちなことは、作成した記事を公開後放置してしまうことです。
立ち上げたばかりのメディアに記事を公開して、上位表示されることは滅多にありません。そのため、記事を公開したら検索順位を確認しながら、適宜、記事のリライトを行いましょう。
検索順位を観察する
前述したとおり、オウンドメディアにとって検索順位は非常に重要なものです。しかし、検索順位はアルゴリズムのアップデート等が行われると、急激に変化します。
検索順位を観察して、順位が上がらない場合は、上がらない要因を考えましょう。
オウンドメディアの運用目的に合ったキーワードを選ぶ
キーワードは、オウンドメディアの目的から選定しましょう。
キーワードの検索数
- BtoB オウンドメディア(検索ボリューム:320)
- オウンドメディア SEO(検索ボリューム:210)
例えば、上記のキーワードでは「BtoB オウンドメディア」のほうが、検索ボリュームが多いので「BtoB オウンドメディア」の記事を作成をしがちです。
しかし、この2つのキーワードは全く異なる検索意図を持ったユーザーが検索しています。
具体的に説明すると、前者の「BtoB オウンドメディア」を検索したユーザーは、BtoBのビジネスを行っている、または行いたい企業のキーワード。後者の「オウンドメディア SEO」はオウンドメディアを運営しているユーザーがオウンドメディアのSEOについて知りたい場合に検索するキーワード。
選定するキーワードによって、その記事が刺さるユーザーが異なります。オウンドメディアの運用の目的を考えながらキーワードを選びましょう。
オウンドメディアのSEOの内部対策
ここからはオウンドメディアの内部対策について解説していきます。
ユーザーとクローラーを意識したWebサイト構造にする
オウンドメディアのSEOの内部施策を行う際は、ユーザーとクローラーを意識したWebサイト構造にすることが求められます。Googleはユーザー目線の質の高い記事が上位表示されるシステムになっています。
タイトルや見出しに、キーワードを使用したり、hタグを正しく使われているWebサイトの方が、良い評価をもらえるようになっています。
近年Googleのアルゴリズムはアップデートを続けており、ユーザー目線の質の高い記事を作成しないと上位表示されるのは難しくなっています。そのため、ユーザーとクローラーを意識したWebサイト構造になるよう、SEO内部対策を実施しましょう。
モバイル端末からの見え方を意識する
現在、Webサイトの閲覧はPCのみからではありません。スマホやタブレットから閲覧するユーザーも多く、そのようなモバイル端末からの見え方を意識する必要があります。
現在Googleは、スマホサイトの使いやすさが重要視され、PCページのみでは評価を受けにくい傾向があります。
モバイル対策していないWebサイトは、スマホの検索の順位が下がるような仕組みになっています。そのため、上位表示を受けるために、モバイル端末に向けたSEO内部対策を実施しましょう。モバイル端末から見えやすくするWebサイトのデザインに関してこの記事で取り上げていますので、ご覧ください。
Webサイトの表示速度をはやくする
Webサイトの表示速度が遅いと、ユーザーの離脱が起きます。
2018年7月にはGoogleスピードアップデートが導入され、表示速度が極端に遅いWebサイトに順位に影響を与えるようになりました。そのため、表示速度も検索上位表示に必要なものになりました。
Webサイトの表示速度をはやくするには下記のような対策が重要です。
- 画像を圧縮する
- 不要なCSSを消す
実際にWebサイトの表示速度を測る場合、Googleが提供しているPagespeed InsightsでURLを入力すると表示速度を測定できます。
オウンドメディア運営で起こしやすい失敗
ここまでは、オウンドメディアのSEO対策について解説してきましたが、ここからはオウンドメディア運営で起こしやすい失敗について解説します。
PV数が増えてきてもCVが増えない
SEO対策を行い、検索エンジンからの流入数が増えても、コンバージョンが増えないということが起こってしまう場合があります。
要因として考えられるのは、キーワード選定にあります。検索ボリュームの大きいキーワードで作成した記事は上位表示されれば、流入には繋がりますが、コンバージョンに繋がらないこともあります。
例えば、ダイエットを目的としたトレーニングサービスを提供している企業がコンバージョン数を増やしたい場合。
- ダイエット 方法
- ダイエットトレーニング 費用
「ダイエット 方法」のキーワードの検索ボリュームは多いので、このキーワードで記事を制作すれば、流入数は期待できるかと思います。しかし、ダイエットのトレーニングを提供している会社のサービスを申し込む層からは少し遠いキーワードなので、コンバージョンはあまり見込めません。一方、「ダイエット トレーニング 費用」と検索するユーザーはダイエットのためのトレーニングを申し込む費用を具体的に検索しているので、コンバージョンに近いキーワードと言えます。
このように、キーワードを選定する時は、何をねらったキーワードなのか意識することをおすすめします。
キーワードのカニバリが起きる
キーワードのカニバリとは、同じWebサイトの複数のページが同一検索キーワードに対して、競合している状態のことです。ちなみに、カニバリとはカニバリゼーションの略で、日本語では共食いを意味します。
カニバリが発生すると、被リンク、コンバージョン、CTRなど各指標を2つに分割された状態になるため、上位表示されにくくなる現象が発生します。
そのため、キーワードを選定するときは、キーワードのカニバリが発生しないか確認しましょう。
キーワード難易度/キーワードグルーピングを使用すれば、あらかじめカニバリが発生しそうなキーワードを特定できます。
オウンドメディア全体の戦略設計
オウンドメディアの運用を始める前に、まずは全体の戦略設計が重要です。そのオウンドメディアによって何を成し遂げたいかの目標設定をすることで、全体の方向性を決めることができます。
目標を設定することで、ターゲットとしたいユーザーやサイトコンセプト、獲得キーワード等を決めることができます。まずは、オウンドメディア全体の戦略設計を行い方向性を明確にした上で、サイト設計やコンテンツ設計をしていく必要があります。
SEO対策は、サイト設計やコンテンツ設計の部分に当たるため何よりも初めはオウンドメディア全体の戦略設計が重要です。
注目されているオウンドメディアのSEOトレンド
アメリカの有名なSEO調査会社であるBACKLINKOが発表している2021年のSEOトレンドをの中で、オウンドメディアに活用できるものを4つ紹介します。これから更に注目されていくSEO対策なので、今のうちからしっかりと対策しておきましょう。
オウンドメディアのUX改善
グーグルが2020年に発表した、Webページのユーザーエクスペリエンス(UX)に関する重要指標であるコアウェブバイタルが注目を集めています。ウェブでのユーザー体験の向上を目的とした取り組みである、ウェブバイタルの中でも特に重要なものとして3つの指標を「コアウェブバイタル」と設定しています。
ページ表示速度を測る指標(LCP)、サイトのインタラクティブ性や反応速度を測る指標(FID)、レイアウトのずれなどの視覚要素の安定性を示す指標(CLS)の3つの指標が2021年5月よりリリースされました。
デバイスの進化にともない、ユーザーのつかい勝手を重視したサイトが求められてきています。今後は、コアウェブバイタルの3つの指標に合わせてオウンドメディアのUIを見直していく必要がありそうです。
専門家を活用した記事作成
Googleの公式ガイドラインにおいても、重要であると明記されている権威性、信頼性、専門知識(E-A-T)ですが今後さらに重要視される傾向になると予測されています。
全く同じ質のコンテンツでも、一般人が書くよりもその分野に精通した人が書いた記事の方が順位が上がりやすくなるため、誰が発信していて、信頼できる情報なのかを示していく必要があります。
そのため、オウンドメディア内のコンテンツを作成する際には、その分野に精通している人が書いているということを示すこと、または専門家に記事を監修してもらうなどの専門家を活用した記事制作が必須になってきます。
動画のSEO対策
近年では、動画から情報を得るユーザーが増えており、検索エンジンの検索結果に動画が表示されることも多くなってきました。それに伴い、動画のSEO対策も重要度を増してきています。
オウンドメディアのコンテンツ内に動画を埋め込んだり、動画のタイトルや概要欄に対策したいキーワードを含めるなどの対策を行い、動画の内容をGoogleに知らせることが重要です。
また、動画コンテンツはテキストや画像のみのコンテンツに比べて検索ユーザーに視覚的なインパクトを与える他、検索ユーザーのサイト滞在時間を長くできます。そのため、コンテンツと関連性の高い動画を組み込むことでサイト滞在時間を高め、結果的にSEO対策に結びつく場合もあります。
タイトルやメタ情報の最適化
BACKLINLOの調査(※2)によると、スマートフォンのオーガニック検索のクリック率は、2015年から41.4%減少しています。原因としては、Googleが検索結果にスニペット表示やFAQを表示させるなどの、ユーザー課題の早期解決のために進化をしているからだと考えられます。
そのため、このような進化した検索結果からオウンドメディアの集客に繋げるためにはタイトルやメタ情報をユーザーにとって魅力的なものに最適化していかなければなりません。タイトルやメタ情報はユーザーが検索した際の最初に目に触れる情報となるため、ユーザビリティやクリック率に大きな影響をもたらします。UXの観点からも正しく設定することが必要です。
オウンドメディアのSEOでよくある質問は?
Q:キーワード選定でおすすめのツールはありますか?
Answer)Googleが提供する、キーワードプランナーがおすすめです。
キーワードプランナーは、キーワードの検索ボリュームの抽出機能があります。
ただし、無料で使用する場合は検索ボリュームがアバウトに表示されます。Google広告に出稿すれば、正確なデータを取得できます。
また、キーワード選定とは【初心者向け】良いキーワード選定のコツなどを徹底解説!ではキーワード選定ツールも紹介していますので、ご覧ください。
Q:オウンドメディアの運用目的にはどんなものがありますか?
Answer)運用目的には大きく下記のものがあります。
- 見込み客の獲得
- 企業や商品・サービスの認知拡大
- 企業や提供しているサービスのブランディング
- 採用力の強化
- マネタイズ
Q:オウンドメディアで発信するコンテンツにはどんなものがありますか?
Answer)コンテンツには下記のようなものがあります。
- 記事コンテンツ
- 画像コンテンツ
- 動画コンテンツ
- 口コミ・レビュー
- 診断コンテンツ
- メールマガジン
オウンドメディアの運用目的によって、最適なコンテンツが変わってきますので、目的に応じてコンテンツは作成しましょう。
まとめ
 この記事ではオウンドメディアのSEO対策について解説してきました。SEO対策とは、Googleなどの検索エンジンで、Webサイトが上位表示しやすいように対策することです。オウンドメディアは立ち上げ初期は、成果の出にくいものです。そのため、SEO対策を適宜行わないと、上位表示されず、ユーザーから見てもらえないオウンドメディアになりかねません。この記事が、御社のオウンドメディア成功の一助となれば幸いです。
この記事ではオウンドメディアのSEO対策について解説してきました。SEO対策とは、Googleなどの検索エンジンで、Webサイトが上位表示しやすいように対策することです。オウンドメディアは立ち上げ初期は、成果の出にくいものです。そのため、SEO対策を適宜行わないと、上位表示されず、ユーザーから見てもらえないオウンドメディアになりかねません。この記事が、御社のオウンドメディア成功の一助となれば幸いです。