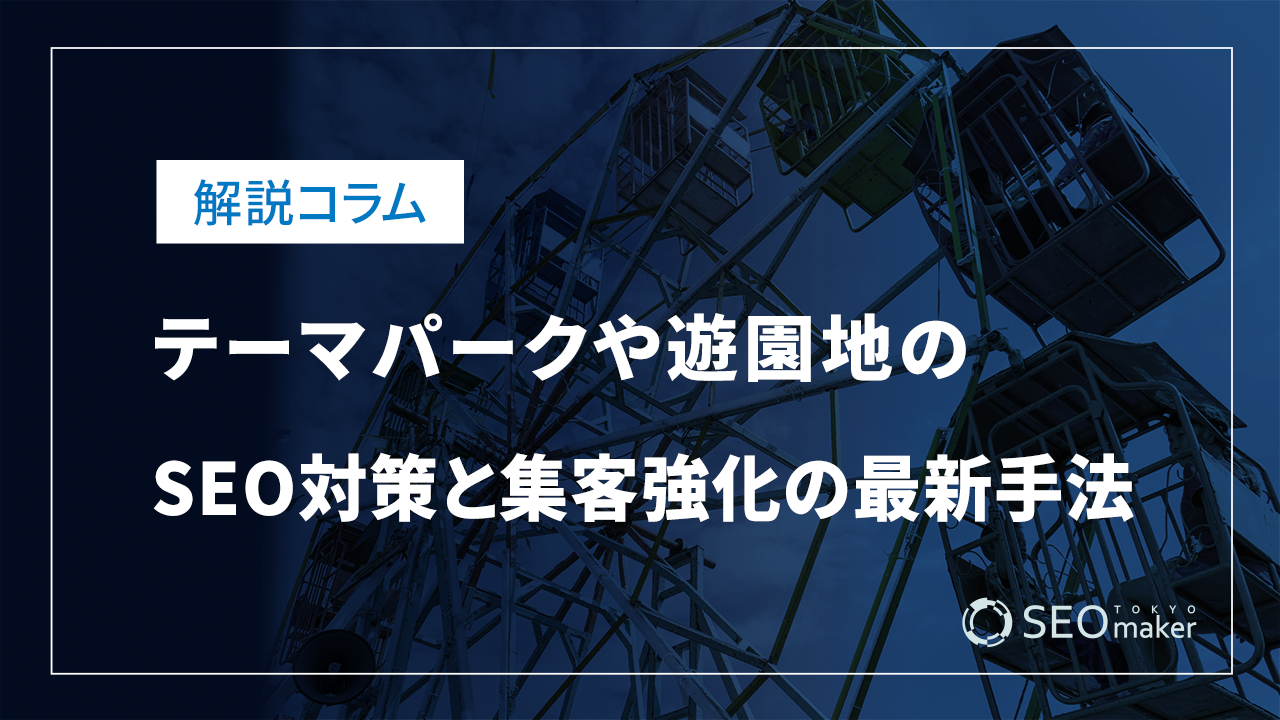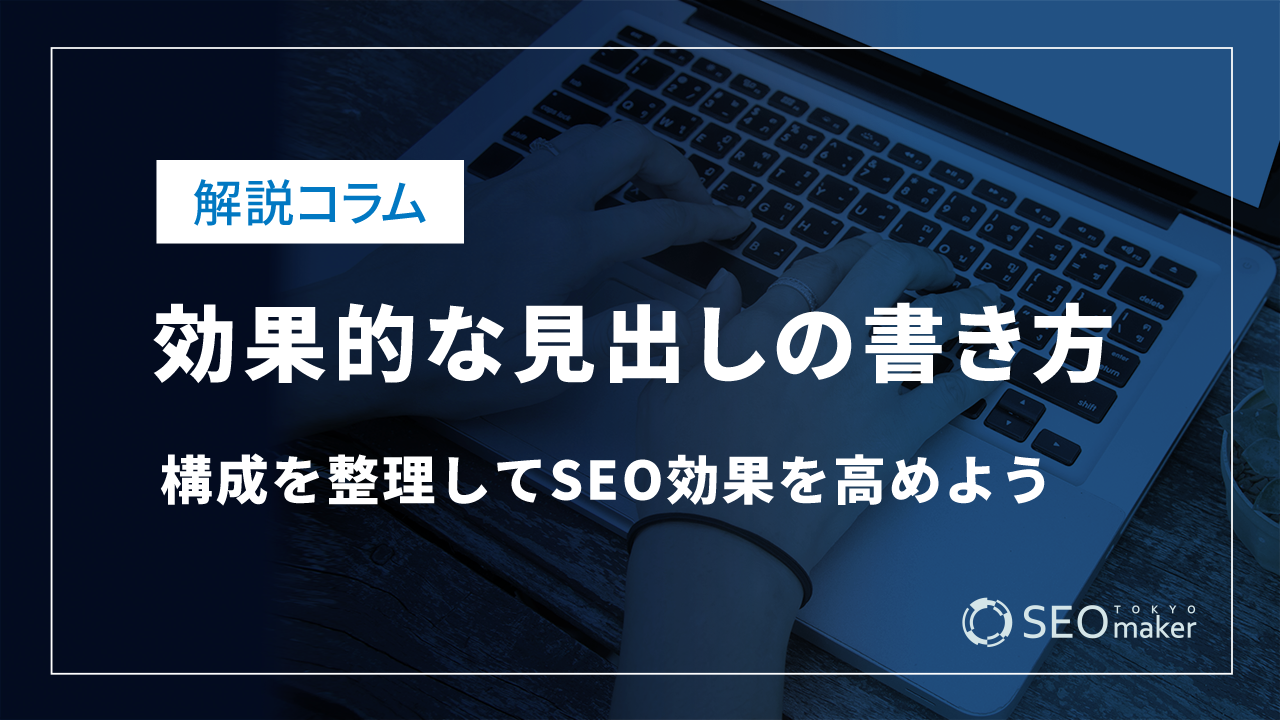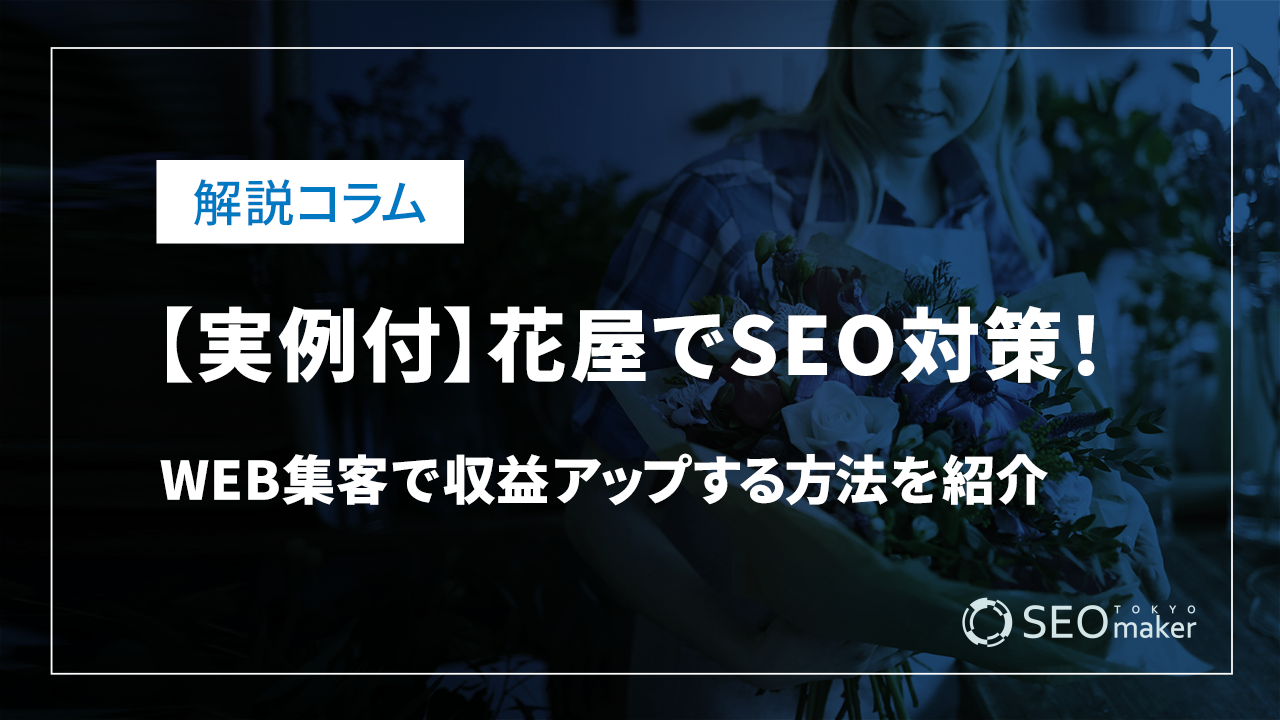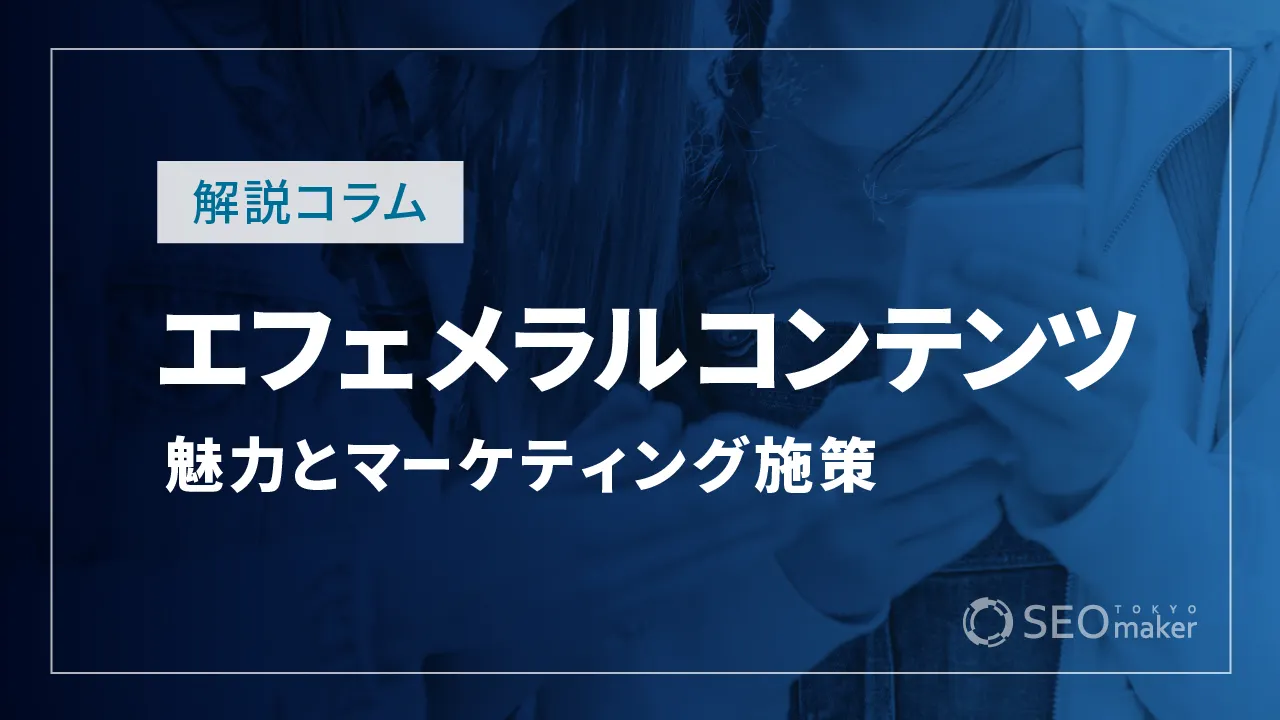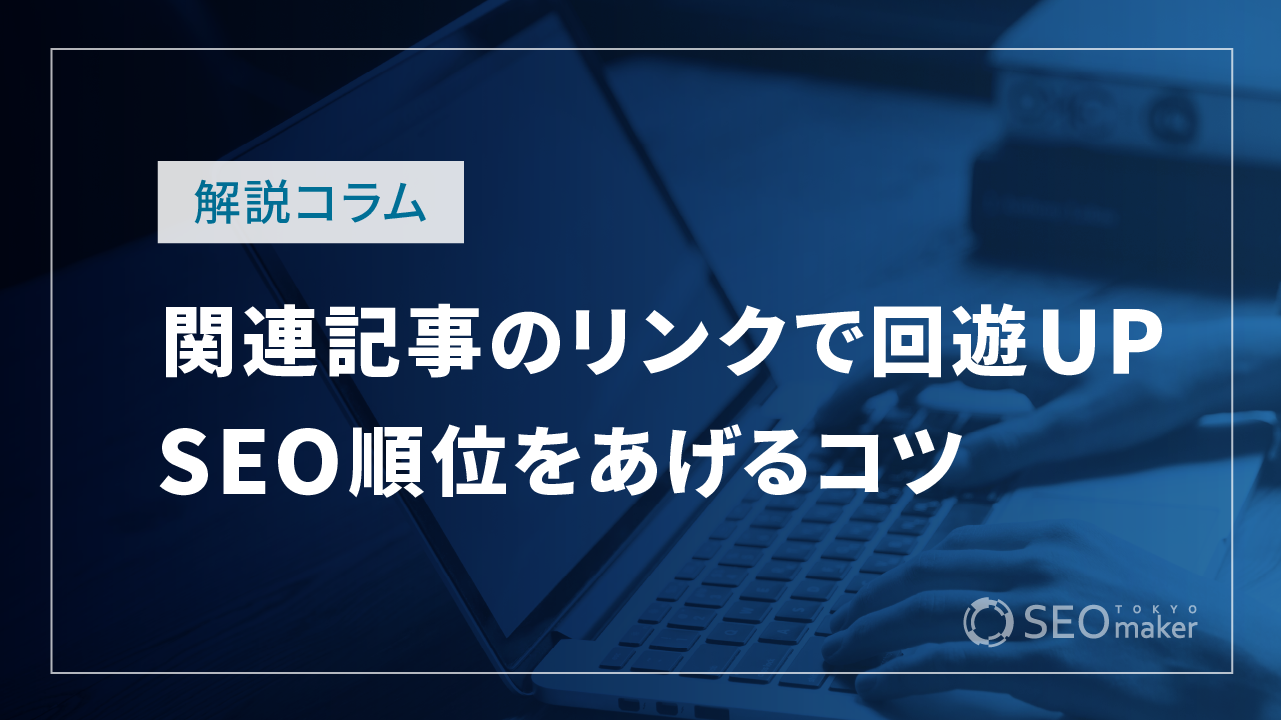リダイレクト(redirect)の意味とは?目的やSEOで必要な場面・設定方法を解説
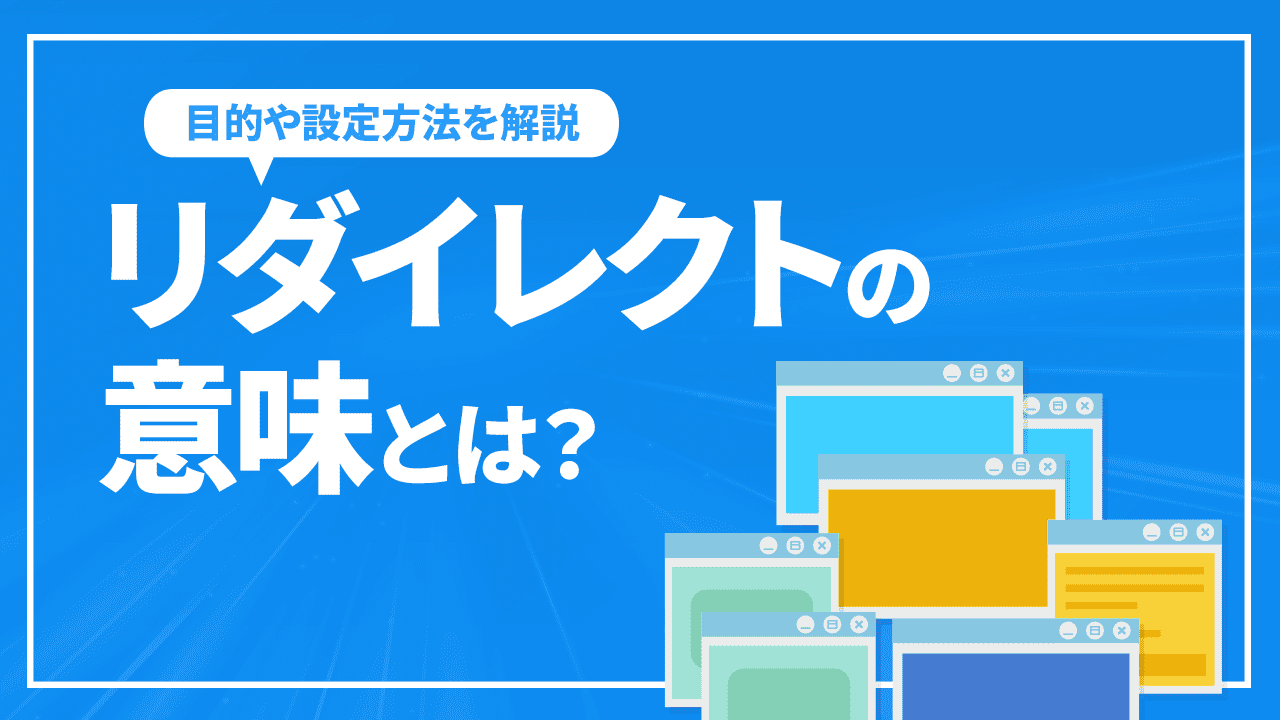
Webサイトを運営していると「リダイレクト」という単語を耳にすることがあります。これは、特定のページを訪問したユーザーを指定のページへ転送する方法のことです。
リダイレクト元のページのSEOの評価をリダイレクト先に引き継ぐことができます。
複数のサイトを1つにまとめたり、メンテナンスを行ったりするときには必要になるため、Web担当者なら知っておいて損はありません。
 そこで本記事では、リダイレクトの意味や実装する理由、具体的な導入方法などを解説します。
そこで本記事では、リダイレクトの意味や実装する理由、具体的な導入方法などを解説します。
リダイレクト(redirect)の意味とは何か
リダイレクトは、サイトを訪問したユーザーを事前に指定した別ページに遷移させる仕組みです。サイト運営者の視点で考えると、古いページから新しいページへ訪問者を移動させるために使う手法といえます。
反対に利用者目線では、自動でページが遷移するためリダイレクトについて意識したことがある方は少ないかもしれません。ただこの手法がないと、たとえばブックマークするサイトのURL更新時にページへアクセスできません。リダイレクトによって自動で転送されないので、更新前の古いものにつながってしまうためです。
よって運営者は、ユーザーを自動で遷移させる仕組みを理解しておく必要があります。Web担当者には必須の知識なので、利用経験がない方は理解を深めておいてください。
リダイレクトのメリット
リダイレクトのメリットはSEOとユーザビリティの2つの側面があります。リダイレクト元のページのSEO評価をリダイレクト先に引き継ぐことができます。
これは逆をいえば、リダイレクトをしないことで新サイトや新しいページを作った際に古いサイトやページの評価がどこにも受け継がれずになくなってしまうことを意味します。
そのため、もともとページ評価や検索順位が高かった際には非常に大きな損失となります。
そして、サイトリニューアルの際には古いページURLは削除され、新しいURLになるということがよくあります。
この場合、ユーザーが古いページをブックマークしていた場合には目的の記事にたどり着きづらくなり、ユーザビリティがよくありません。しかし、正しくリダイレクトをすることでストレスなく対象の記事にアクセスすることが可能になります。
リダイレクトの仕組み
設定したURLへ自動で転送する仕組みがリダイレクトです。
通常「http.example」にアクセスしてきユーザーには、URLの情報をそのまま表示します。しかし新しいURLとして「http.example-2」を転送先に設定することによって、元のURLである「http.example」にアクセスしてきたユーザーを自動で転送できます。
リダイレクトの流れ
- ユーザーが「http.example」にアクセス
- Webサーバーがユーザーへ「http.example-2」へのアクセスを要求
- ユーザーが「http.example-2」にアクセス
- Webサーバーが「http.example-2」の情報を返答
厳密には一度Webサーバーからユーザーへのアクセス要求を挟みますが、ユーザー側からは見た目が変わらずに自動で転送されている状態となります。
リダイレクトの必要性
リダイレクト設定が必要な理由は、閲覧ユーザーの利便性とSEOの評価を維持するためです。特にSEOの評価はサイト運営で欠かせない要素のため、どのサイトにも共通して重要な設定といえるでしょう。
ここでは、リダイレクト設定の必要性について詳しく解説していきます。
ユーザビリティを高めるため
リダイレクトを設定する主な理由は、ユーザビリティを高めるためです。
仮にサイトのリニューアルやページのメンテナンス時など別のURLを使用するタイミングでは、新しいURLをユーザーへ知らさなければいけません。
もしも何も設定していなければ、ページが表示されないだけでなく、ユーザーはサイト内でページを探し続ける状態となります。求めているページが見つからなければほとんどのユーザーはサイトから離脱してしまい、最終的にはサイト全体の評価を下げることにもつながるでしょう。
このようにリダイレクト設定がなければ新規・既存問わずに重要な顧客を失う行為となるため、ユーザービリティを高め、適切なURLを表示させることは重要です。
SEO対策を強化するため
リダイレクト設定が重要な理由は、ユーザービリティだけでなくSEOを対策するためでもあります。
仮に設定をしないままでいると、古いURLと新しいURLはまったくの別物と扱われます。そのため古いURLで積み重ねてきたSEOの評価は何も活かせません。
しかし正しく転送先に設定を行えば、古いURLのSEO情報を引き継ぐことが可能です。
特にアクセス数の多いページや、問い合わせ・購入への成果が高いページであれば、SEO情報の引き継ぎは欠かせない要素といえるでしょう。
SEOで評価を得ることは難しいため、長期間運営していたサイトであればあるほど重要な役割をもちます。
すべてをトップに転送するのはNG
ユーザビリティの観点から古いURLをトップページやカテゴリトップにリダイレクトするという方もいますが、原則的に全てをトップに転送することは推奨されません。
リダイレクトの中でも後述する301リダイレクトがよく使われますが、これは同じ内容の記事が古いページから新しいページに移ったことを意味する設定だからです。
トップページやカテゴリトップに転送させるのは本当に対象ページがなくなった場合に限りますので、基本的には旧ページと新ページを1対1でつなぐようにしましょう。
リダイレクトは必須ではない
特にサイトリニューアルの際によく使われるリダイレクトですが、必須の設定ではありません。
むしろ、URL変更に伴い仕方なく設定する意味合いもありますので、URLを変更する必要がないのであればリニューアルしたとしても、そのままのURLを維持することが推奨されます。
これは正しいリダイレクトの設定をしたとしてもSEO評価のすべてが引き継がれるわけではなく、多少の損失が発生するためです。
Googleは公式ではリダイレクトにより損失は起こらないと発言していますが、弊社の体験では、SEO評価の一部が損失して順位を落とすケースがあります。
リダイレクト(redirect)の目的
では、ユーザーを遷移させる設定はなぜ必要なのでしょうか。実装する目的は、大きく以下の2つです。
- ユーザビリティの低下防止
- SEOでのマイナス評価防止
それぞれ詳しく解説します。
1. ユーザビリティの低下防止
一つ目の目的は、訪問者にとって利用しやすいサイトにすることです。転送設定をしていないと、ユーザーは古いページを訪問してしまいます。つまり、ユーザーは閲覧を希望していたコンテンツにアクセスできません。
インターネットの利用時、コンテンツが表示されないページにつながってがっかりした経験がある方は多いのではないでしょうか。古いページから自動で転送されないと、大半の方は別サイトで情報収集を始めます。アクセスユーザーの減少にも直結するため、転送設定をすることは重要です。
関連記事: コアウェブバイタル(Core Web Vital)とは
2. SEOでのマイナス評価防止
二つ目の目的は、SEOでのマイナス評価を受けないことです。サイトやページが移動になったのに転送設定をしないと、GoogleやYahoo!は移動後のサイトを新しいものとして認識しません。そのため、たとえば上位表示しているページを更新した際には、URLの変更をGoogleなどが認識できないため評価が引き継がれないのです。
ページが移動になったと伝えている対象は、サイト訪問者だけではありません。不要なマイナス評価を防ぐためにも、適切なタイミングで正しく設定しましょう。
リダイレクト(redirect)が必要になる主な場面
サイト訪問者を転送する設定は、次のような場面で必要になります。
- サイトのリニューアル時
- ドメイン変更時
- サイトのSSL化時
- 一部ページでの不具合発生時
- サイトのメンテナンス時
まず考えられるのは、サイト更新時やドメイン変更時です。このケースで転送設定をしないと、URLを記録するユーザーは古いページを訪問してしまいます。通信を暗号化(https化)するSSL化時にも、同様の理由で実装が必須です。
また、不具合発生時やメンテナンス時といった一時的に別ページへ遷移してほしい場合にも、訪問者を転送させたほうが親切でしょう。メンテナンス中である旨や終了時刻の目安などを把握できると、利用者の不満は軽減されるためです。上記のような対応をする際には、転送設定を欠かさず行ってください。
リダイレクト(redirect)には大きく2種類ある
サイト訪問者を遷移させる方法は、301と302の2種類です。要点を簡潔にお伝えすると、両者の違いは転送を設定する期間にあります。それぞれの詳細を順に見ていきましょう。
1. 301リダイレクト
恒久的に訪問者を転送する301は、サイトの更新時やドメイン変更時など期間が限定的でない場合に行う設定です。この設定をすれば古いサイトやページの評価を引き継げるため、SEOでマイナス評価を受けたくないなら活用しない理由がありません。
301は永続的な転送設定であることを意味するため、検索エンジンに対しても評価を引き継ぎたい旨を伝えられるのです。一時的な変更ではなく、継続的に新規のURLを使用する際には301の設定を行ってください。
2. 302リダイレクト
永続的に訪問者を転送する301に対して、一時的に遷移させる仕組みが302リダイレクトです。301では検索結果に新しいURLが記載されますが、302では古いものが表示されます。そのため、URLを見ただけではページが変更になっているとわかりません。
302の設定は、サイトのメンテナンス時やページに不具合が発生した際などに用います。両者の違いを把握していないと、たとえばドメインを変更したのに302の設定をしてしまい、SEOの評価が失われるなどのトラブルに発展しかねません。転送設定を適切に行うために、2種類の違いについて正しく理解しておくことが大切です。
リダイレクト(redirect)の設定方法の種類
訪問者を転送する設定方法には、以下の2種類があります。
1. サーバーサイドリダイレクト
一つ目は、サーバーの指示によってユーザーを転送する仕組みです。歴史あるWebサーバー「Apache」の.htaccessファイルなどにアクセスしたり、PHPなどのサーバー側のスクリプト言語を用いたりすると設定できます。
やや複雑な内容ですが、ここでは「サーバー側が転送先の情報を返している」と理解しておけば問題ありません。二つ目の転送方法と比べて、すぐに新たなページへ遷移することが特徴です。
2. クライアントサイドリダイレクト
二つ目は、サイト運営者やサーバー管理者などにとっての顧客であるブラウザ側で転送情報を解釈する仕組みです。ページ遷移の情報がHTMLファイル内に記述されており、サーバーから転送の指示を受けない点が一つ目との違いといえます。
Webサイトを閲覧していて「数秒後にページが遷移する旨の表示」を見かけたことがある方は少なくないでしょう。この表示は、リダイレクト設定によりブラウザ側が転送情報を解釈した結果なのです。
Googleの推奨はサーバーサイドリダイレクト
複雑な内容なので、どちらの設定をすべきかと混乱した方がいるかもしれません。結論をお伝えすると、基本的にはGoogleが推奨するサーバー側の設定がおすすめです。
サーバー側が指示を出す方法のほうが、リダイレクトの情報をGoogleが正しく解釈する可能性が高まるからです。いい方を変えると、転送設定をすることでユーザビリティが低下したりSEOでマイナス評価を受けたりする可能性を減らせます。これからリダイレクトの設定をする方は、2種類の違いについて大まかにでも理解しておきましょう。
関連記事: レンダリングとは? Googleクローラとレンダリングの関係を解説
リダイレクト(redirect)の具体的な実装方法
続いては、リダイレクト(redirect)の実装方法を解説します。種類やもっとも一般的な設定方法について、順に確認していきましょう。
実装方法は大きく5つ
リダイレクトの実装方法には、大きく以下の5つがあります。
- .htaccess
- PHP
- meta refresh
- JavaScript
- WordPressプラグイン
.htaccessとPHPを用いる方法はサーバーサイド、meta refreshとJavaScriptを使った方法はクライアントサイドのリダイレクトです。よって可能であれば、サーバーサイドのいずれかを使用することをおすすめします。
なお、JavaScriptでのリダイレクトは、Googleに認識されない可能性があると公表されています。同言語を用いる設定は、サーバー側の二つの方法及びmeta refreshでのリダイレクトが行えない場合にのみ使用しましょう。WordPressを使用している場合は「Redirections」などのプラグインを活用するのも一つの方法です。
もっとも一般的な「.htaccess」による実装方法
ドメイン・ディレクトリ・ページURLを変更する場合の記述例を紹介します。
ドメインの変更
「old.coml」から「new.com」
RewriteEngine OnRedirect permanent / https://www.new.com/
ディレクトリの変更
「example.com/old/sample.html」から「example.com/new/sample.html」
記述例)
RewriteEngine on
RewriteRule ^old(.*)$ /new$1 [R=301,L]
ページURLの変更
「example.com/old.html」から「example.com/new.html」
記述例)
RewriteEngine on
RewriteRule ^old.html$ /new.html [R=301,L]
Googleが公表する設定方法を知りたい方は、こちらのページをご覧ください。
リダイレクト(redirect)設定後に確認すべきこと
次にこの章では、サイトやページの転送設定をした後に確認すべき内容を紹介します。
- ページが正しく遷移するか
- 検索結果に表示されるか
1. ページが正しく遷移するか
転送設定をしたら、実際にページが遷移するかどうか確認しましょう。意図したとおりにページが遷移しない場合は、誤った設定をしている可能性があるからです。
リダイレクトが正しく実装されているかどうかは、301・302・303などのステータスコードを見ることでも確認できます。ステータスコードを確認する無料のツールも多くあるため、必要に応じてこれらのサービスを活用するとよいでしょう。
2. 検索結果に表示されるか
ページの遷移だけでなく、検索結果への表示を確認することも大切です。適切に表示されない場合は、やはり実装方法を誤っているかもしれません。
リダイレクトの設定が検索エンジンに反映されるまでには、基本的に数週間程度かかります。設定直後にはクロールに認識されていないことがあるので、確認するのはある程度時間が経過してからにしてください。
リダイレクト設定時の注意点
リダイレクトは少しでも設定が間違っていると正しく転送できません。なかには転送が永遠に続いてしまう状態もあるため、設定時だけでなく定期的な確認をおすすめします。
ここでは、リダイレクト設定時の注意点について詳しく解説していきます。
リダイレクトループにならないようにする
リダイレクトが正しく設定されていない場合、ページを永遠に転送し続けてしまうリダイレクトループの状態になることがあります。リダイレクトループが発生するとユーザーはページへアクセスできないため、転送先や設定を再確認しましょう。
リダイレクトの確認は、無料ツールの「リダイレクトチェッカー」で確認できます。リダイレクト順に処理速度も表示されるため、定期的な確認にも活用可能です。
リダイレクト先を確認する
根本的な問題ではありますが、リダイレクト先が正しく設定されていなければページの転送は行われません。そのためリダイレクト先はかならず確認しましょう。
特にクライアントサイドリダイレクトを設定する場合、ユーザーのPCやブラウザ環境によって正常に作動しないことがあります。
さまざまな状況に対応するためにも「転送しない場合は下記をクリック」などの文言とともに転送先のURLを設置し、安心してユーザーを誘導できる状態にしておきましょう。
リダイレクト警告の原因と対処法
リダイレクト設定をしたものの、ページを開くと「リダイレクト警告」と表示されてしまう場合があります。リダイレクト警告はGoogleがなんらかの判断によって、転送先へのアクセスを危険視した場合に表示されるアラートです。
表示されるまま放置するとユーザーへ不安を与えてしまうため、早急に対象をしましょう。
ここでは、リダイレクト警告の原因と対処法について詳しく解説していきます。
ブラウザに保存されたCookie
最初に考えられる原因が、ブラウザに保存されているCookieです。Cookieとはユーザーがアクセスした際のログイン情報のことをいい、簡単に削除できるため最初に試してみましょう。
Cookieの削除方法はブラウザによって異なりますが、基本的に各ブラウザの設定画面から行えます。
GoogleChromeの場合は以下の流れです。
- Chromeの「設定」を開く
- 「プライバシーとセキュリティ」→「Cookieと他のサイトデータ」を選択
- 「すべてのCookieとサイトデータを表示」→「すべて削除」をクリックすると削除完了
非SSL化ページへのリダイレクト
つぎに考えるべき原因は、非SSL化ページへのリダイレクトです。Googleはセキュリティ強化の観点からSSLを推奨しています。そのためSSL化されていないページへ転送する際は、セキュリティ問題として警告が表示される仕組みです。
もしもリダイレクト設定を行いたい場合は転送先をSSL化し、再度設定しなおすことで解決できます。
関連性が無いページへのリダイレクト
続いての原因は、元のURLと関連性が無いページへリダイレクト設定を行っている場合です。Googleは元のURLからSEO情報を引き継ごうとするため、内容の違いや関連性を確認しています。
そのため仮にまったく関連性の無いページへリダイレクトを行っている場合、Googleからはエラーとして警告を発する仕組みとなるため注意をしましょう。
SEO情報を正しく引き継ぐためにも、できるだけ元のURLと同じ内容であり、関連性が強いページを設定することが重要です。
短縮URLを使用している場合
最後の原因が、リダイレクト先に短縮URLを使用している場合になります。
短縮URLは、本来は長いURLであっても簡潔化できる点がメリットです。しかし短縮URLから表示する場合は専用のサーバーを通す必要があるため、ページを表示するためには2つのサーバーを経由することになります。
リダイレクト設定では関連性の無いページへのアクセスはエラーの要因となり、短縮URLであっても警告が出やすいといえるでしょう。
したがって短縮URLは使用せずに、本来のURLをリダイレクト先に設定することが重要です。
リダイレクトチェーンとリダイレクトループ
サイト運営が長いとリニューアルを繰り返したり、構造変更が数回行われるということがあります。このような時に正しくリダイレクトを設定していても想定していない動きをすることがあります。
中でも特に注意すべきはリダイレクトチェーンとリダイレクトループです。
リダイレクトチェーン
リダイレクトチェーンとは
サイトリニューアルが2回以上ある場合には旧URLを新URLに転送することが2回以上起こることがあります。このようなリダイレクトのリダイレクトのことをリダイレクトチェーンと呼びます。
一定規模以上のサイトになるとリダイレクトチェーンが起きることはありますが大きな問題になることはほとんどありません。しかし、リダイレクトを繰り返すということはサーバーに負荷がかかりますし、ユーザーにも若干の待ち時間が発生するため望ましいことではありません。
可能であればリダイレクトチェーンは解消するようにしてください。
もしリダイレクトの回数が5回以上だった場合にはGoogleが最終URLを認識しない可能性がありますので,
早急に修正することを強く勧めます。
リダイレクトループ
リダイレクトループとは、リダイレクトを繰り返すうちに同じURL内でグルグルとループをしてしまい、最終URLにたどり着かないことを指します。
ループしてしまうとユーザビリティが著しく悪くなりますし、Google botにも正しく認識されないページができることになりますので、早急に修正すべきといえます。
リダイレクトによるSEO効果
301リダイレクトでページを転送するときに、旧ページのSEO評価は新ページに引き継がれます。そのため、今までサイト運営をしていて評価された価値をそのまま使うことが可能になります。被リンク効果も同時に引き継げるため、正しくリダイレクトをしないことで大きな損失につながる場合があります。
301リダイレクトはGoogleも推奨している方法ですので、SEO評価の維持のためにも必ず設定しましょう。
301リダイレクトをすればSEO評価は失われない
以前、Googleはリダイレクトを行うと旧ページの価値の8割~9割程度しか引き継げないとしていました。スパム行為を防ぐために意図して仕様になっていたからです。これはGoogleのMatt Cutts(マット・カッツ)氏の発言ですので間違いありません。
しかし、現在ではこのようなスパム行為もGoogle判断することができるようになり、リダイレクトを行うことでSEO評価が失われることはないとGoogle John Mueller(ジョン・ミューラー)氏が発言しています。
ただし、そもそもリダイレクトはしない方がユーザビリティは高いわけですから、リダイレクトしないサイト構造や設計を考えるべきでしょう。
Google botは5回までリダイレクトを追う
検索結果に反映するためにGoogle botは日夜サイトをクロールしていますが、リダイレクトがあった場合にはGoogle botは5回までしかリダイレクトを追いません。
つまり、リダイレクトが5回以上行われるとクロールされないページが出てくることになりますのでSEO的には大きくマイナスです。もしもリダイレクトを繰り返しているようであれば修正するべきです。
ただし、5回までしか追わないのはGoogleの仕様ではなくRFC1945では以下のように定めているためです。
9.3 Redirection 3xx
This class of status code indicates that further action needs to be
taken by the user agent in order to fulfill the request. The action
required may be carried out by the user agent without interaction
with the user if and only if the method used in the subsequent
request is GET or HEAD. A user agent should never automatically
redirect a request more than 5 times, since such redirections usually
indicate an infinite loop.
このことからGoogle検索セントラルでは次のようになっています。
HTTP/1.0 の RFC 1945 で定義されているように、5 ホップ数以上リダイレクトした後、停止して 404 として処理します。
リダイレクト(redirect)についてよくある質問
最後に、リダイレクト(redirect)についてよくある質問に回答します。
- リダイレクトについてサイト運営初心者が知っておくべきことは?
- 301リダイレクトはいつ解除したらいい?
- リダイレクトの警告が出た場合はアクセスしないほうがいい?
- サイト利用時にリダイレクトが繰り返された場合の対処法は?
1. リダイレクトについてサイト運営初心者が知っておくべきことは?
最低限、リダイレクトには以下の2種類があることを知っておきましょう。
- 301リダイレクト:恒久的にユーザーを転送する
- 302リダイレクト:一時的にユーザーを転送する
これらは、用途に応じて使い分ける必要があるからです。転送設定をする理由によって、どちらの設定をすべきかは異なります。違いを正しく把握し、適切な方法で設定しましょう。
2. 301リダイレクトはいつ解除したらいい?
少なくとも、1年程度は解除しないことをおすすめします。あまり時間が経過していない状態で解除すると、検索エンジンにドメインやURLの変更を認識してもらえないからです。
また、外部サイトから自サイトへのリンクがある場合に、変更前のページが表示されてしまう恐れがあります。一つの目安として、変更前のページにアクセスがある間はリダイレクトを解除しないほうが無難でしょう。
3. リダイレクトの警告が出た場合はアクセスしないほうがいい?
Webサイトの閲覧時、不適切なリダイレクトが設定されているとGoogleが判断した場合には、画面に警告が表示されます。「http://example.comにリダイレクトしようとしています」といった旨の警告を見たことがある方は多いでしょう。
警告が出たページは転送設定を誤っている可能性があり、なかには悪意を持って不正なリンクへ誘導しているケースもあるため危険です。信頼性に乏しいサイトで警告表示が出たら、基本的にはアクセスを避けましょう。
4. サイト利用時にリダイレクトが繰り返された場合の対処法は?
誤った転送設定をしているサイトにアクセスすると「リダイレクトが繰り返し行われました」と表示されることがあります。多くの場合は設定側に問題があるため、サイト利用者に非はありません。ただ、ユーザー側で実施できる対処法もいくつか存在します。
- ブラウザの再起動
- シークレットモードでのアクセス
- Cookieの削除
再起動やシークレットモードでの閲覧であれば、実施するのにあまり手間はかかりません。どうしてもサイトにアクセスしたい場合は、上記の方法を試してみてください。
まとめ
 リダイレクトは、特定のページにアクセスしたユーザーを指定した別ページへ転送する仕組みです。ユーザビリティの低下やSEOでのマイナス評価を防止するためには、目的に応じた適切な転送設定をすることが欠かせません。初めてリダイレクトを設定するなら、少なくとも301と302の違いを把握しておくことは必須です。本記事を参考に、ぜひ自サイトに適したリダイレクトを設定してみてください。
リダイレクトは、特定のページにアクセスしたユーザーを指定した別ページへ転送する仕組みです。ユーザビリティの低下やSEOでのマイナス評価を防止するためには、目的に応じた適切な転送設定をすることが欠かせません。初めてリダイレクトを設定するなら、少なくとも301と302の違いを把握しておくことは必須です。本記事を参考に、ぜひ自サイトに適したリダイレクトを設定してみてください。