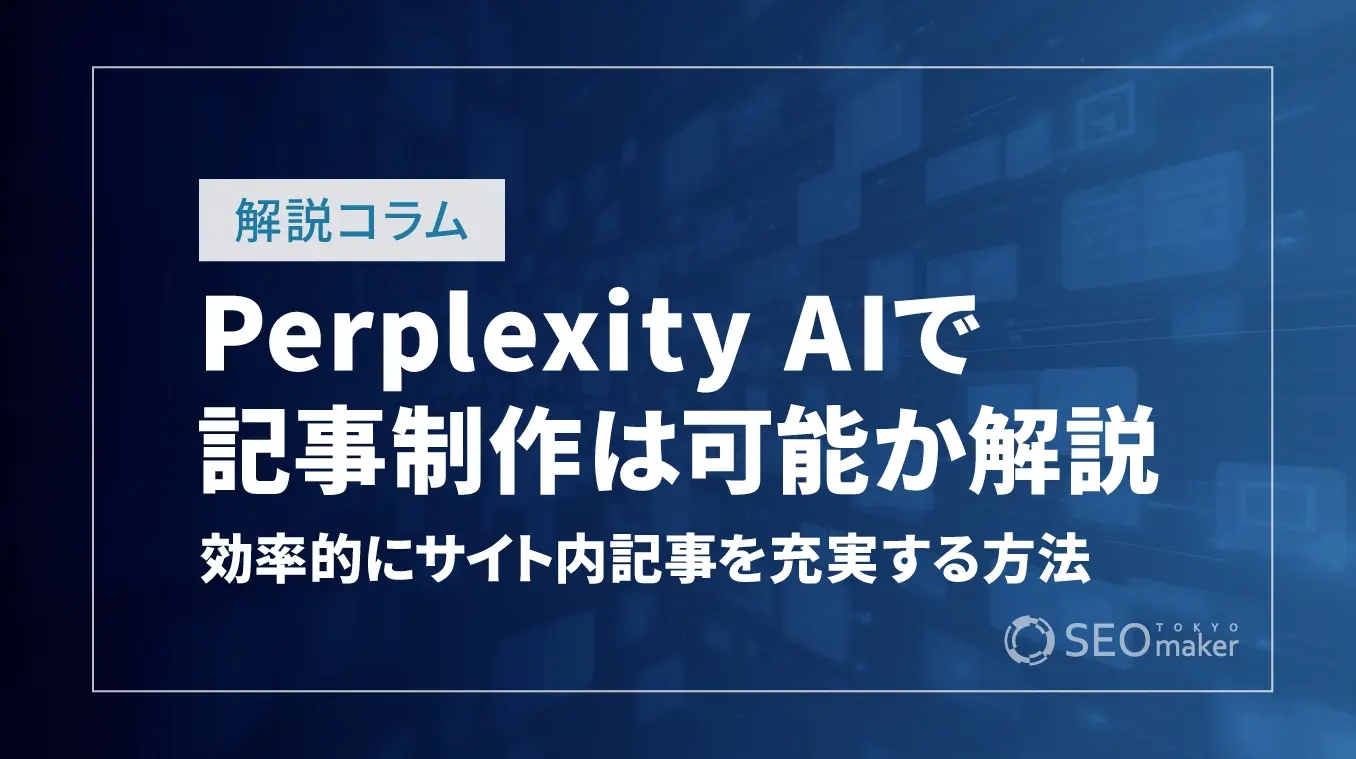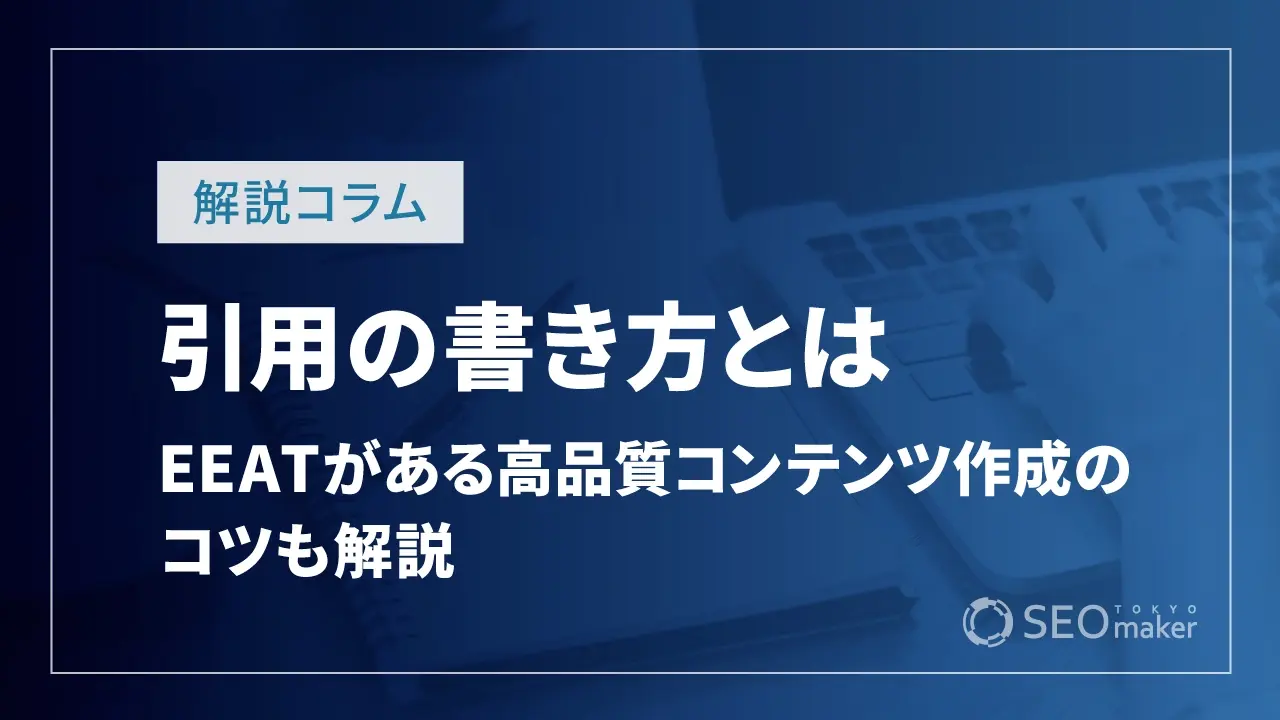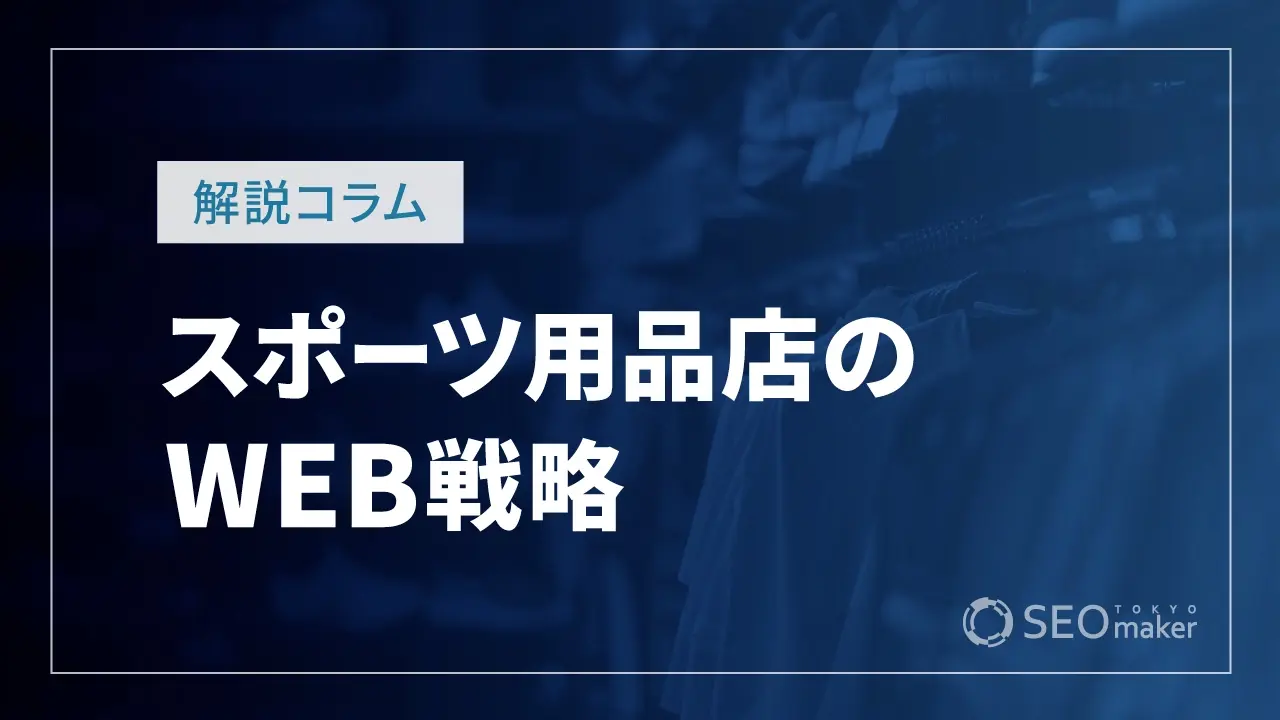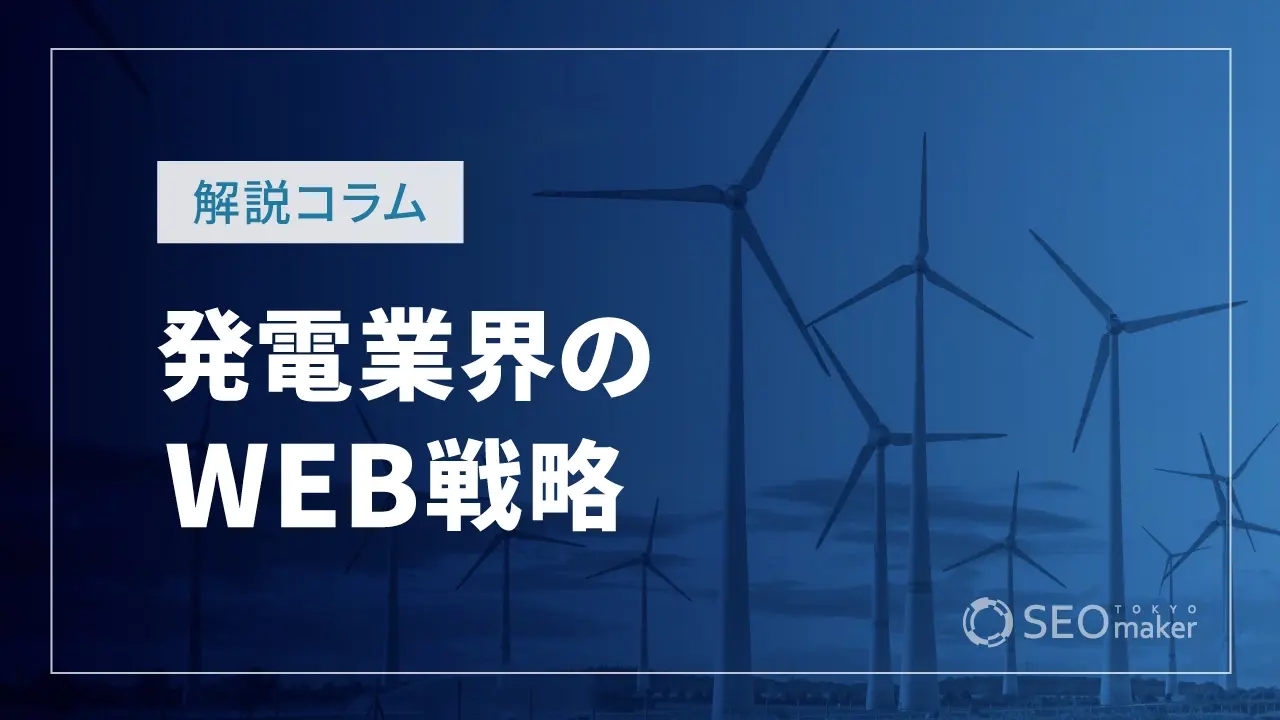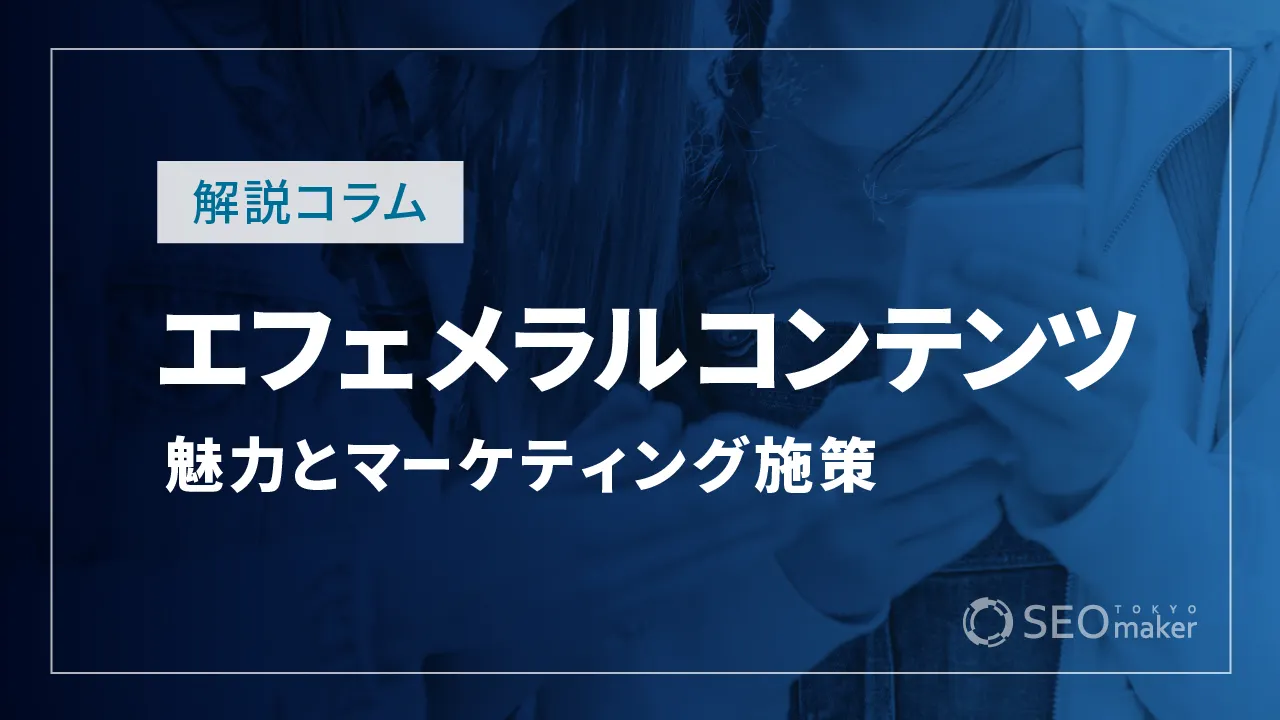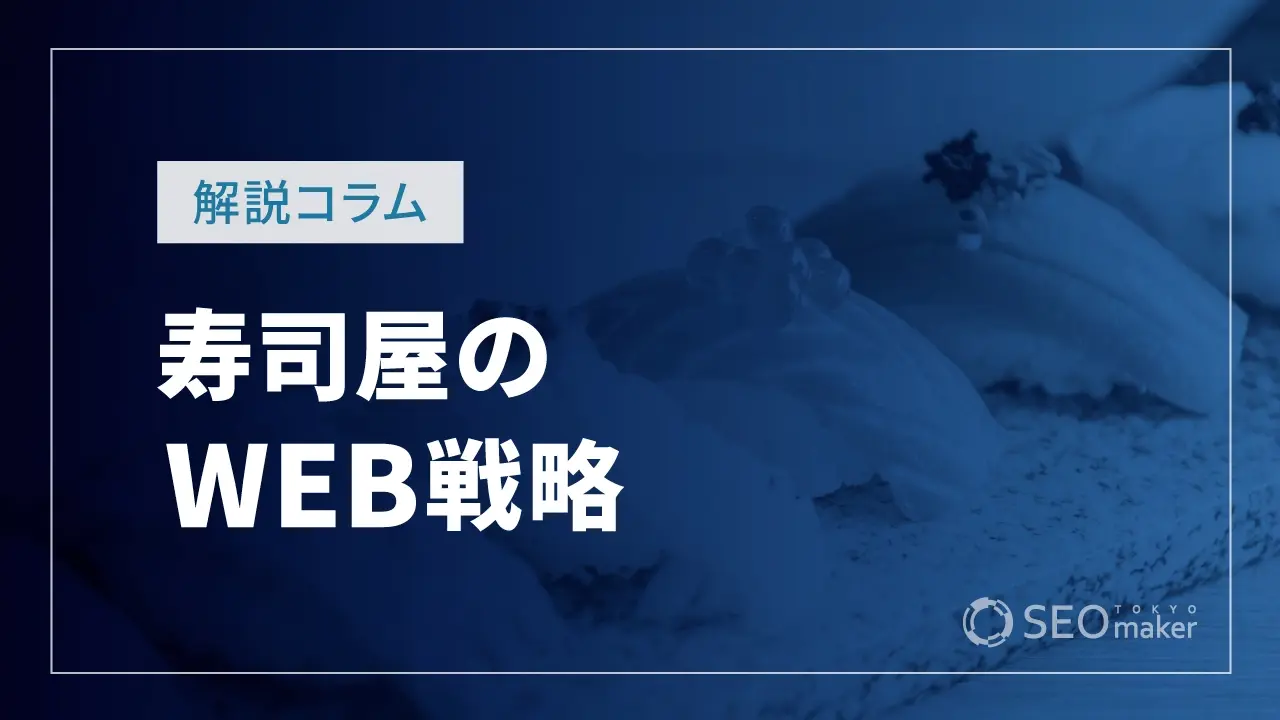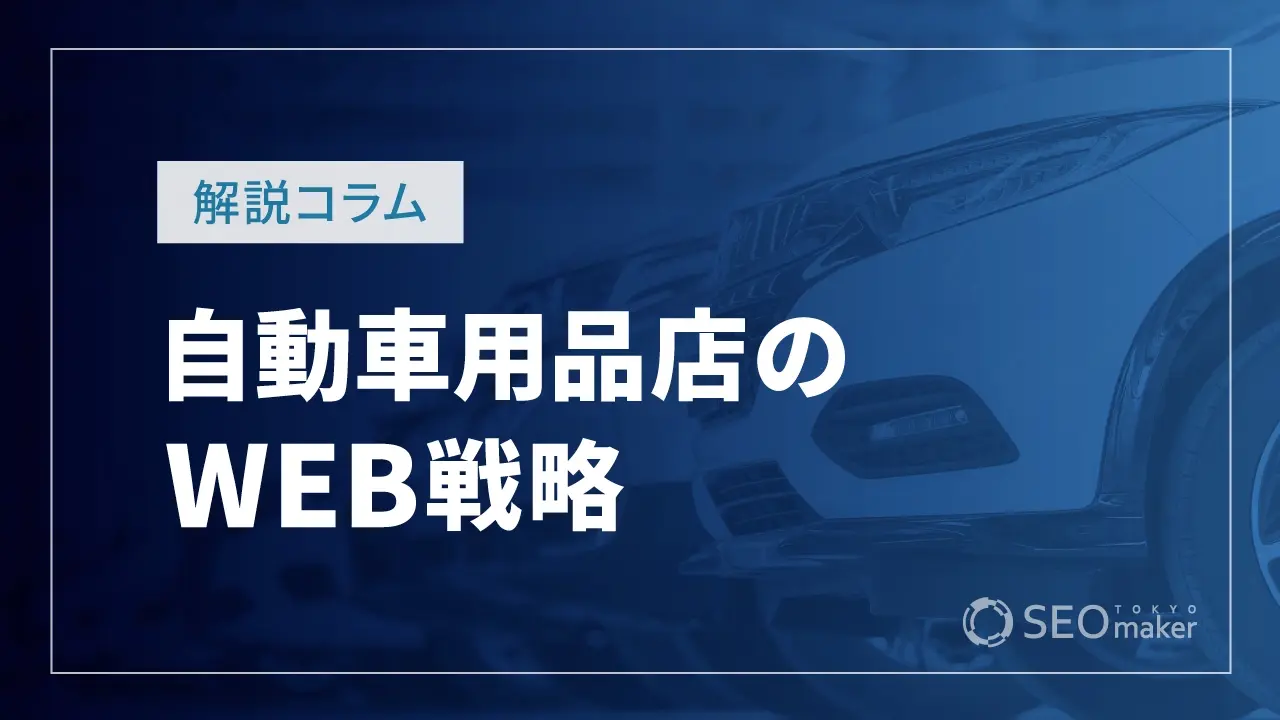schema.orgとは?構造化データのマークアップについてメリットデメリットを解説
 schema.orgは、Webページに構造化データを加える際に使用される標準語彙のセットです。検索エンジンにコンテンツの意味を正確に伝え、検索結果に「リッチリザルト」として表示される可能性を高めることができます。
schema.orgは、Webページに構造化データを加える際に使用される標準語彙のセットです。検索エンジンにコンテンツの意味を正確に伝え、検索結果に「リッチリザルト」として表示される可能性を高めることができます。
 この記事では、schema.orgの基本から、実装手法・メリット・デメリット・SEOへの影響まで、初心者でも理解できるように体系的に解説します。
この記事では、schema.orgの基本から、実装手法・メリット・デメリット・SEOへの影響まで、初心者でも理解できるように体系的に解説します。
schema.orgとは
schema.org(スキーマ・ドット・オルグ) とは、Google、Microsoft、Yahoo!、Yandex など複数の検索エンジンが共同で策定した、Webページ上の構造化データを記述するための共通語彙(ボキャブラリー) を定めたプロジェクトおよびその仕様です。
Webページの内容(商品・レビュー・企業情報・イベントなど)を、検索エンジンに正確に伝えるための「標準フォーマット」として使用されます。
構造化データのマークアップとは、コンテンツの内容を検索エンジンにより正確に理解してもらうためのコードを記述を指し、構造化データとして正確に認識されることを目的としています。構造化データの記述は共通仕様となります。
コンテンツ作成者は、定義された構造を使ってマークアップを行うことで、GoogleやYahoo!、Microsoftの検索エンジンで検索結果に詳細情報を表示しやすくすることが可能です。
さらに、検索エンジン側はより精度の高い結果を提供でき、ユーザーは必要な情報をスムーズに見つけられるというメリットがあります。
参照:schema.org
仕組み
仕組みは、Webページに含まれる情報を標準化された形式で整理し、構造化データとして内容を分類します。例えば、レシピページであれば、材料や調理時間、温度などを明確に定義するためのデータ形式を指します。
人間は文脈から情報を理解することは可能ですが、検索エンジンは、テキストをそのままの文字列としてしか捉えられません。構造化データを使うことで、ページの意味を検索エンジンに正確に伝え、理解を助けることが可能です。
schema.org以外の構造化マークアップの種類
schema.org以外のマークアップの種類については、以下の3つが挙げられます。
- JSON-LD
- microdata
- RDFa
それぞれの種類について解説していきます。
JSON-LD
JSON-LDとは、構造化データを記述するために利用されるフォーマットの一種で、JSON形式をベースにしたシンプルなデータ形式です。このフォーマットは、Linked Data(連携データ)の表現を目的としており、データを統一的かつ効率的に管理する手段として広く活用されています。
構造化データの記述方法にはさまざまな種類がありますが、その中でもJSON-LDはグーグルが推奨する形式であり、多くの場面で採用されています。JSON-LDは「“キー”:”値”」という基本的な構造でデータを定義し、特定のキーに対応する値を設定する形式が特徴です。この形式により、コンピュータはデータを効率的に処理することができ、Microdataなどと比べて優れた可読性を実現しています。
通常、JSON-LDはHTML内のどこに記述しても機能しますが、多くの場合、headタグ内に記述されることが一般的です。また、他の構造化データ記述方法と比較した場合、以下のような利点があります。
- HTMLソースに直接影響を与えないため、柔軟性が高い。
- Dataを一か所に集約できるため、管理や理解が容易である。
- 必要な記述が簡潔で、効率的にDataを表現できる。
一方で、HTMLの内容を更新した際には、JSON-LD側のデータも適切に修正する必要があります。これを怠ると、HTMLとJSON-LDの間で情報が不一致となり、データの整合性が失われるリスクがあるため、メンテナンスが重要となります。
microdata
Microdataは、HTML5で導入された手法で、W3Cが仕様を標準化しました。Microdataを含む複数の構造化データフォーマットで使用できる語彙を提供しており、多くのWebサイトで広く使用されています。
HTMLのタグや属性を使用して情報を記述するため、構造化データとHTMLの内容が整合しやすいというメリットがあります。しかし、HTML属性が増えることで、ソースコードが複雑になりがちで、保守や修正に手間がかかるというデメリットもあります。
RDFa
RDFaは、HTMLやXMLなどの文書にRDF(Resource Description Framework)を埋め込むための手法として開発されました。また、仕様が複雑なため、より簡単でMicrodataに近い形に簡素化されたRDFa Liteがあります。
RDFa LiteはXHTMLでも使用可能ですが、現在ではHTML5の普及に伴い、RDFa Liteの採用は減少傾向にあります。さらに、後述するマークアップ支援ツールでも、RDFa Liteは広くサポートされていない状況なのも事実です。
参考:トップPage|RDFa
schema.orgで構造化データのマークアップを行うメリット
Markupを行うメリットとして、以下の3つが挙げられます。
- Rich Snippets(リッチスニペット)に表示されやすくなる
- パンくずリストが表示できる
- Contentsの情報を認識してもらいやすくなる
それぞれのメリットについて解説していきます。
Rich Snippetsに表示されやすくなる
通常、検索エンジンの結果ページには、ページのタイトルと、その要約がテキスト形式で表示されますが、Rich Snippetsはより視覚的にわかりやすく表示させることができます。
例えば、求人情報の場合は、会社の所在地や時給、勤務時間といった詳細が、Rich Snippetsに含まれます。また、レシピサイトでは料理の写真、材料、調理時間などが見やすく表示されることによって、ユーザーは欲しい情報を素早く判断できるようになります。
このように、自社サイトがRich Snippetsとして検索結果に表示されれば、ビジュアル面での訴求力が高まり、ユーザーの目に留まりやすくなり、高い集客効果が期待できます。
関連記事:Rich Result(Rich Snippets)とは? 構造化Dataの書き方をご紹介
パンくずリストが表示できる
パンくずリストが表示されることで、検索エンジンのクローラーがより効率的にWebサイトを解析できるようになります。パンくずリストとは、ユーザーが訪問しているWebサイト内で、自分の現在位置を簡単に把握できるようにするための、リンク構造のことを指します。
通常、Webページの上部に配置され、左から右へと進む形で、階層が深くなる仕組みが一般的です。また、ユーザーにとっても利便性が向上します。現在閲覧しているページが、サイト全体のどの部分に位置しているのかが一目でわかるため、別のページやトップページに簡単に移動することが可能です。
このように、パンくずリストの設置によって、Siteの使いやすさが向上し、結果としてユーザーに好印象を与えることができます。
Contentsの情報を認識してもらいやすくなる
文章や単語にタグを付けて、その意味を明確にし、検索エンジンが認識しやすくなります。例えば、所在地に関する情報には「address」、商品に関する情報には「product」などが挙げられます。
定めた語彙を利用して、タグを付けることで、テキストの意味をより明確に、検索エンジンに伝えることができるようになり、検索結果に反映されやすくなります。
schema.orgで構造化データのマークアップを行うデメリット
Markupを行うデメリットについては、以下の2つが挙げられます。
- 専門的な知識や技術が必要になる
- Rich Resultに表示されない場合もある
それぞれのデメリットについて解説していきます。
専門的な知識や技術が必要になる
マークアップを行うには、一定の専門知識や技術が求められるため、初心者にはハードルが高いというデメリットがあります。構造化データを適切にマークアップするためには、書き方を理解し、使いこなす必要があります。
また、構造化データのマークアップを補助するツールも利用できますが、それを活用するにも基礎的な知識がないと、正確に設定できているか確認するのが難しいのも事実です。
結果として、専門知識や技術が不足している場合、予想以上に作業に時間がかかる可能性があるので注意が必要です。
Rich Resultに表示されない場合もある
構造化データを設定しても、必ずしもその内容がRich Resultとして検索結果にそのまま反映されるとは限りません。また、構造化データを正しく導入するためには、社内にその分野に精通したスタッフが必要であり、設定には一定の作業量が伴います。
このように、労力をかけて導入したにもかかわらず、期待していたような検索流入が得られないケースもあるので、事前に費用対効果を十分に検討することが重要です。
schema.orgのSEOへの影響や効果
SEOへの影響や効果については、以下の2つが挙げられます。
- 検索画面に構造化データを表示可能
- サイトへの評価を高められる
それぞれの項目について解説していきます。
検索画面に構造化データを表示可能
検索結果に表示される情報量が増え、ユーザーが内容に興味を持ちやすくなるため、クリック率の向上が期待できます。
構造化データを適切にマークアップすれば、検索結果ページにタイトルやメタディスクリプション以外にも、詳細な情報を表示できる可能性があります。
また、検索結果で表示される追加情報は「Rich Result」と呼ばれ、よくある質問(FAQ)や商品に関するデータなど、ユーザーのニーズに応じた内容を含むことができます。これによって、ユーザーの目を引きやすくなり、クリック率の向上も期待できます。
サイトへの評価を高められる
グーグルクローラーが、サイト内の情報を正確に把握できるようになり、その結果としてサイトの評価が向上し、SEO対策に効果をもたらす可能性があります。実際、構造化データを導入することで、検索エンジンは、ページ内のコンテンツの意味をより深く理解しやすくなり、サイトの内容が適切に認識されやすくなります。
また、検索エンジンが、そのコンテンツを価値あるものと評価すれば、SEOにおいても良好な影響を与え、検索結果での順位が上がることが期待できます。
schema.orgの実装方法
実装方法については、以下の3つが挙げられます。
- HTML上にマークアップ
- 構造化データ マークアップ支援ツール
- データハイライター
それぞれの実装方法について解説していきます。
HTMLにマークアップ
HTMLにマークアップする実装方法は、必要な情報を直接HTMLファイルに組み込むことを指します。具体的には、HTML内に、手動で構造化データを追加するアプローチで、細かい設定が可能なので、schema.orgの概念やマークアップのルールを、正しく理解して適切に記述することが求められます。
特にマークアップの正確さが重視される場面で効果的です。グーグルのサポート資料を参考にしながら、適切な箇所に構造化データを配置することが推奨されています。しかし、扱うコンテンツの量に応じて、記述に時間がかかる場合があります。
構造化データマークアップ支援ツール
実装方法として、Googleが提供する支援ツールを活用することができます。このツールを使用すれば、仕様や記述ルールが不明確な場合でも、ガイダンスに従うことで比較的簡単に設定できます。
HTMLに直接マークアップを追加する場合と比べて、作業の効率を高めることができます。ただし、一部のツールはGoogleアカウントでのログインが必要ですが、必ずしもサーチコンソールとの連携は前提ではありません。
参照:Search Consoleヘルプ|構造化DataMarkup支援ツール
データハイライター
データハイライターとは、Googleが無料で提供しているサービスの一つです。Googleアカウントでログインすれば利用可能です。必ずしも、サーチコンソールとウェブサイトを連携させる必要はありません。
データハイライターは、前述の2つの方法と比較して構造化できる情報の範囲が限られていますが、タグ付けしたい部分をクリックしてDataを選び、簡単にMarkupを行うことができるのが特徴です。
参照:Search Consoleヘルプ|データハイライターについて
構造化タグの種類
schema.orgを活用するためには、構造化タグの種類を把握しておくことが重要です。主要な構造化タグについては以下を参考にしてください。
| 構造化タグの種類 | 内容 |
| <section> | 文章をテーマごとに区切ったセクションであることを示します。1つのセクションには、見出し、本文、そして補足的な情報が含まれることが一般的です。 |
| <article> | 独立した記事やContentsを表現するために使われるタグです。ブログでは記事全体、ニュースSiteでは各ニュースがこれに該当し、個々の独立したContentsとして扱われます。 |
| <aside> | 補足的な情報を示すためのタグで、本文の内容に関連しつつも、独立して記載されるべき情報が含まれます。サイドバーなど、本文とは直接関連しない部分にも用いられることがあります。 |
| <nav> | ナビゲーションのために使われるタグで、Site内の主要なPageへのリンクをまとめて表示します。例えば、グローバルナビゲーションやパンくずリストに使われることが多いです。 |
| <header> | Pageのヘッダー部分を示すタグで、通常はPageの冒頭にあり、導入やナビゲーションの補助として機能します。 |
| <footer> | Pageのフッター部分を示すタグです。ここには著者情報や著作権表記、関連する文書やリンクが含まれることが多いです。 |
これらのタグを正しく使うことで、検索エンジンに対してページの内容を明確に伝えられるようになり、SEOにも良い影響を与える可能性があります。
特に、ユーザーにとって価値のある情報を整理しやすくするための重要なツールとなり、サイト全体のコンテンツ品質を高める土台を築くことができます。
このように、構造化タグを正確に使うことは、Webサイトの情報を効率的に整理し、検索エンジンでの視認性を高めるために不可欠と言えます。
しかし、誤った使い方をすると、検索エンジンに誤解を与える恐れがあるため、適切に扱うように留意することが大切です。
構造化データの検証方法
構造化データの検証方法については、以下の2つが挙げられます。
- 構造化データテストツール
- サーチコンソール
それぞれの方法について解説していきます。
構造化データテストツール
構造化データテストツールは、以前Googleが提供していたツールでしたが、現在は Schema Markup Validator に置き換えられています。このツールでは、シンプルな操作で簡単にデータテストを行うことができます。
まず、Schema Markup Validator のPageにアクセスし、調査したいURLを入力します。その後、「RUN TEST」を押すことで解析を始めることができます。
また、本番サイトではなく、テスト用のページやURLが存在しない場合は、「Codeスニペット」のタブに切り替え、解析したいHTMLを直接入力することも可能です。テストが完了したら、ツールの右側に表示される結果を確認し、データが正しく反映されているか確認することが大切です。
サーチコンソール
Google Search Consoleでは、構造化データの設定が、正しく行われているかどうかを確認することができます。
従来の構造化データテストツール(現在はSchema Markup Validatorに置き換えられています)では、1つのURLやHTMLしか検証することができませんでしたが、Google Search Consoleでは、サイト全体の構造化データの状況を、一覧で把握することが可能です。
操作方法については、サーチコンソールにログインした後、「検索での見え方」メニューから「構造化データ」を選択すれば、サイト内のデータを簡単にチェックすることができます。
エラーが発生した場合や、サイトの内容を更新したときには、サーチコンソールで状態を確認するのがおすすめです。
また、構造化データの設定ミスが、直接検索順位に影響を与えることはありません。しかし、検索エンジンに正確な情報を提供するため、エラーのない状態を維持することが大切なので、定期的な確認とメンテナンスを行うことが大切です。
参照:Search Consoleヘルプ|Search Consoleの概要
schema.orgで構造化マークアップができない原因
Markupができない原因については、以下の3つが挙げられます。
- Codeが正しく記述されていない
- コンテンツのクオリティが低い
- グーグルのガイドラインに違反している
それぞれの原因について解説していきます。
Codeが正しく記述されていない
Codeが正しく記述されていないと、期待しているSEO効果が得られないだけでなく、場合によってはWebサイト全体のレイアウトが崩れるリスクもあるため、正確に記述することが重要です。
Codeが適切に記述されているかどうかは、以下の3つのツールを使って確認することができます。
- 構造化Dataテストツール
- Rich Resultテスト
- グーグルサーチコンソール
構造化データテストツールとRich Resultテストは、確認したいWebページのURLを入力するだけで簡単にチェックできますが、1ページずつしか確認できないので、大量のページを一度に確認する場合は手間がかかることもあります。
一方、Google Search Consoleでは、サイト全体を対象にエラーチェックが可能で、全体の設定に問題がないかを確認することが可能です。このツールを活用して、まずは自分のサイトに使用しているマークアップの状態を確認し、必要に応じて修正を行います。
コンテンツのクオリティが低い
コンテンツの質が低いと、Rich Snippetsが正しく表示されないことがあります。もし正しいCodeを実装し、ガイドラインに従って設定しているにもかかわらず、問題が生じているなら、コンテンツの質を再評価することが重要です。
実際に、コンテンツSEOで最も重要とされている要素は、コンテンツの質です。読みやすさや理解しやすさだけではなく、情報が正確であることや、幅広くカバーされているかどうかなどユーザーにとって、役立つ内容であるかがポイントになります。
このように、コンテンツのクオリティを高めるには、ユーザーがコンテンツを読むことで、価値を感じられるかどうかが重要です。
グーグルのガイドラインに違反している
マークアップができない理由の一つとして、Googleのガイドラインに違反している可能性があります。たとえ意図していなくても、Googleが「ガイドラインに違反している」と判断すると、Rich Snippetsに表示されなくなることがあります。
そのため、構造化データを導入する際は、事前にGoogleのガイドラインをしっかり確認することが重要です。
構造化マークアップを導入する際の注意点
Markup(マークアップ)を導入する際の注意点については、以下の3つが挙げられます。
- SEO対策の効果が低い
- Webサイトへの流入が減るリスクがある
- 基本的な知識が必要になる
それぞれの注意点について解説していきます。
SEO対策の効果が低い
マークアップを導入する際の注意点の一つとして、SEO対策の効果が限定的であることが挙げられます。マークアップを使用することで、検索エンジンが正確に情報を理解する手助けにはなりますが、それだけでは検索結果の順位が大きく向上するわけではありません。
SEOに直接的な効果をもたらす施策ではないので、SEOを強化したい場合は、他のアプローチを検討するほうが良いケースもあります。
他の手法と比較し、それぞれのメリットやデメリットを十分に評価したうえで、導入するかどうかを慎重に判断することが重要です。
Webサイトへの流入が減るリスクがある
マークアップを実装し、Rich Snippetsに情報が表示されると、Webサイトへの流入が減少するリスクがあります。
理由として、検索結果ページに、ユーザーが求める詳細な情報が表示されるので、ユーザーがその情報だけで満足し、サイト自体にアクセスする必要がなくなる場合があるからです。
特にFAQ Pageのようなコンテンツでは、Rich Snippetsに質問と、その回答が表示されてしまうので、ユーザーはその情報で十分だと感じてしまい、わざわざサイトを訪れることが少なくなることがあります。
しかし、Rich Snippetsによってユーザーの興味を引き、さらに詳しい情報を求めて、アクセスしてもらえる場合もあります。
schema.orgのよくある質問
よくある質問については、以下の3つが挙げられます。
- schema.orgとは
- 構造化Data Markupとは
- 構造化MarkupはSEOにどのような効果がある
それぞれのよくある質問について解説していきます。
Q:schema.orgとは
A:マークアップの基準を策定し、管理している共同プロジェクトです。マークアップの標準仕様を提供しており、Webサイトがこの仕様に沿ってマークアップを行うことで、検索エンジンはサイトの内容をより正確に把握できるようになります。また、情報をRich SnippetsやRich Resultといった形で、より分かりやすく表示することが可能になります。
Q:構造化データマークアップとは
A:構造化データマークアップとは、グーグルの検索エンジンが、ウェブページ上のテキスト情報を効果的に理解できるよう、HTML内で特定のタグを使用して情報を構造的に記述する手法です。検索エンジンが構造化データを必要とする理由は、検索エンジン自体が自然な言葉の意味をそのまま解釈することができないからです。
例えば、構造化データを通じて「これは会社名です」や、「これは人物名です」といったように、テキストが持つ意味を機械的に伝える役割を果たします。このように、構造化データを適切に配置することで、クローラーがそのページの情報をより正確に理解し、検索結果に反映させることが可能になります。
Q:構造化マークアップはSEOにどのような効果がある?
A:構造化Markup自体には、直接的にSEOの順位を向上させる効果は期待できません。しかし、Markupを施すことで、検索engineのクローラーがPageをより理解しやすくなり、結果として情報が正確にインデックスされる可能性が高まります。実際に、Markupを施していないPageと比較すると、グーグルの評価が高くなる傾向があります。
さらに、Rich Resultが検索結果に表示されることで、ユーザーの目を引きやすくなり、アクセス数が増加することが期待されます。特に、質の高いContentsは、ユーザーによって共有されたり、他のSiteからの被リンクを得ることができ、さらなるトラフィックの増加につながります。
まとめ
 schema.orgを活用した構造化データのマークアップは、検索エンジンにページの内容をより正確に伝えるための強力な手段です。特にリッチリザルトの表示によって、クリック率(CTR)の向上やユーザー体験の向上が期待できます。ただし、実装には一定の技術的知識が求められ、すぐにSEO順位が上がるわけではありません。正確な記述とGoogleガイドラインの順守が不可欠です。導入後は、テストツールやSearch Consoleでエラーを定期的にチェックし、継続的なメンテナンスを行いましょう。技術と運用を両立させることで、schema.orgの効果を最大限に引き出すことができます。
schema.orgを活用した構造化データのマークアップは、検索エンジンにページの内容をより正確に伝えるための強力な手段です。特にリッチリザルトの表示によって、クリック率(CTR)の向上やユーザー体験の向上が期待できます。ただし、実装には一定の技術的知識が求められ、すぐにSEO順位が上がるわけではありません。正確な記述とGoogleガイドラインの順守が不可欠です。導入後は、テストツールやSearch Consoleでエラーを定期的にチェックし、継続的なメンテナンスを行いましょう。技術と運用を両立させることで、schema.orgの効果を最大限に引き出すことができます。