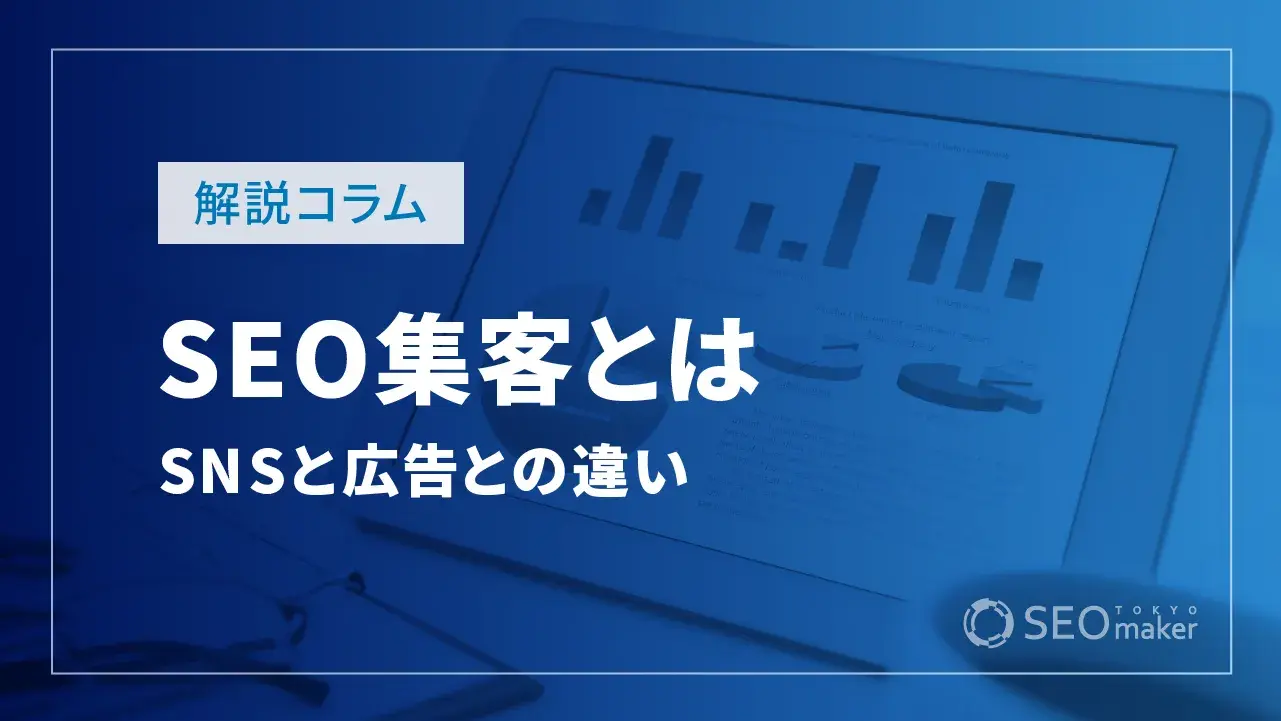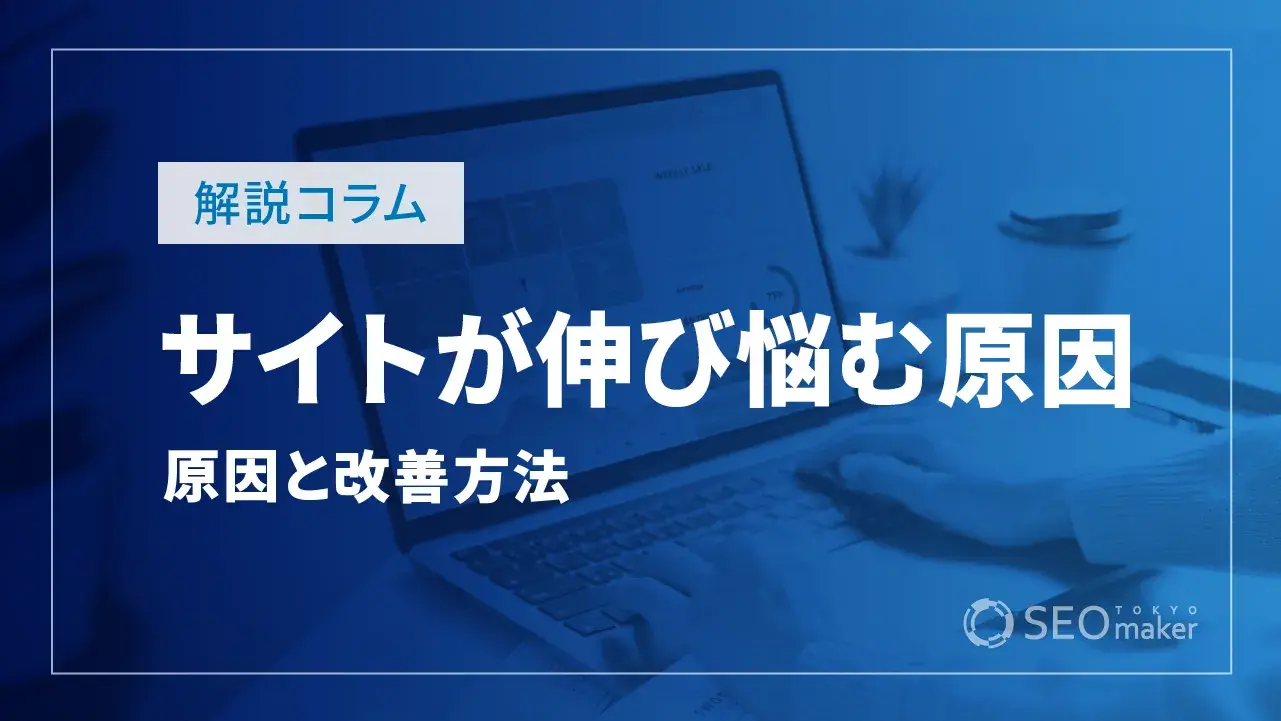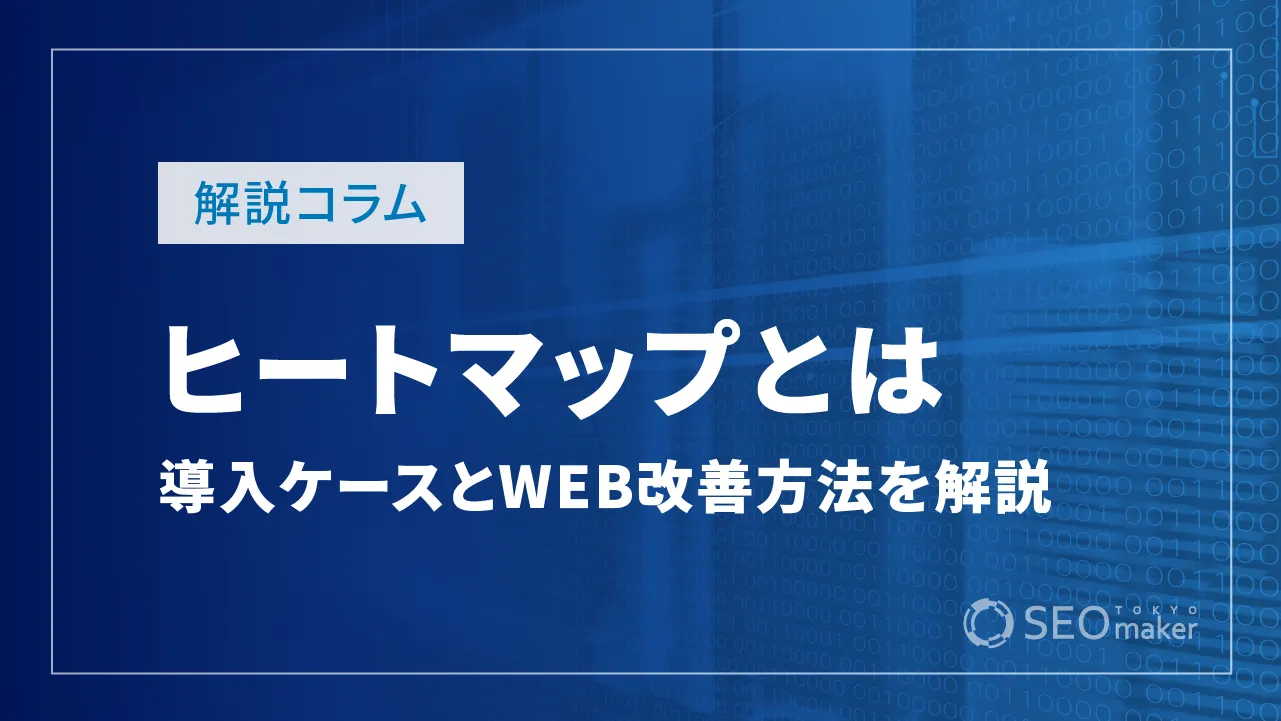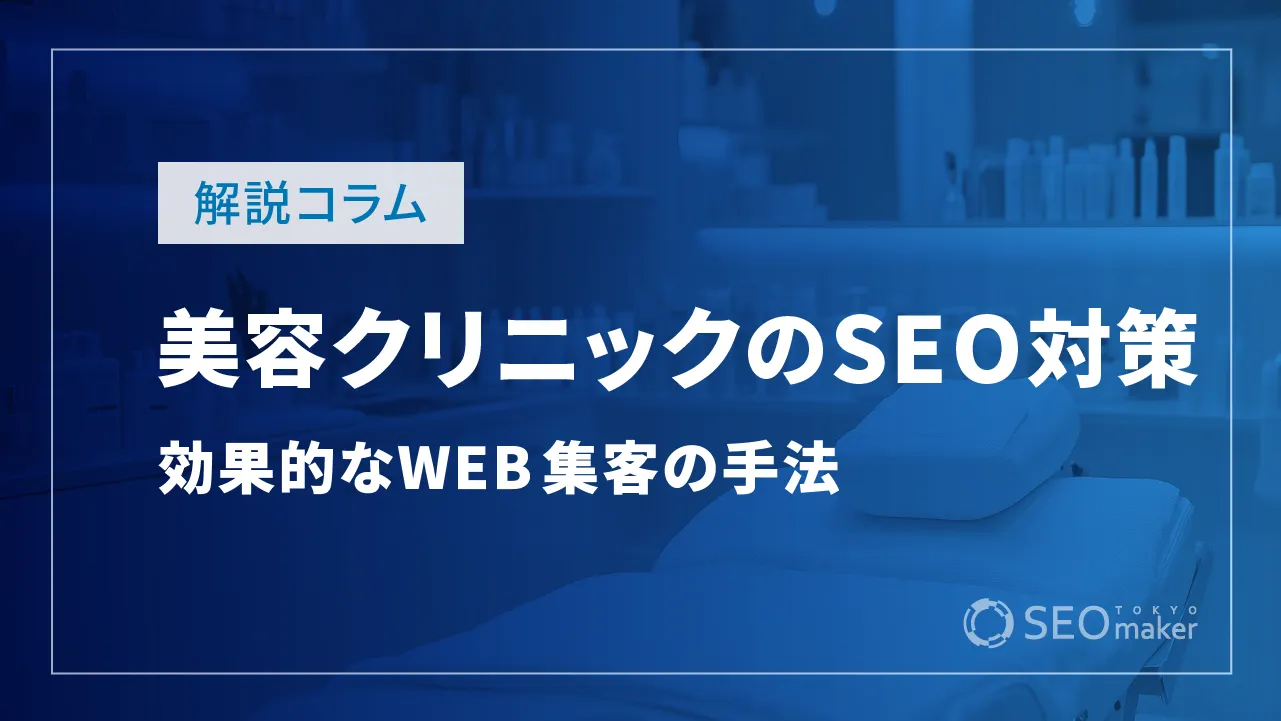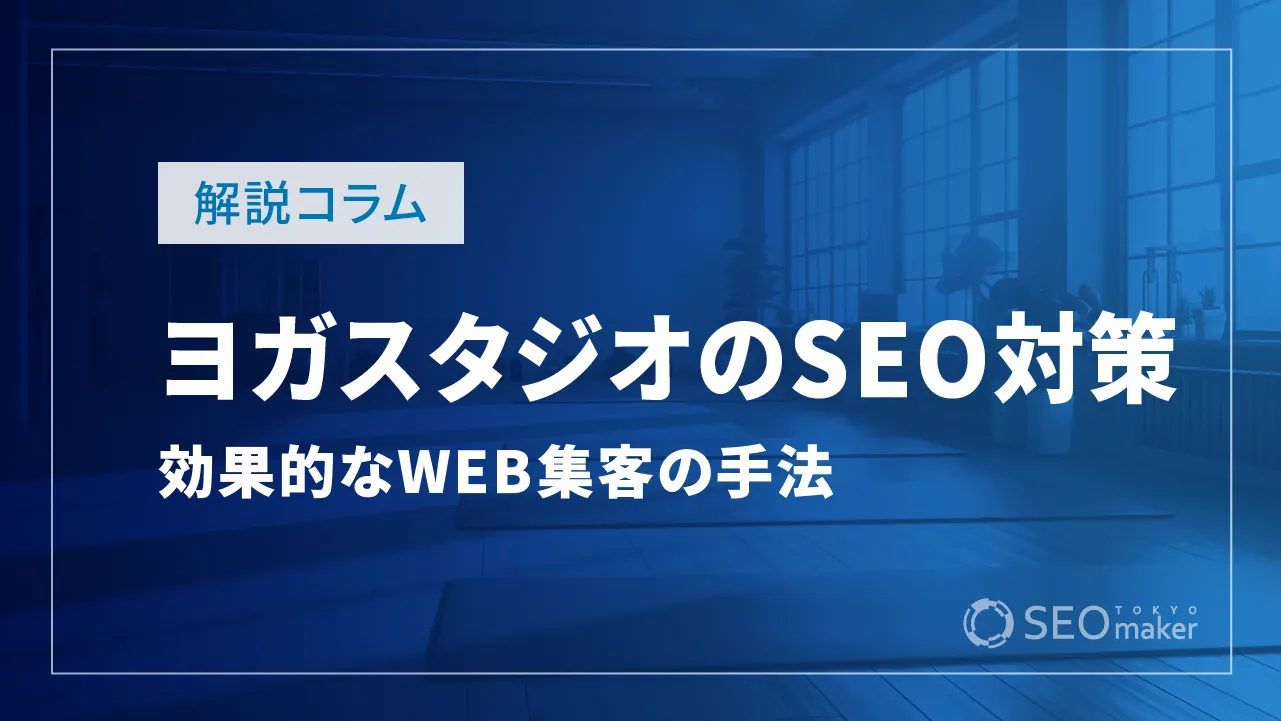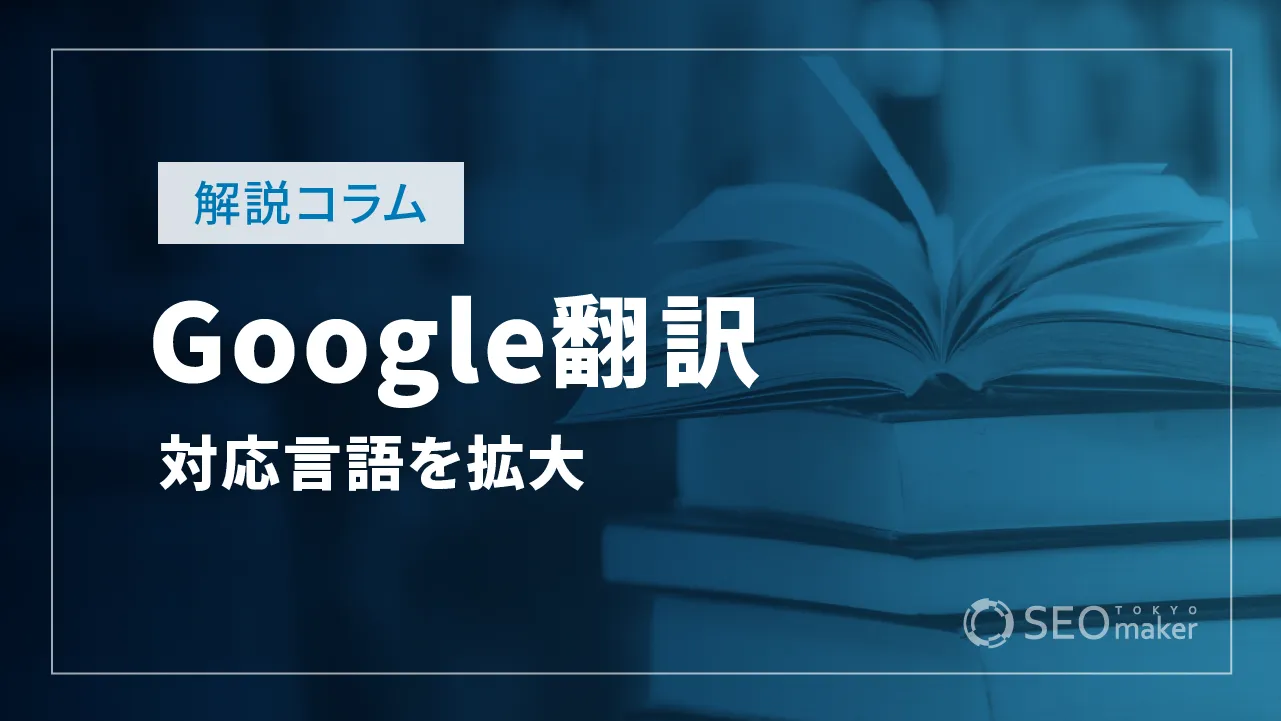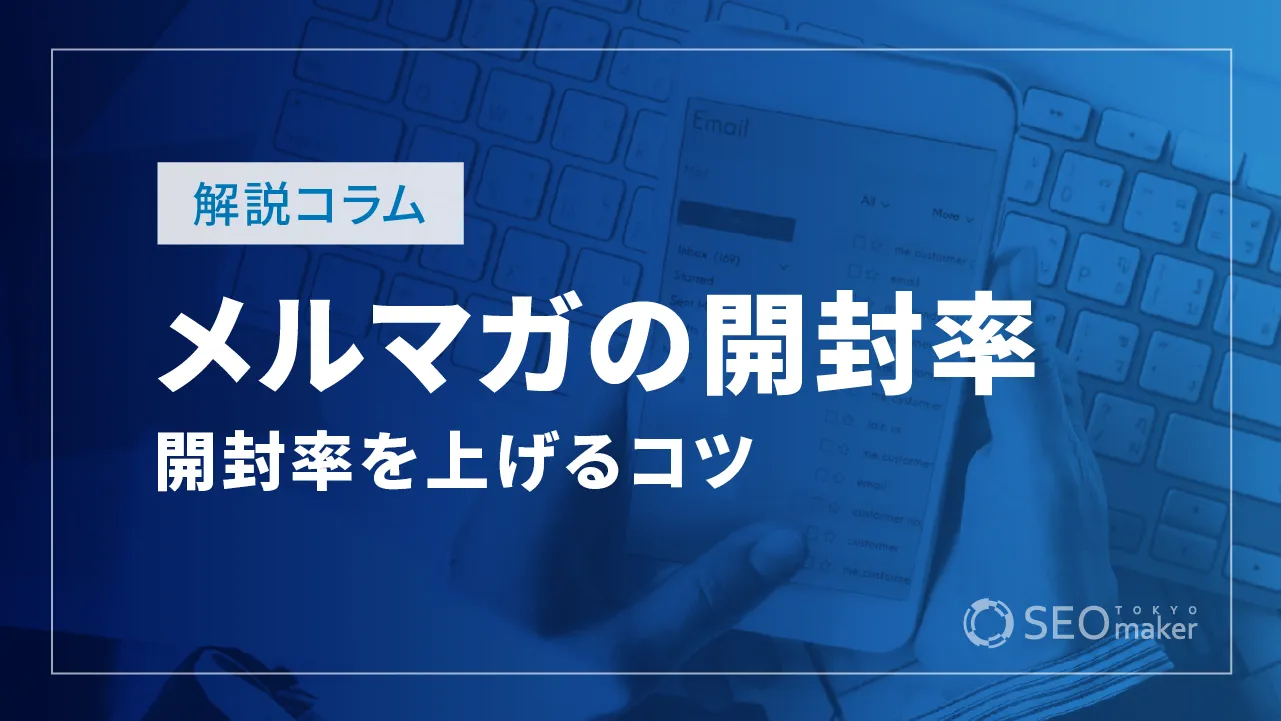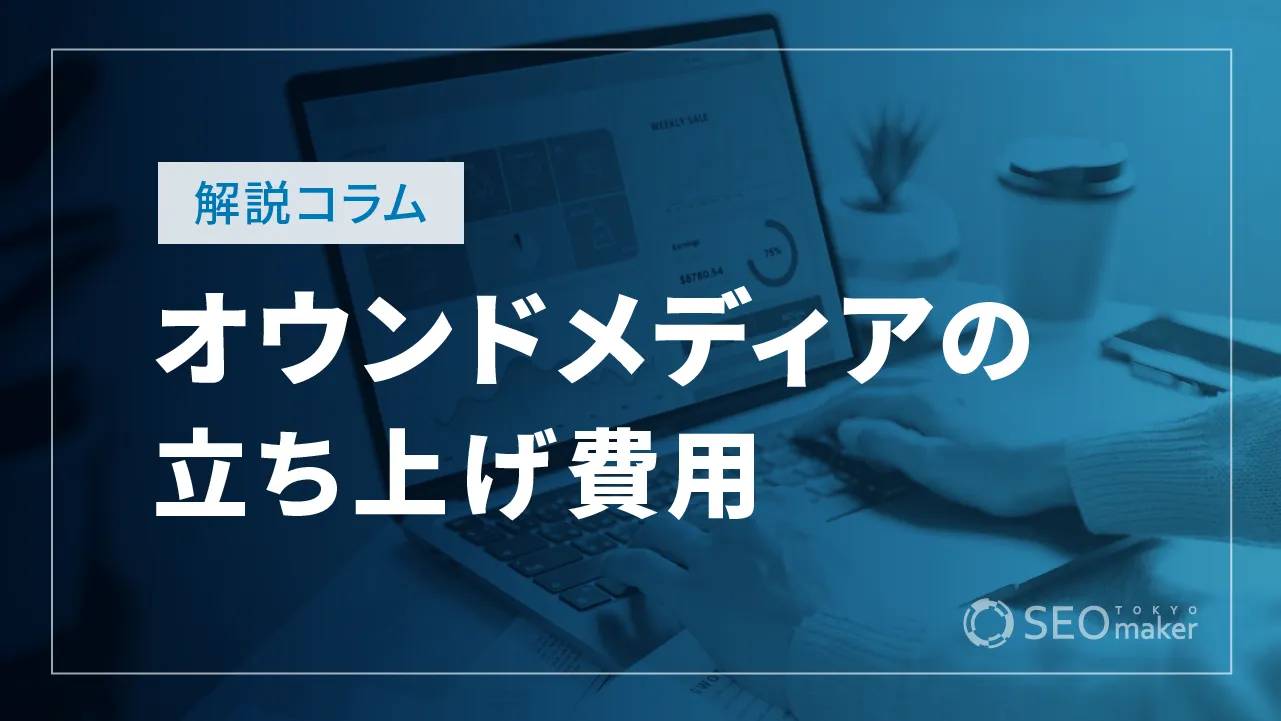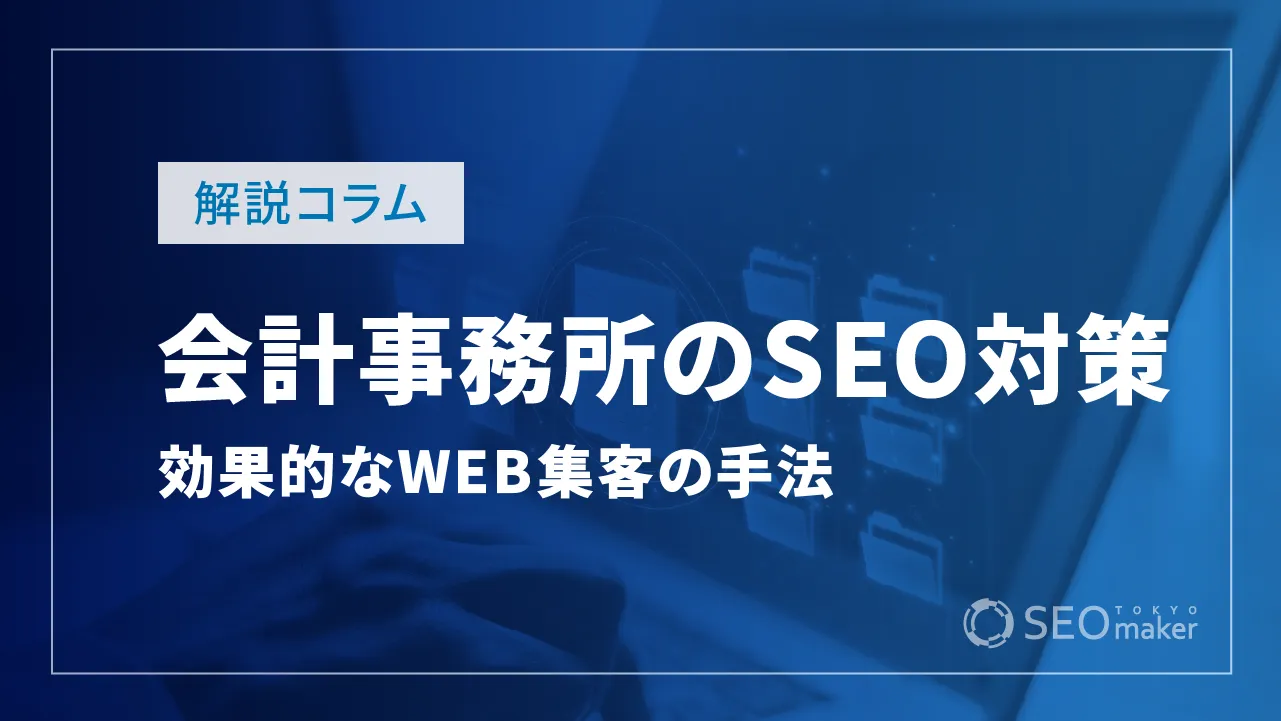SEO対策で効果が絶大だった施策ベスト50<100のサイトで検証>

自分でSEO対策をやろうと思っても何から手をつければよいのか困ってはいませんか。企業のWEB担当者であれば、SEO業者に色々話を聞いて、優先順位を決めて取り組んでいることと思います。そこで、今回は、SEO専門会社である弊社の研究結果において、効果が非常に高かったSEOの施策を優先順位をつけて50個紹介します。
 弊社では、最新のGoogleアルゴリズムの研究を日々行っており、たくさんのサイトで検証を繰り返しています。2024年では、100のWEBサイトで実験と検証を行ってきました。50の施策については、上から順に、優先順位が高いものです。1~14の施策は、大きなランキング上昇が確認できた施策ですのでSEO対策をすると決めたら必ず修正してください。個々の正しい修正ができない方は、是非、東京SEOメーカー迄ご相談ください。では、ご紹介します。
弊社では、最新のGoogleアルゴリズムの研究を日々行っており、たくさんのサイトで検証を繰り返しています。2024年では、100のWEBサイトで実験と検証を行ってきました。50の施策については、上から順に、優先順位が高いものです。1~14の施策は、大きなランキング上昇が確認できた施策ですのでSEO対策をすると決めたら必ず修正してください。個々の正しい修正ができない方は、是非、東京SEOメーカー迄ご相談ください。では、ご紹介します。- 26.ユーザビリティを考慮してサイト導線の設計をやり直した
- 27.スマホサイトをモバイルフレンドリー化した
- 28.内部リンクのアンカーテキストを最適化した
- 29.URLの正規化をした
- 30.グローバルナビゲーションを10個から5個にした
- 31.Canonical設定をした
- 32.パンくずリストを追加した
- 33.ページネーションを設定した
- 34.コンテンツ要素が似ているページを統合した
- 35.古いページを廃止して新しいページを作り、リダイレクトした
- 36.構造化データをページに設置した
- 37.FAQページを増設した
- 38.XMLサイトマップを設置した
- 39.サイトの階層を3階層までにした
- 40. サイト内検索を実装した
- 41.競合他社の記事を調べて足りない記事を追加した
- 42.記事に画像や図を追加した
- 43.タグ検索を実装した
- 44.記事に独自性の高い要素を追加してリライトした
- 45.記事の更新日を最新のものにした
- 46.記事のリード文をユーザーが魅力的に感じるように修正した
- 47.記事に目次を追加した
- 48.プレスリリースを出した
- 49.リンク営業が来たので対応した
- 50. Xにサイトの記事を投稿した
80%以上のサイトでランキング上昇が確認できた施策
1.タイトルの変更
TOPページに対策キーワードを内包したタイトルを作成し、下層ページもキーワード最適化したタイトルを設定。100サイトすべてに対策キーワードでのランキング上昇がみられました。
2.メタディスクリプションの作成
タイトルと違った言い回しで対策ワードの類義語、共起語などを利用して文章を作成したところ、インデックス数が増え、サイト全体のランキング上昇に貢献しました。できるだけ狙っているキーワードを自然な形で入れました。
3.ページコンテンツの見直し・リッチ化
1000文字程度だったページを5000文字までコンテンツをリッチ化したところ、ランキング上昇が大幅にみられました。文字数が少なく、インデックスしていなかったページも文字数を増やしたところ、インデックスしました。
4.内部リンクの構築
各下層ページよりTOPページへ内部リンクを構築したところ、ほとんどのサイトで全体のランキング上昇が確認されました。また、関連記事同士も内部リンクでつなぎました。
5.監修者の追記
コラム記事に監修者を追記したところ、インデックスするページが大幅に増えました。EEATのEの専門性にかかわる領域ですが、特にYMYLの領域のサイトは監修者を追加すると目に見えて効果が現れました。
6.TOPデザインの改善
TOPページのUIを改善したところ、ランキング上昇がみられました。特に、一昔前のデザインや古いと感じるデザインは、最新のデザインにすると大幅に順位アップが見られました。
7.コンテンツ内のキャッチと文章の見直し
各ページのキャッチと文章をコピーライターにより修正、改善したところ、ランキングが上昇しました。特に、キャッチ部分を修正したところ多くのサイトで順位上昇がみられました。
8.各ページのコピペ率を下げた
コピペ率が高かったサイトのみピックアップして、各ページのコピペ率を30%以下にしたところ、全体のランキング上昇がみられました。ミラーページ、重複ページは評価を下げると言われているので、実際に修正対応したところ、ほとんどのサイトで好影響が出ました。
9.SSL化(https)
明らかに順位が変わりました。ほとんどのサイトはSSL化していましたが、いくつかのサイトでSSL化していませんでした。SSL化してないサイトが上位にランクインすることはほぼないに等しいと言えるようです。
10.外部リンクを獲得した
外部リンクをプレスリリースや相互リンク、広告掲載、リンク営業で増やしたところ、全体的なキーワードランキング上昇がみられました。ビックワードになればなるほど外部リンクの影響が強く出ています。月間検索件数が低く、難易度が低いキーワードは、コンテンツの質さえよければ上位表示しますが、難易度の高い検索件数の多いビックワードは外部リンクの獲得が必要のようです。
11.トピッククラスター化
ビックワードを狙うピラーページとクラスターコンテンツを親子にしてトピッククラスターモデルを構築しました。ディレクトリ構造の修正も合わせてすることで大きな効果が確認できました。これは、インデックス数が1000以上あるWEBサイトやメディア、大規模サイトで顕著に好影響が出ました。サイトが大きくなればなるほど、トピッククラスターが必要になります。
12.ディレクトリ構造の最適化
トピッククラスターとともに、ピラーページとクラスターコンテンツを親子のディレクトリにして内部リンクを構築したことにより、ユニットでGoogleに評価され、ビックワードで狙ったピラーページのランキング上昇を確認しました。トピッククラスターとディレクトリ構造の最適化はセットで修正してください。
13.ピラーページとクラスターページの内部リンクを最適化した
クラスターページとは、ピラーページ(ハブページ)を支えるサポート的なページです。メインワードの複合ワードや類似ワードで構築し、メインとなるピラーページに内部リンクを構築します。トピッククラスターとディレクトリ構造の最適化とともに内部リンクの構築をセットで対策することにより、大規模サイトでは、大きなランキング上昇が確認されました。
14.サイトのソースコードの不備の修正
HTML Living Standardに準拠していない箇所の修正を行ったところ、順位改善が見られました。特に、Footerタグがないサイトなど基本的なルールに沿って構築されていないサイトの場合、問題点を修正すると本来ランキングする順位に戻る傾向が大いに確認されました。
上記1~14の施策は、明らかにランキング上昇が確認できた施策ですので、最優先でSEO対策をしたい項目です。
施策をいくつか組み合わせてランキング上昇が確認できた施策
次に、サイト全体の品質を向上して、全体のサイトの平均ランキングを高めるための施策です。
15~25の施策は、1つだけ対策したところで大きな変化はありませんでしたが、いくつもの施策を着実に進めれば数ヵ月後大きな成果が表れたものです。これらの改善は、競争が激しくなるビックワードでの上位表示では必ず必要な修正です。基本的なSEO対策からミクロのSEO対策まで徐々にサイト品質を高めるために修正を進めていきます。
15.サイト表示スピードの改善
主に、画像をすべてwebpにして、サイト表示スピードを上げました。特に、画像が重くサイト表示スピードが著しく遅いサイトでは、画像の軽量化をするとサイト全体の順位が上がります。スマホでのランキング上昇がたくさん確認できました。
16.画像にALT属性を入れた
画像の説明を丁寧にしました。画像は、何も明記せずアップするのではなくて、ソースコードのalt部分にその画像の説明文を入れるようにします。
| <img src=”画像のURL” alt=”画像の説明”> |
alt属性を入れると、画像検索でよく引っかかるようになりました。
17.画像の名前を小文字ローマ字に修正した
なるべく短い名前で英語表記しました。また、画像サイトマップを送信しました。画像名で大きくランキング下降していると決定づけることはできませんでしたが、日本語文字などの長い画像名は、Googleも推奨してないので避けるようにしています。
18.リンク切れをなくした
404エラーをなくし、リンク先がなければそのリンクを削除しました。リンク切れが多いとサイト品質は落ちることは理解できますが、リンク切れのために大きくランキングが下がっていると決定づけることはできませんでした。しかし、ユーザーのことを考えてユーザビリティを優先しリンク切れをなくしました。
19.H1タグを設定し、タイトルと違う文言を入れた
H1タグは、固定の文言にして、タイトルと違った言い回しで同じ意味の文言に修正しました。検索結果にもH1の表記が現れることが多く、ランキングにも大きな影響があるように思えました。
20.サーバーを高速サーバーに変えた
サイト表示スピードがひどく遅かったサイトがありました。サーバーを高速サーバーに変更し、サイト表示スピードが遅い原因となる部分を修正して、page speed insight で合格ラインに引き上げたところ、スマホサイトで顕著にランキング上昇が確認されました。
21. URL(パーマリンク)を短い英単語に修正
日本語URLや長いURLを修正しました。そのページを要約する英単語にパーマリンクを修正しました。ランキング上昇したかどうかというよりも、検索表示一覧結果にきれいにURLが表記されるようになったり、インデックスしやすくなったりと好影響が出ました。
22.無駄な内部リンクを削除した
内部リンクをたくさんつけたほうが順位上昇するという間違った情報をうのみにし、無駄に内部リンクを大量に構築しているサイトがありました。ユーザーの導線やユーザビリティの観点から、必要のない内部リンクを削除して、必要最低限且つ有益な内部リンクだけを残したところ、サイト順位の上昇がみられました。
23.インデックスしないページを削除した
NO INDEXページが大量にあったサイトのインデックスしていないページをすべて削除しました。サイト全体の品質が上がり、SEOのランキングにおいても好影響が出ました。
24.動的URLを静的URLに変更した
データベース型SEOの商品一覧ページや店舗一覧ページの動的URLを静的URLに修正したところ、インデックスが良くなされてサイト全体のランクインページが増えました。
サイト全体のランキングポジションが向上しました。
25.各ページのテーマを1つに絞った
テーマがぶれているページやテーマを1つに絞れていないページがあったサイトを、全て1ページ1テーマにし、サイトテーマも1つに絞ってテーマ特化型サイトにしたところ、そのテーマで全体的にランキングが上がった。
ここまでの15~25の施策では、たいていのサイトで対策ワードのランクイン上昇ができました。よって、1~15の施策の後、次フェーズで15~25のSEO対策を進めてください。
余裕があればやっておきたい施策
残りの26~50は、サイトの品質を上げるための内部施策と外部の施策によりサイト評価を高めるものです。余力がある場合や競合と熾烈なランキング争いをしており少しでもサイト品質を高めてランキングアップを狙いたい場合、トライしてみてください。
26.ユーザビリティを考慮してサイト導線の設計をやり直した
ユーザーにとってわかりやすいボタン、クリック場所、コンテンツ要素の配置を修正、改善しました。サイト導線とサイト設計をやり直したところ、大幅に順位が上昇しました。
27.スマホサイトをモバイルフレンドリー化した
スマホサイトの文字を読みやすく修正しました。スマホのメニューを作り、レスポンシブデザインでサイトを構築しました。SEOランキング評価の検証はできませんでしたが、ユーザービリティが上がり問い合わせが増えました。
28.内部リンクのアンカーテキストを最適化した
サイト内内部リンクを構築するときに、リンク先ページのタイトルをリンク元のアンカーテキストに入れたところ、リンク先ページのタイトルキーワードでランキングが上がった。
29.URLの正規化をした
URLの正規化をしたところ、類似サイト、ミラーサイトのリスクがなくなった。
30.グローバルナビゲーションを10個から5個にした
グローバルナビゲーションが多すぎるとユーザーが混乱するので、5個程度に削除することによりサイトの品質が上がりました。その結果SEOのランキングが上がることはありませんでしたが、ユーザビリティの向上に寄与しました。
31.Canonical設定をした
類似ページ、重複ページが大量にあったサイトで、Canonical設定をしたところ、県外からランキングするまでの成果が出た。
32.パンくずリストを追加した
パンくずリストがないサイトにパンくずリストを追加しました。ユーザビリティが向上しましたが、大きくランキングが上がることはありませんでしたが、パンくずリストがないサイトで上位表示しているサイトはほとんどありません。
33.ページネーションを設定した
ページネーションとは、コラム記事などの一覧ページにおいて、2ページ目、3ページ目と遷移できる導線の部分を言います。リンク付きのページ番号が羅列した要素のところです。
ページネーションを追加することで直接的な検索上位表示やランキングへの影響は確認できませんでしたが、ユーザービリティの向上は期待されます。現在ではほとんどのメディアでは、ページネーションがあるので、必ず設置しておきましょう。
34.コンテンツ要素が似ているページを統合した
大量にコラム記事を作成していると、似た要素のコラムコンテンツが出てきます。インデックスしている2つの似通ったコラム記事を1つに統合したところ、統合ページのランキングが上がりました。この結果、2つの記事は、評価分散が起きていたと推測できました。
35.古いページを廃止して新しいページを作り、リダイレクトした
新しく対策キーワードに合致するコンテンツページを作成し、URLも新しくしました。古いURLから301リダイレクトをして新ページを公開したところ、以前よりも上位にランクインしました。
36.構造化データをページに設置した
構造化データは様々な種類がありますが、FAQページに構造化データを実装したところ、検索結果でリッチリザルト部分の表示が始まりました。
37.FAQページを増設した
FAQページを厚くして10ページ以上にした。トピッククラスター化して実装したところ、全体のランキングが上がりました。
38.XMLサイトマップを設置した
XMLサイトマップをGoogle Search Consoleより送信しました。その結果、インデックスが促され、インデックスページが増えて好影響が出ました。
39.サイトの階層を3階層までにした
7階層まであったサイトの階層をユーザーが使いやすいように3階層にしてサイト設計をやり直しました。インデックス数が増えて、SEOに好影響が出ました。
40. サイト内検索を実装した
サイト内検索を実装してユーザビリティを高めました。
41.競合他社の記事を調べて足りない記事を追加した
競合他社の対策キーワードと実装記事をSEMRUSH(セムラッシュ)で調べて、不足記事を実装していきました。自然検索からの流入が増えました。
42.記事に画像や図を追加した
コラム記事にサムネ画像と図を追加しました。コラム画像のサムネが画像検索で引っかかるようになりました。図を入れたことでページコンテンツの品質が上がり、ランキングが上がりました。
43.タグ検索を実装した
タグ検索を実装したところ、タグを含む投稿表示にページが表示されるようになりました。
44.記事に独自性の高い要素を追加してリライトした
記事のテーマに合わせて、独自の検証結果や見解を追加してコンテンツ要素を追加しました。その結果、ランキングが上がりましたが、入れるコンテンツ要素の信頼性が非常に大事です。また、その独自性のリソース元が正しいことが大前提です。
45.記事の更新日を最新のものにした
記事を更新して日付を最新のものにするとランキングが少し上がる傾向がみられました。特に古い更新日のものは、最新のものにすると効果がありました。
46.記事のリード文をユーザーが魅力的に感じるように修正した
記事のリード文が薄かったので、より具体的で尚且つ、記事が読みたくなるような文章に修正しました。その結果、離脱率が減り、ランキングも全体的に上がりました。
47.記事に目次を追加した
目次を各記事のタイトル、TOP画像、リード文の下に追加しました。
ユーザービリティの向上に寄与しました。ランキング向上したかどうかは不明ですが、上位表示している記事枠のメディアは、ほとんど目次があるので必ず実装したいところです。
48.プレスリリースを出した
定期的にプレスリリースを出すことによりサイテーションを獲得しました。中には、Do followリンクを獲得するケースもあり、効果的な外部対策として有効であることがわかりました。
49.リンク営業が来たので対応した
リンク営業が来たので、お互いの相互リンクを行ったところ、そのページのキーワードでランクイン上昇がみられました。
50. Xにサイトの記事を投稿した
Ⅹにサイトの記事を投稿して、サイトへ誘導したところ、サイトへのセッション数が増えました。Ⅹはタグ検索で表示され、サイトはSEO枠で表示されて可視性が高まりました。
まとめ
 今回は、2024年の最新のアルゴリズムの研究のために日々行っている実験と検証結果から考えられる効果のあるSEO対策を50ピックアップしました。必ずこの項目の修正をすれば検索ランキングが上がるとは断言できませんが、弊社の検証ではランキング向上が見られた対策を優先的にご紹介しました。個々のサイトの条件は異なっておりすべての項目を普遍的事実としてはお伝え出来ませんが、参考程度にしていただければ幸いです。また、100サイトでの検証は、実際運営されているメディアやサテライトサイトで行いました。1~14の施策は、80%以上でランキングが上がった施策です。15~25に関しては、それ1つの施策というわけではありませんが、何個かの施策を組み合わせて対策して概ねランキング上昇が確認された施策です。是非、参考にしてみてください。
今回は、2024年の最新のアルゴリズムの研究のために日々行っている実験と検証結果から考えられる効果のあるSEO対策を50ピックアップしました。必ずこの項目の修正をすれば検索ランキングが上がるとは断言できませんが、弊社の検証ではランキング向上が見られた対策を優先的にご紹介しました。個々のサイトの条件は異なっておりすべての項目を普遍的事実としてはお伝え出来ませんが、参考程度にしていただければ幸いです。また、100サイトでの検証は、実際運営されているメディアやサテライトサイトで行いました。1~14の施策は、80%以上でランキングが上がった施策です。15~25に関しては、それ1つの施策というわけではありませんが、何個かの施策を組み合わせて対策して概ねランキング上昇が確認された施策です。是非、参考にしてみてください。